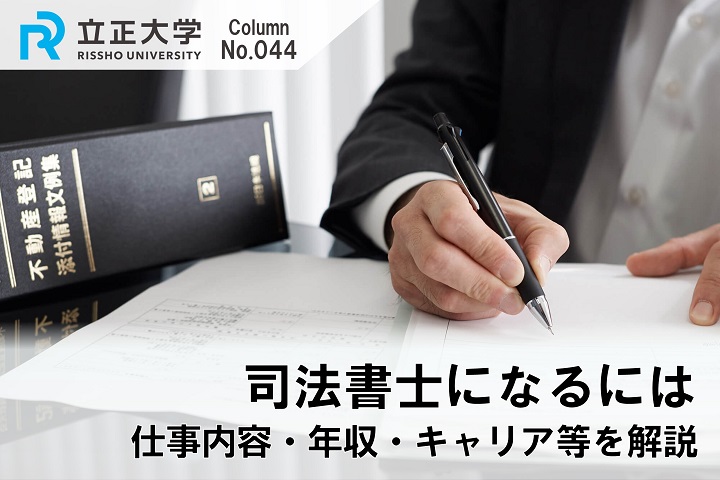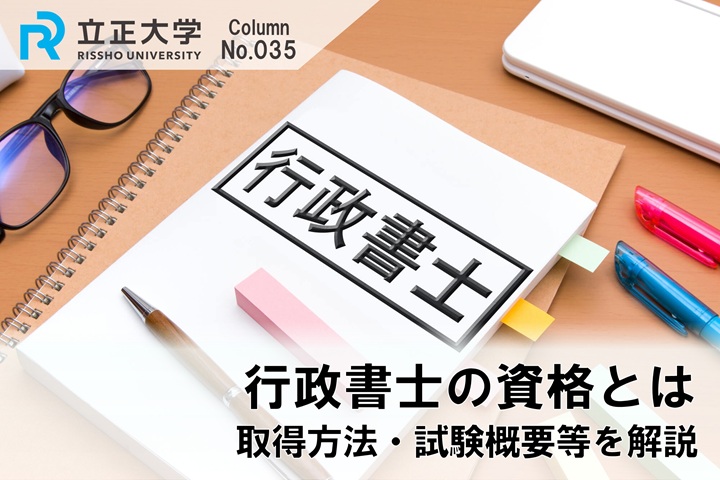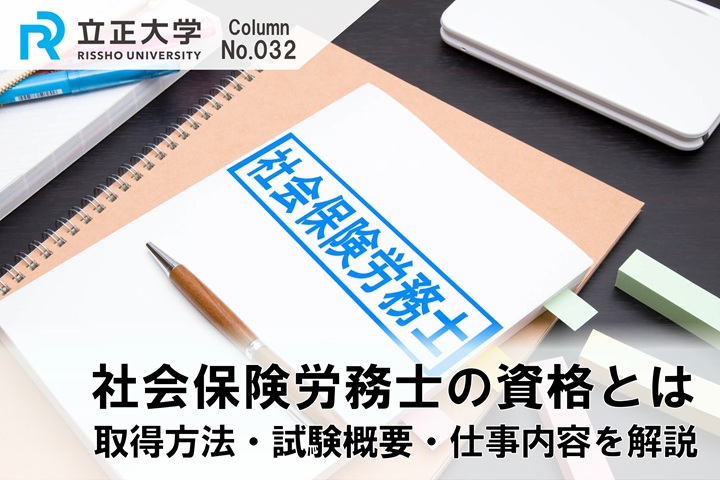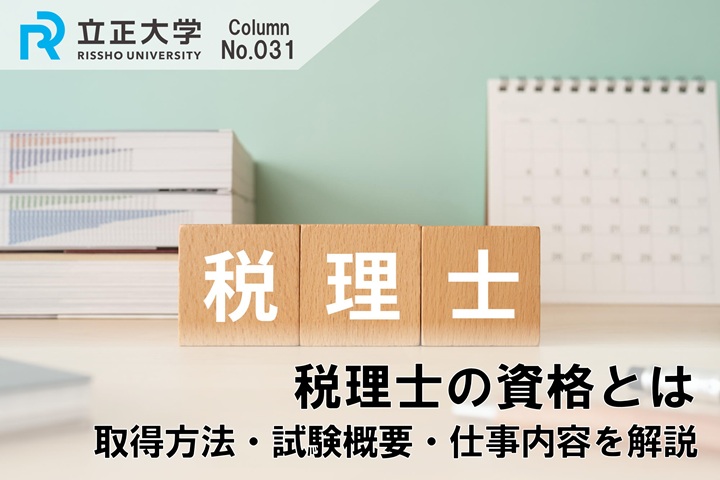法学に関する仕事や資格とは 立正大学法学部で学べること
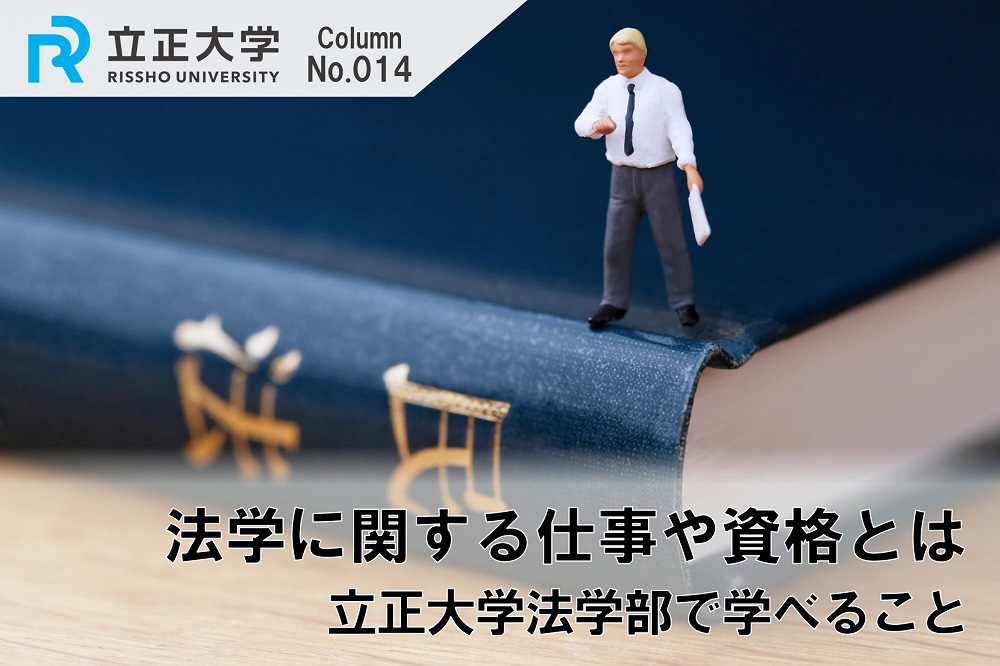
主に法律について研究する法学ですが、実際にはどんなことを学ぶのでしょうか?
また、法学の知識はどのような仕事・就職先で生かすことができるのでしょうか。
今回は、法学とは何か、大学の法学部で学ぶことを具体的に解説します。
加えて、立正大学 法学部で学べることも紹介しつつ、法学を学んだ先でどのような仕事・就職先に生かせるか、さらに法学に関する資格についても紹介します。
法学に興味のある方や、法学部への進学を考えている学生さんはぜひ最後までご覧ください。
法学とは
法学とは、法律について学ぶ学問です。
憲法・民法・商法・民事訴訟法・刑法・刑事訴訟法の六法を中心として法律そのものを知るだけでなく、法律が制定された歴史的背景を学ぶことや、事件や問題を解決するために法律をどのように活用するかを考えることも、法学に含まれます。
法学を研究する具体的な手法として代表的なのが、「解釈論」と「立法論」です。
解釈論では、現在ある法律を駆使して問題解決を図るのに対して、立法論では、新しい法律を作ることで解決を図ります。
言い換えれば、解釈論では施行されている法律の解釈を深めることを主に行いますが、立法論ではそもそも現在の法律が社会に適合しているのかを考えます。
なお、「法学では法律を暗記しなければいけないの?」といった疑問がよく見られますが、法律を暗記する必要はありません。
法学は、法律そのものの知識よりも、法律をどのように活用して、どのように問題を解決するかという思考を養うことが重視される学問です。
そのため、実際の判例について、用いられた法律を参照しながら理解を深めていくのが主な学び方となっています。
法学部で学ぶこと

大学の法学部では、主に法学のほかに政治学を学ぶことが多いです。
法律と政治は非常に深い関係にあります。法律を理解する上で、その法律が生まれる要因となった政治を学ぶことは欠かせません。
政治学では、主に政治の歴史や公共政策、さらに世界中の法律や政治を学びます。
また大学の法学部では、法学や政治学そのものだけでなく、将来法学部での学びを社会で役立てられるよう、リーガルマインドを養うことも重視されます。
リーガルマインドとは「法的思考力」のことです。物事を法的な視点から、客観的に分析する能力を指します。
さらに、法学の知識をそのまま仕事にできるよう、行政書士や司法書士などの資格取得を意識した講義が開かれている場合も。
基本的な学修の進め方としては、1年次に法学の基礎を修得し、2年次に法の制度や概念など専門的な知識を修得、3・4年次に専門的な知識を応用する力を身に付ける、というのが一般的です。
具体的な講義の科目としては、「法学入門」から始まり、「憲法」「民法」などの六法のほかにも「保険法」や「労働法」などメジャーな各法を学べる講義が設置されていることが多いです。
さらに、「政治学」に関する科目や、法律の歴史に重点を置いた科目も設置されています。
立正大学 法学部で学べること
「法学の森」といわれるように、一口に法学といっても、その分野はきわめて広大です。また、法学部出身者の活躍の場は、公務員、民間企業、各種士業など、実に幅広く用意されています。そのため、立正大学法学部では、学生が将来の進路に応じて体系的に学修を進められるようにするため、社会公共コース、ビジネス法コース、特修コースの三つのコースを用意しています。多くの高校生にとって、法学は未知の学問であろうと思います。そこで、コースの選択は、大学入学後、1年次の12~1月ごろに行います。大学で法学の講義を受け、あるいは大学生活を送る中で様々な経験や出会いを経たうえで、将来の進路や個々の志向に応じて、所属コースを決定することができます。なお、選択した各コースの特徴に合わせて設定されているいくつかの科目を履修することが求められていますが、どのコースに所属していても、法学部開講のほとんどすべての科目を履修することができます。したがって、コース選択後に将来の希望進路が変わったとしても、問題なく対応できます。
立正大学法学部の特長は、徹底した少人数教育、大学内にとどまらないフィールドワーク、経験豊かな実務家による教育とともに、現代社会の諸問題に即応した科目の充実にあります。また、法学部独自に多彩な課外講座が展開されてもいます。立正大学法学部は、正課および課外での教育により、学生の希望進路の実現を後押しするだけでなく、リーガルマインド(法的思考力)を身につけた一人の社会人として社会や地域に貢献できる人材の育成に尽力しています。
- 学びの特徴
- 基礎を学んだ上で3つのコースを選択
法学を生かせる職業は多岐にわたるため、基礎学修やさまざま経験・出会いを経た後、1年次12月に進路や志向に応じたコースを選びます。 - ステップアップ方式で入門から応用まで修得
憲法、民法、刑法等の主要な科目は、入門講義→専門講義→応用講義と、段階的に履修。難解な法学の知識や論理を基礎からしっかり学びます。 - 授業で実務を体験し実戦経験を積む
国会議員秘書や地方公務員、士業等でのインターンシップで実務を体験します。実務家による「実務実習」では業務に必要な技術を学びます。
- 基礎を学んだ上で3つのコースを選択
-
3コース制
立正大学 法学部では、学生それぞれの将来の進路に応じて、2年次から3つのコースに分かれて学びを深める仕組みになっています。
1年次には法学部の全学生が基本となる法律を学び、2期(後期)にコースを決定するため、立正大学で学ぶ中で得た興味・関心に沿って選ぶことももちろん可能です。- 社会公共コース <公的機関等における法律を学ぶ>
社会公共コースは、国家公務員や地方公務員、警察官、消防官などの公務員や、行政書士や税理士などの士業を志す学生に最適なコース。
中学校や高校の教員や、NPOなどの団体職員として必要となる知識も習得できるので、これらを目指す学生にもおすすめです。
国や地方自治体の運営において必要とされる法律知識を身に付けながら、人権意識や国際感覚を磨けるコースになっています。 - ビジネス法コース <社会で必要な法的知識を修得>
ビジネス法コースは、民間企業への就職、あるいは自ら会社や事業を立ち上げることを目指す学生にぜひ選んでもらいたいコースです。
士業の中でも、司法書士や社会保険労務士など、企業活動に関わる法律専門家を目指す学生にもおすすめ。
契約、財産、会社や労働問題など、生活をしていく上で必要になる法的知識を修得できます。 - 特修コース <双方向で多様な価値観を学ぶ>
特修コースは、特定の進路を意識したコースというより、授業形式が双方向型・少人数講義と特徴的なのが魅力のコースです。
教員と学生、学生と学生の距離が近いのは立正大学 法学部全体の強みですが、特修コースはその強みを最大限生かしたコースになっています。
ディスカッションなどを通し、多様な価値観やバランス感覚を修得することで、現代社会の諸問題に取り組んでいきます。
- 社会公共コース <公的機関等における法律を学ぶ>
-
資格取得・就職支援体制
資格取得やキャリア形成の支援体制が充実しているのも、立正大学 法学部の魅力です。
まず、公務員志望の学生向けには、学外の予備校講師を招いての「公務員課外講座」を展開しています。学外の授業と同じクオリティの授業を低価格で受けられるのが魅力です。
受講生には、国家公務員試験や地方公務員試験(上級職)、国税専門官試験、裁判所事務官試験など、難関といわれる公務員試験に合格した学生も多数います。
ほかにも、「行政書士講座」や「宅建課外講座」など、士業を目指す学生向けの資格取得支援講座を開講しているだけでなく、民間企業への就職を目指す学生には「民間就活入門講座・就活徹底サポート講座」を開講。
特定の資格を取得したり、検定に合格したりした学生に対して、課外講座を割安で受講できるようにする「受講料割引制度」や、各種資格試験・検定試験に合格した学生に一定の金額の法学部奨励金(図書カード)を給付する「資格取得奨励制度」、さらに課外講座を開講していない士業資格の取得を目指す学生に学習支援(図書カードの給付)を行う「士業学修奨励特別補助制度」など、立正大学 法学部は資格取得やキャリア形成の支援体制が盛りだくさんです。
法学に関する資格
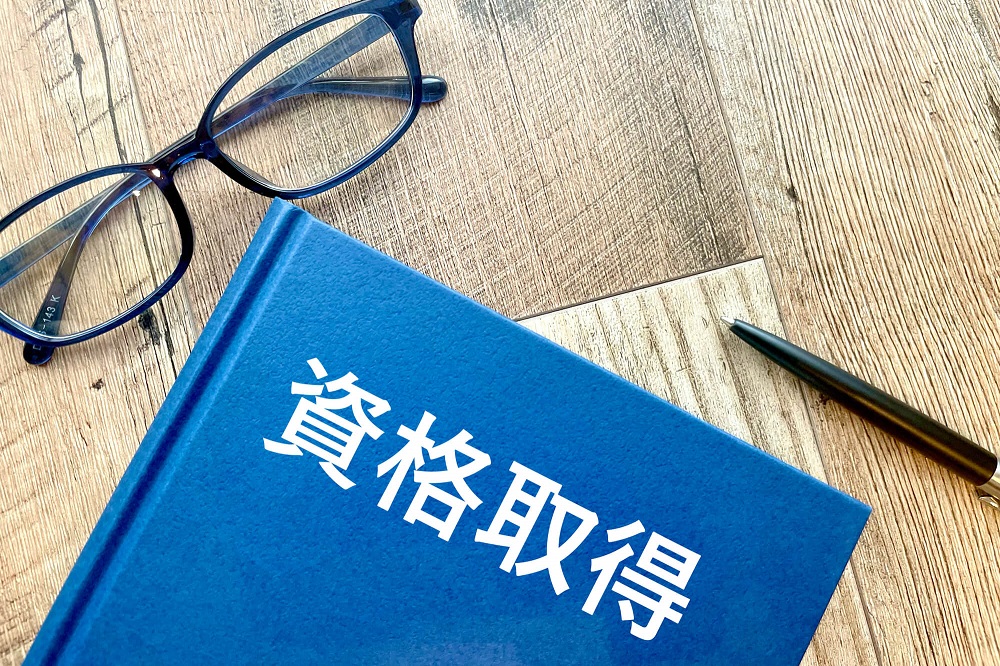
法学に関する資格には、どのようなものがあるのでしょうか。
ここからは、法学に関する資格で、主に国家資格を紹介します。
-
弁護士(司法試験)
法律を扱うスペシャリストのトップに位置するのが弁護士です。
弁護士は、主に刑事事件で被疑者や被告人の弁護活動を行う印象が強いですが、民事事件を解決に導いたり組織の法律遵守をサポートしたりと、活動の幅は非常に広いです。
弁護士になるには、法科大学院を卒業もしくは予備試験に合格した上で、司法試験に合格する必要があります。
司法試験はここ数年の合格率が4割程度で、受験資格を得るハードルの高さを考えると非常に難易度の高い資格といえるでしょう。
-
司法書士
司法書士は、主に登記業務や供託業務を担います。
登記業務とは、権利関係などについて国が管理する登記簿に登録し、公に示すための手続き。供託業務とは、国家機関である供託所に金銭などを預けることで、本来支払うべき相手に直接支払っていなくても、通常どおり支払いを行ったと認めてもらう手続きを指します。
司法書士になるには、司法書士試験に合格する必要があります。
受験資格は特になく、誰でも受験できますが、合格率は例年3〜5%と非常に低いです。
司法書士については以下のコラムで詳しく解説しておりますので、興味のある方はぜひ読んでみてください。
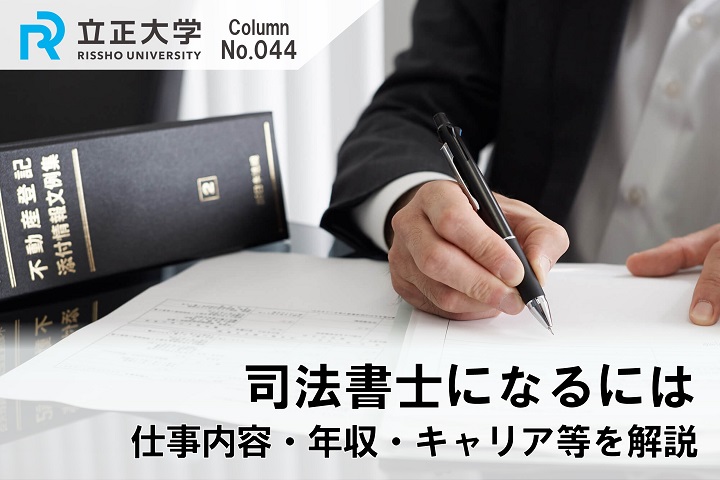
司法書士になるには 仕事内容・年収・キャリア等を解説
記事はこちら出典:司法書士を目指す人へ日本司法書士会連合会ホームページ
-
行政書士
行政書士は、法律に関係する書類作成業務や許認可申請の代理などを行います。
書類作成業務については、官公庁に提出する書類のほか、企業の会計帳簿や個人の遺言書などを作成することができ、幅広く活躍します。このような書類作成業務は、行政書士の独占業務です。
行政書士になるには、受験資格なしの行政書士試験に合格するほかにも、弁護士・弁理士・公認会計士・税理士の資格をすでに持っている場合は、行政書士会に登録するだけで行政書士として活動できるようになります。
行政書士については以下のコラムで詳しく解説しておりますので、興味のある方はぜひ読んでみてください。
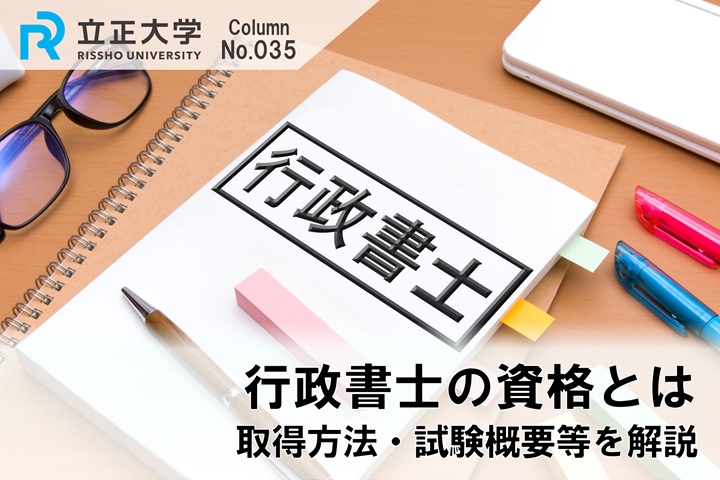
行政書士の資格とは 取得方法・試験概要等を解説
記事はこちら出典:行政書士になるには日本行政書士会連合会ホームページ
-
税理士
税務書類の作成・税務代理・税務相談の3つの業務は、税理士だけが行える独占業務です。
税理士になるには税理士試験に合格する必要がありますが、受験するには一定の受験資格を満たさなければなりません。
学識・資格・職歴の3つの分野のうち、いずれか1つの要件を満たせば受験資格が得られますが、例えば学識では「社会科学に属する1科目を履修した上で大学を卒業する」などがあり、比較的容易に受験資格を得られます。
ただし、税理士資格を得るには通算2年以上の租税や会計に関する実務経験が必要で、試験合格前の経験でも認められます。
税理士については以下のコラムで詳しく解説しておりますので、興味のある方はぜひ読んでみてください。
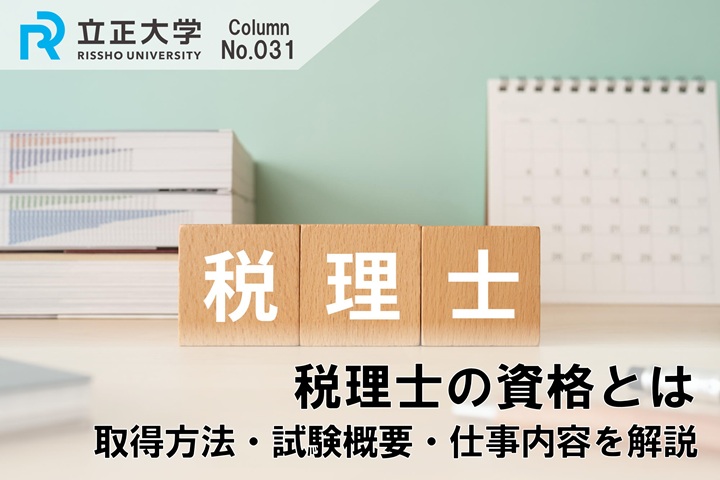
税理士の資格とは 取得方法・試験概要等を解説
記事はこちら -
社会保険労務士
社会保険労務士は、企業の労働分野をサポートします。
例えば、雇用保険や社会保険の加入手続きの代理や、就業規則や給与規則などの帳簿作成は社会保険労務士の独占業務です。
社会保険労務士になるには、社会保険労務士試験への合格と、2年以上の実務経験もしくは指定された講習を修める必要があります。
受験資格はいくつかありますが、大学を卒業していれば受験することが可能です。
社会保険労務士については以下のコラムで詳しく解説しておりますので、興味のある方はぜひ読んでみてください。
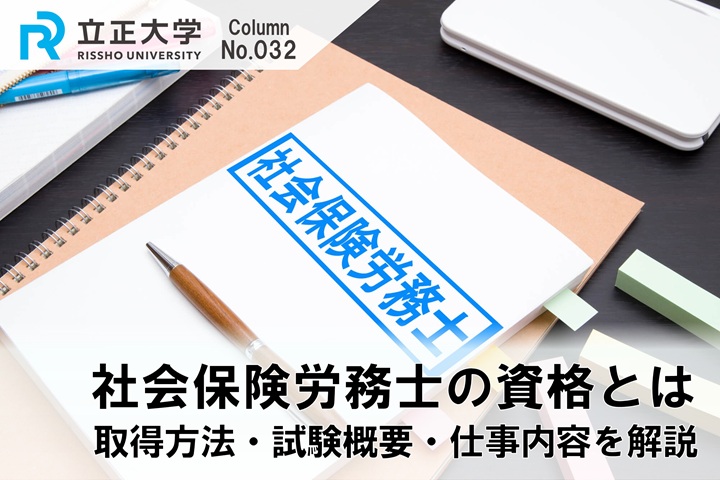
社会保険労務士の資格とは 取得方法・試験概要等を解説
記事はこちら -
宅地建物取引士
宅地建物取引士は、不動産取引のスペシャリストです。
例えば、不動産の売買時や賃貸借契約の締結時に行う重要事項説明は、宅地建物取引士にしか許可されていません。
宅地建物取引士になるには、宅地建物取引士試験への合格と、2年以上の実務経験もしくは指定された講習の修了が必要です。
試験の受験資格はなく、誰でも受験できます。
法学を生かせる仕事・就職先

法律に関する知識や技術は、どのようにして活用できるのでしょうか。
ここでは、法学を特に生かせる仕事や就職先を紹介します。
-
法曹
法曹は、裁判官・検察官・弁護士の3つの職業を指します。
裁判官は裁判で公正な判決を下すこと、検察官は事件の捜査や取り調べ、被疑者の起訴などが主な仕事内容です。弁護士は、上記のとおり刑事事件や民事事件で弁護活動や問題解決へのサポートを行います。
どれになるにしても、司法試験に合格しなければならないため、簡単ではありません。
しかし、3つとも法律の専門家としてトップに位置する職業です。
-
士業
士業とは、主に弁護士や弁理士、司法書士、税理士、行政書士、社会保険労務士などを指します。
それぞれ、専門的に取り扱う法律の分野が異なりますが、どの士業も人々の生活や企業の活動には欠かせない仕事であり、すべてが国家資格です。
法学を存分に生かせる仕事というと法曹か士業になりますが、士業は法曹よりも難易度が低くなるため、目指しやすい仕事といえるでしょう。
-
公務員
公務員は、常に法令に従って業務を遂行する必要があるため、公務員は法学を生かせる仕事です。
加えて、公務員になるための公務員試験には法律の科目が多くあるため、法学の知識が合格に直結します。
公務員というと国家公務員や地方公務員が浮かびますが、法律に深く関わる公務員の職種としては、裁判所事務官や家庭裁判所調査官補、国税専門官、労働基準監督官、警察官などが代表的です。
-
法務部門
一般企業の法務部門は、法学を生かせる職種です。
法務部門では、主に取引先との契約書類の確認や、企業の法的手続き、社内規定の整備、さらには法律に関する社内相談窓口としての役割など、法律に関する知識が必須な業務を多くこなす必要があります。
例えば新卒で法務部門の社員を採用する場合、法律について研究してきた法学部出身の学生が選ばれることが多くなります。
まとめ
法学とは、法律の内容や歴史について研究しながら、法律をどのように応用するかを学ぶ学問です。
法学を学ぶことで、法曹や士業への道が開けるのはもちろん、企業の法務部門や法遵守が厳しく求められる業界など、法律を扱うさまざまな分野で活用できます。
立正大学 法学部では、学生それぞれの将来像や興味・関心に沿って、2年次から「社会公共コース」「ビジネス法コース」「特修コース」の3コースに分かれて学びを深めます。
充実したキャリア形成支援により、難関といわれる公務員試験や各種士業資格の合格者も多数輩出しています。
法学に興味がある方、法学部への進学を考えている方は、ぜひ以下から立正大学 法学部のホームページもご覧ください。

「法学を学ぶなら」 立正大学 法学部へ
立正大学法学部の特長は、徹底した少人数教育、大学内にとどまらないフィールドワーク、経験豊かな実務家による教育とともに、現代社会の諸問題に即応した科目の充実にあります。また、法学部独自に多彩な課外講座が展開されてもいます。立正大学法学部は、正課および課外での教育により、学生の希望進路の実現を後押しするだけでなく、リーガルマインド(法的思考力)を身につけた一人の社会人として社会や地域に貢献できる人材の育成に尽力しています。
法学部Webサイトへ