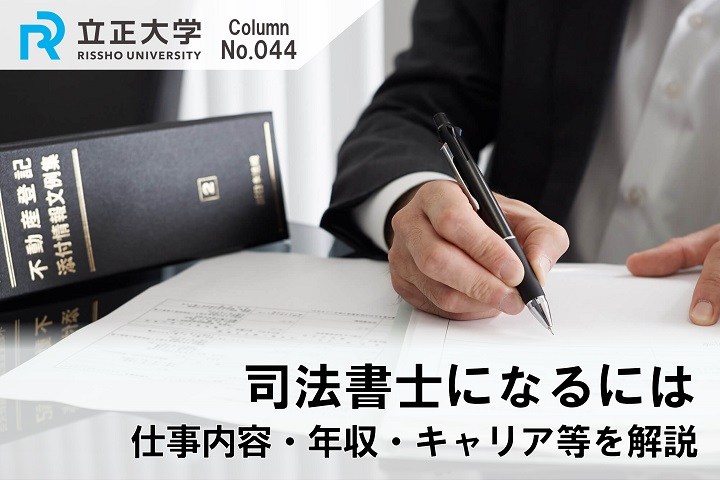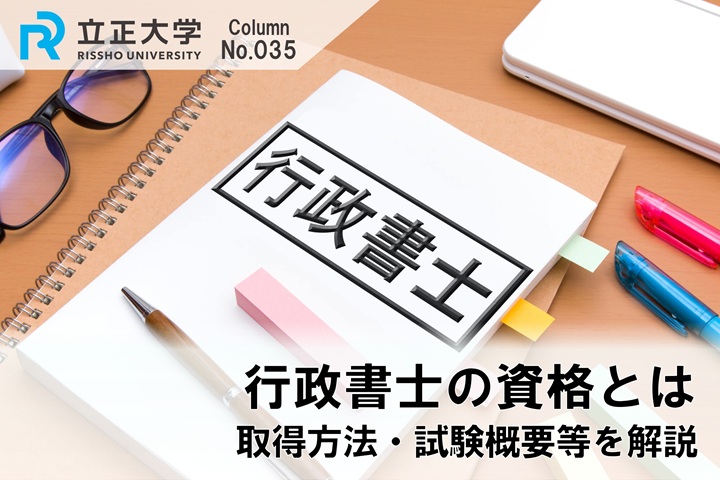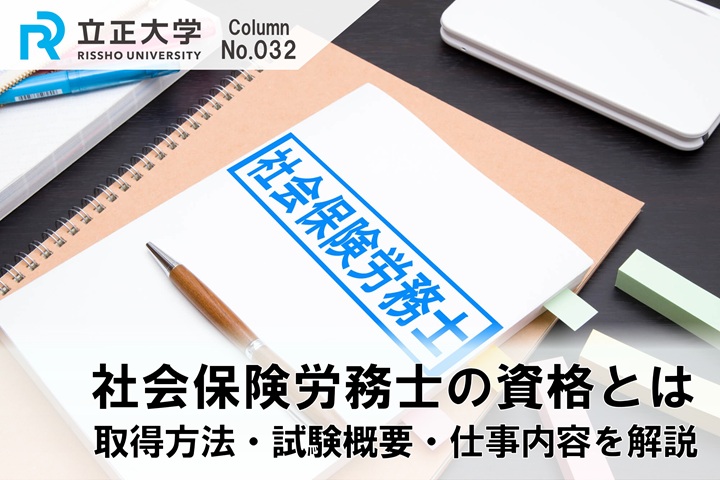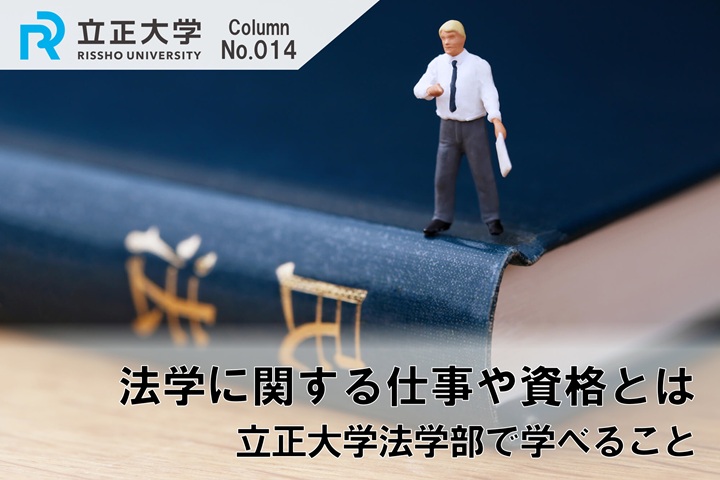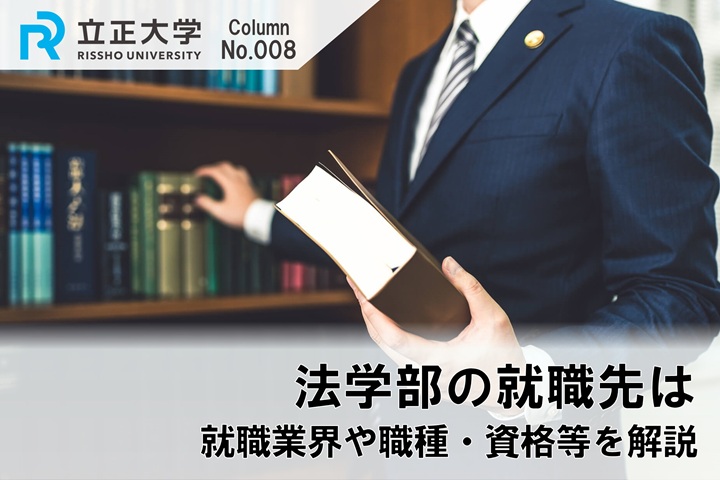法学部の学生におすすめ資格 国家資格・民間資格 19選
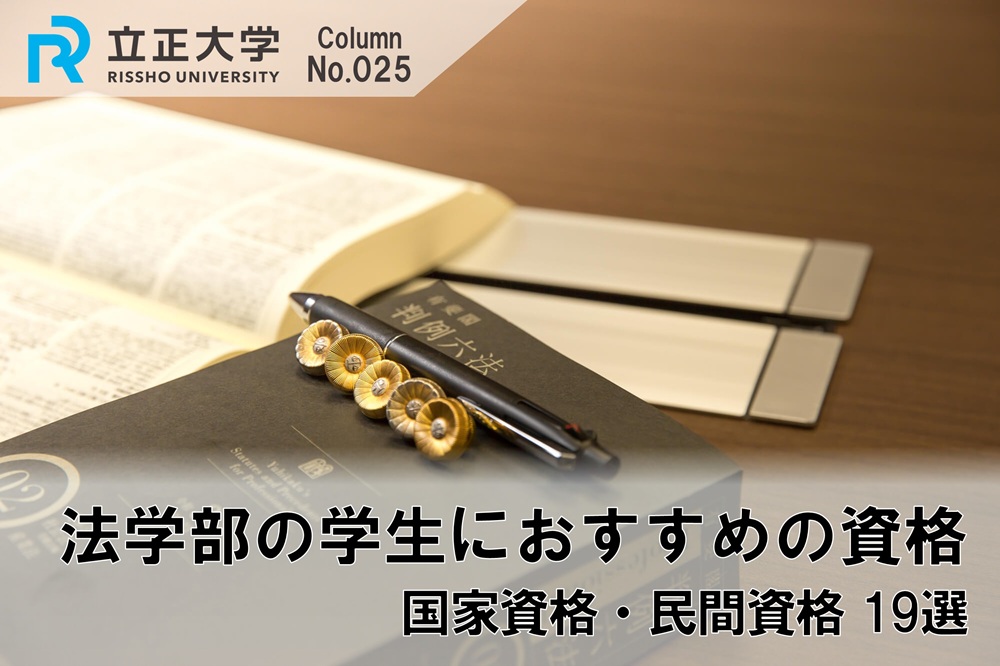
私たちが安全・安心で豊かな生活を送るのに不可欠な「法律」。法律を学ぶ法学に関する資格は、非常に数多く存在します。
そんな中で、大学の法学部生が取得しておくとよい資格には、どんなものがあるのでしょうか?
今回は、法学部の学生におすすめの資格を、信頼性の高い国家資格から実務に役立つ民間資格まで19選ご紹介します。
資格取得を考えている学生さんは、自分の興味や将来の夢に合う資格選びの参考にしてください。
法学部の学生におすすめの資格14選【国家資格】
初めに、法学部の学生におすすめの国家資格を、士業を中心に14紹介します。
国家資格は信頼性が高いのが魅力。受験資格が必要ないものから長い道のりが必要な資格まで、詳しく見ていきましょう。
-
司法書士
司法書士は、身近な暮らしの中の法律家です。登記または供託手続きの代理や、法務局に提出する書類の作成は、司法書士の独占業務となっています。多くの市民が直面する問題として、相続に携わることも多いです。
受験資格はなく、誰でも挑戦できる国家試験です。特に市民に寄り添った活動をしたいと考えている方におすすめの資格です。
司法書士については以下のコラムで詳しく解説しておりますので、興味のある方はぜひ読んでみてください。
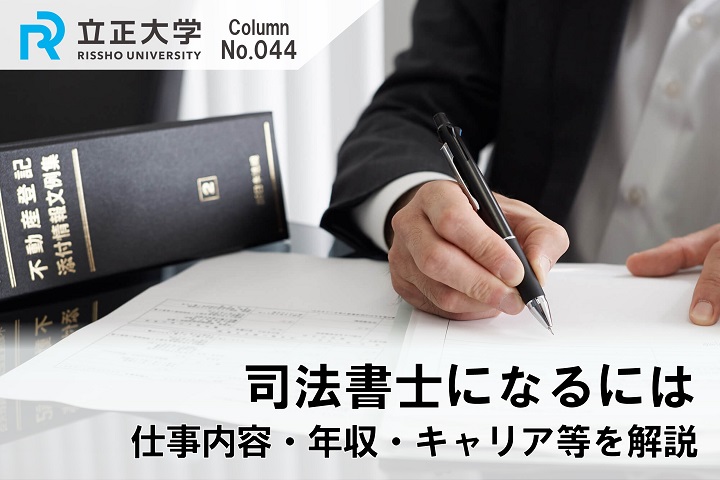
司法書士になるには 仕事内容・年収・キャリア等を解説
記事はこちら出典:司法書士を目指す人へ日本司法書士会連合会ホームページ
-
行政書士
行政書士は、許認可申請や書類作成のスペシャリストです。
「官公署に提出する書類」「権利義務に関する書類」「事実証明に関する書類」の3つの作成が独占業務となっており、例えば飲食店営業許可申請や、遺言書の作成、会社の会計帳簿の作成などが挙げられます。
行政書士も、受験資格はありません。主に書類関係の仕事で活躍したい方におすすめです。
行政書士については以下のコラムで詳しく解説しておりますので、興味のある方はぜひ読んでみてください。
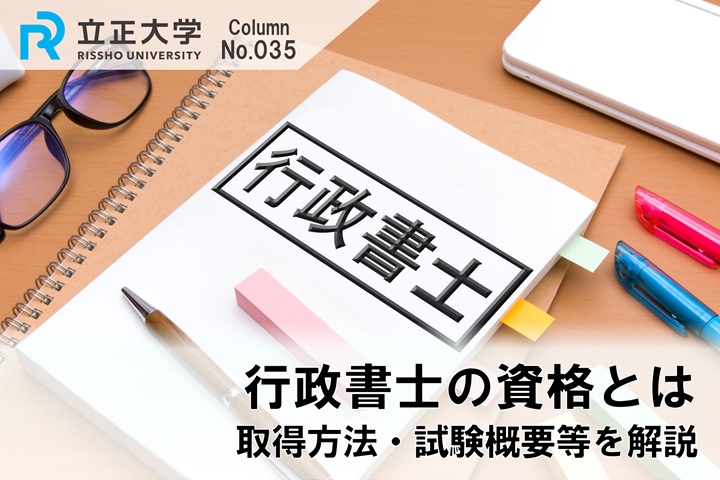
行政書士の資格とは 取得方法・試験概要等を解説
記事はこちら -
社会保険労務士
社会保険労務士は、企業の労働や社会保険を支えるスペシャリストです。
労働保険や社会保険に基づく申請書の作成や提出、帳簿作成などの代行は、社会保険労務士の独占業務です。
大学や短期大学を卒業していれば、受験資格を得られます。また、司法書士や行政書士といった国家資格をすでに持っていれば、学歴などの要件を満たしていなくても受験可能です。
社会保険労務士については以下のコラムで詳しく解説しておりますので、興味のある方はぜひ読んでみてください。
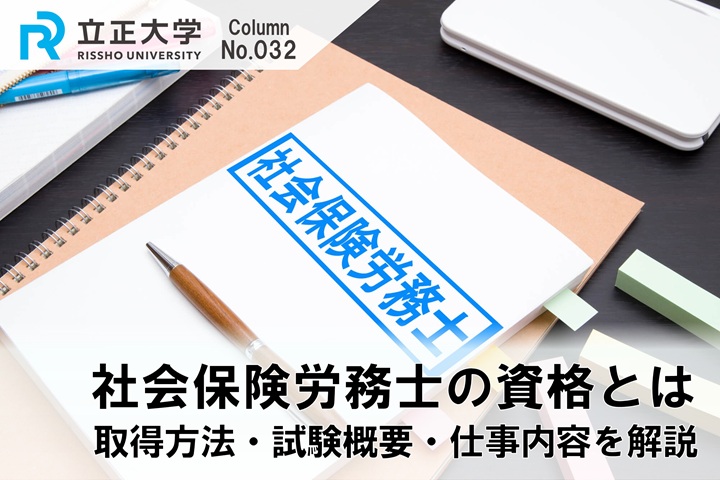
社会保険労務士の資格とは 取得方法・試験概要等を解説
記事はこちら出典:社会保険労務士試験とは全国社会保険労務士会連合会 試験センターホームページ
-
宅地建物取引士
宅地建物取引士は、不動産取引のスペシャリストです。
不動産取引における「重要事項の説明」「契約書の記名」などは、宅地建物取引士の独占業務です。
受験資格は特にありません。不動産業界で活躍したい方は、ぜひ取得しておきたい資格です。
出典:宅建試験一般財団法人不動産適正取引推進機構ホームページ
-
不動産鑑定士
不動産鑑定士は、家や土地などの不動産の価値を鑑定するスペシャリストです。不動産自体の価値から市場の需要まで、幅広い視点から鑑定を行います。
宅地建物取引士よりも難易度が高いですが、不動産鑑定士は令和6年1月時点で9千人弱しかおらず、100万人を超える宅地建物取引士よりも希少価値が高いです。業務の幅も広くなるので、宅地建物取引士→不動産鑑定士といった順でダブルライセンスを目指すのがおすすめです。
不動産鑑定士も、受験資格はありません。
出典:土地・不動産・建設業:不動産鑑定士試験国土交通省ホームページ
-
土地家屋調査士
土地家屋調査士も不動産業界におけるスペシャリストですが、宅地建物取引士とは異なり「登記申請手続き」や「土地の筆界特定」を主な業務とします。
測量などの現地調査も、土地家屋調査士の大切な仕事です。
土地家屋調査士も、受験資格はありません。一般的に、宅地建物取引士や不動産鑑定士よりも、土地家屋調査士のほうが難易度が高いといわれています。
出典:土地家屋調査士試験法務省ホームページ
-
税理士
税理士は、税のスペシャリストです。
「税務の代理」「税務書類の作成」「税務相談」は税理士の独占業務となっており、企業から個人まで幅広い顧客を対象に業務を行います。
税理士試験は、科目によって受験資格があるものとないものがあり、例えば「大学3年次以上で、社会科学に属する科目を1科目以上含む62単位以上を取得」が受験資格の要件の一つです。
全11科目中5科目を選んで受験する仕組みですが、各科目は一度合格すれば生涯有効なので、何年かかけて合格を目指すのが主流となっています。
税理士については以下のコラムで詳しく解説しておりますので、興味のある方はぜひ読んでみてください。
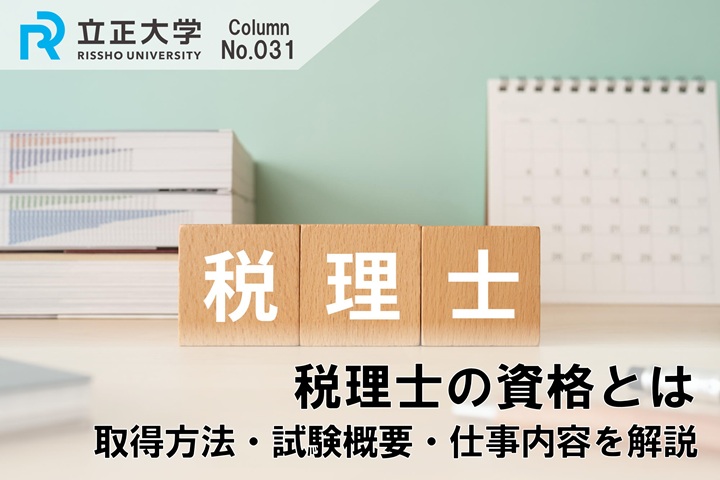
税理士の資格とは 取得方法・試験概要等を解説
記事はこちら出典:税理士を目指す方へ東京税理士会ホームページ
-
公認会計士
公認会計士は、会計や監査のスペシャリストです。
特に「監査」は独占業務となっており、企業の財務諸表が公正なものであるかを確認したり、アドバイスしたりします。ほかに、会計や税務に携わることも多いです。
受験資格は特にありませんが、公認会計士として登録されるには、試験に合格後3年以上の実務経験を積まなければなりません。公認会計士の方は、指定の研修を受けることで税理士試験を受けることなく税理士としても登録できるようになります。
出典:公認会計士とは日本公認会計士協会ホームページ
-
海事代理士
海事代理士は海に関する法律のスペシャリストで、「海の司法書士」「海の行政書士」と呼ばれることもあります。
令和7年時点で総数3,500人程度しかいない一方、「船舶国籍証書取得」「船舶検査」など弁護士も行うことができない独占業務があり、価値の高い資格です。
受験資格はありません。海に関連した仕事がしたい方には、特におすすめの資格といえます。
出典:海事代理士になるには国土交通省ホームページ
-
通関士
通関士は、貿易業界唯一の国家資格です。「通関書類の審査」「通関書類への記名・捺印」は独占業務で、主に外国からの輸出入時に通関手続きを行います。
受験資格はありません。貿易業界で活躍できる資格なので、貿易や流通に携わる商社への就職を志している人にもおすすめの資格です。
出典:通関士試験財務省ホームページ
-
弁理士
弁理士は、知的財産のスペシャリストです。
特許や実用新案、意匠、商標に関する代理業務、例えば特許庁への商標登録の出願代行は、弁理士の独占業務です。
受験資格はありません。弁理士の資格を取ると、特許事務所のほか一般企業や法律事務所の知財部への就職が有利になります。
出典:弁理士試験経済産業省 特許庁ホームページ
-
知的財産管理技能検定
知的財産管理技能検定は、技能検定の中の「知的財産管理」という職種に関する国家試験です。合格者は「知的財産管理技能士」という国家資格を得られます。
知的財産を管理する技能、すなわち「知財マネジメント」スキルの習得レベルを測定・評価し、証明する資格です。
難易度が低い順から3級・2級・1級があり、3級は特に受験資格がないものの、2級・1級では3級や2級に合格していることや、場合によって実務経験を求められるので、試験を受ける際にはよく確認しておきましょう。
-
弁護士
最後にご紹介するのが、法律全般のスペシャリストである弁護士です。
日本最難関といわれる司法試験を合格した後、1年間の司法修習を受けることで弁護士資格を得られます。
受験資格は大まかに2通りで、「法科大学院の修了」か「予備試験の合格」です。「予備試験の合格」は受験資格こそないものの、合格率が3~4%前後と非常に難易度が高いです。
一方で、司法試験自体の合格率は令和6年の司法試験で42.13%でした。受験資格のハードルが高いだけあって、予備試験よりもはるかに大きい数字です。
長い道のりが必要ではありますが、士業の最高位にある弁護士に憧れる方は多いのではないでしょうか。
出典:弁護士になるには日本弁護士連合会ホームページ
法学部の学生におすすめの資格5選【民間資格】

法学部の学生には、士業などというよりは一般企業に就職したい方も多いはず。そんなとき、実務に役立つスキルを身に付けられる民間資格が役立ちます。
ここでは、法学部の学生におすすめの民間資格を5つ紹介します。
-
ビジネス実務法務検定
ビジネス実務法務検定は、法務部門に限らず営業や販売、総務、人事など、あらゆる職種で必要とされる法律知識を身に付けられる検定です。
企業活動の主要分野を多くカバーしていることから業種も問わないとされているため、一般企業への就職を目指すすべての法学部生におすすめといえます。
難易度が低い順から3級・2級・1級と用意されており、3級・2級は自宅のパソコンからでも受けられますが、1級は各地のテストセンターで統一試験を受ける必要があります。
出典:ビジネス実務法務検定試験®東京商工会議所ホームページ
-
個人情報保護士
個人情報保護士は、個人情報の保護に精通し、適正な取り扱いや安全管理を身に付けたエキスパートである証明ができる認定試験です。
今やすべてのビジネスパーソンに求められる個人情報保護法への理解を、正しく深められます。
難易度は1種類のみで、公開会場受験・自宅のパソコンで受けるオンラインIBT受験・全国のテストセンターのパソコンで受けるCBT受験のいずれかから受験方法を選べます。
開催元の一般財団法人 全日本情報学習振興協会は、ほかにも「マイナンバー実務検定」「情報セキュリティ管理士」などさまざまな認定試験を実施しているので、興味がある方は併せて確認してみてください。
出典:個人情報保護士認定試験一般財団法人 全日本情報学習振興協会ホームページ
-
法学検定
法学検定は、法学に関する知識を客観的に評価してもらえる検定です。
難易度が低い順から、ベーシック〈基礎〉コース・スタンダード〈中級〉コース・アドバンスト〈上級〉コースの3つのコースがあり、自分の法学の知識がどの程度あるかを証明できます。
試験は全国の一般会場または団体会場で実施されます。勉強の際は、公式問題集・過去問集を利用するのがおすすめです。
出典:法学検定公益社団法人 商事法務研究会ホームページ
-
ビジネス著作権検定
ビジネス著作権検定は、著作権に特化した検定です。
従来「守らねばならない」という意識の強かった著作権ですが、現在では適切な権利処理を行った上で著作物を活用することこそ、新たなビジネスチャンスを生み出すと考えられています。この検定は、そのような「著作権を適切に活用する」ための知識を養えるものです。
難易度は初級と上級があり、試験形式はどちらも「リモートWebテスト」による在宅試験形式です。
出典:ビジネス著作権検定株式会社サーティファイホームページ
-
マイクロソフト オフィス スペシャリスト(MOS)
マイクロソフト オフィス スペシャリスト(MOS)は、一般企業の多くで使用されているMicrosoft Office製品の知識・操作スキルを証明できる資格試験です。
Word、Excelなどの製品ごと、バージョンごと、さらに一部製品については「一般レベル」と「上級レベル」の難易度ごとに分かれています。おすすめはWord、Excel、PowerPointの3つで、可能な限り最新バージョンで上級レベルを受けましょう。
毎月1~2回の全国一斉試験と、ほぼ毎日実施されている随時試験のどちらかを選べます。なお、どちらも指定の試験会場に出向いて試験を受ける形です。
出典:MOS公式サイト—マイクロソフト オフィス スペシャリスト株式会社 オデッセイコミュニケーションズホームページ
立正大学 法学部について

立正大学には、法学部があります。立正大学の法学部は品川キャンパスにあり、JR山手線の大崎駅または五反田駅から歩いて5分の好立地にあるのが魅力の一つです。
「法学の森」といわれるように、一口に法学といっても、その分野はきわめて広大です。また、法学部出身者の活躍の場は、公務員、民間企業、各種士業など、実に幅広く用意されています。そのため、立正大学法学部では、学生が将来の進路に応じて体系的に学修を進められるようにするため、社会公共コース、ビジネス法コース、特修コースの三つのコースを用意しています。多くの高校生にとって、法学は未知の学問であろうと思います。そこで、コースの選択は、大学入学後、1年次の12~1月ごろに行います。大学で法学の講義を受け、あるいは大学生活を送る中で様々な経験や出会いを経たうえで、将来の進路や個々の志向に応じて、所属コースを決定することができます。なお、選択した各コースの特徴に合わせて設定されているいくつかの科目を履修することが求められていますが、どのコースに所属していても、法学部開講のほとんどすべての科目を履修することができます。したがって、コース選択後に将来の希望進路が変わったとしても、問題なく対応できます。
立正大学法学部の特長は、徹底した少人数教育、大学内にとどまらないフィールドワーク、経験豊かな実務家による教育とともに、現代社会の諸問題に即応した科目の充実にあります。また、法学部独自に多彩な課外講座が展開されてもいます。立正大学法学部は、正課および課外での教育により、学生の希望進路の実現を後押しするだけでなく、リーガルマインド(法的思考力)を身につけた一人の社会人として社会や地域に貢献できる人材の育成に尽力しています。
ここでは、法学部の大きな魅力である「3コース制」やキャリア形成支援について紹介するので、現在進学先の大学を迷っているという方は、ぜひご確認ください。
-
3コース制
法学部では、2年次から学生それぞれの進路や興味に応じて3つのコースに分かれます。これが「3コース制」です。
1年次には、全員が基本となる法律を幅広く学べるので、大学進学時点で進路があまり定まっていない学生さんも安心です。ここからは、3つのコースそれぞれの特徴をご紹介します。
-
社会公共コース <公的機関等における法律を学ぶ>
公的なフィールドで活躍したい方、すなわち公務員や士業を志望する方におすすめのコースです。公的機関等での職務に欠かせない、人権意識や国際感覚を磨くことができます。
中学校・高校の教員や、NPOなどの団体職員として必要となる知識もしっかりと身に付けられるので、これらを目指す方にもおすすめです。
-
ビジネス法コース <社会で必要な法的知識を修得>
民間フィールドで活躍したい方、例えば民間企業に就職したい方や、自ら事業経営を立ち上げたい方におすすめのコースです。契約、財産、会社や労働問題など、市民生活を営む上で必須となる法的知識を修得し、それを応用する力を身に付けられます。
企業活動に関わる専門家として、司法書士や社会保険労務士を目指す方にもおすすめです。
-
特修コース <双方向で多様な価値観を学ぶ>
特定の進路を意識したコースというよりは、多様な価値観やバランス感覚を修得したい方向けのコースです。
双方向型で少人数の講義が一番の特徴で、学生同士のディスカッションなどを通して現代社会の諸問題に取り組んでいきます。
-
キャリア形成支援
立正大学 法学部は、さまざまな進路を考える学生をサポートする、キャリア形成支援を充実させています。
学外の予備校講師を招いて展開している「課外講座」は、学外の講座と同じクオリティでありながら低価格で受けられるのが魅力です。
例えば、難関といわれる公務員試験である「国家公務員試験」「地方公務員試験(上級職)」「国税専門官試験」「裁判所事務官試験」に合格した受講生も多くいます。
ほかにも、在学中に「司法書士」「行政書士」「社会保険労務士」「宅地建物取引士」などの国家資格を取得した学生もいますし、民間企業への就職を目指す学生向けには、学部独自の「OBによる業界セミナー」を開催。
公務員を目指す方、国家資格の取得を目指す方、民間企業への就職を目指す方…学生それぞれのキャリア形成を支援しています。
課外講座は、進路や資格によって各々開催されているので、詳細やスケジュールは以下をご覧ください。
さらに、各種公務員や士業資格取得を志望する学生には、法学部教員が直接指導する「課外ゼミナール」も3年次から設置しています。
課外ゼミナールに加入すると、法学部課外ゼミ室を利用できたり、自修環境の配慮を受けられたりするのも魅力です。
まとめ
今回は、法学部の学生におすすめの資格を紹介しました。
法律の各分野に特化した国家資格が数多くあるほかにも、特に一般企業で実務につながりやすい民間資格が数多くあることをお分かりいただけたのではないでしょうか。
立正大学 法学部は、1年次に法律の基礎を学んだ後、2年次以降はそれぞれの興味や進路に沿って3コースから選べるカリキュラムになっています。
立正大学 法学部は、ほかの多くの大学よりも少し早く、2年次からゼミナールを開始するのも大きな魅力です。
法学部にご興味がある方は、ぜひ立正大学への入学をご検討ください。

「法学を学ぶなら」 立正大学 法学部へ
立正大学法学部の特長は、徹底した少人数教育、大学内にとどまらないフィールドワーク、経験豊かな実務家による教育とともに、現代社会の諸問題に即応した科目の充実にあります。また、法学部独自に多彩な課外講座が展開されてもいます。立正大学法学部は、正課および課外での教育により、学生の希望進路の実現を後押しするだけでなく、リーガルマインド(法的思考力)を身につけた一人の社会人として社会や地域に貢献できる人材の育成に尽力しています。
法学部Webサイトへ