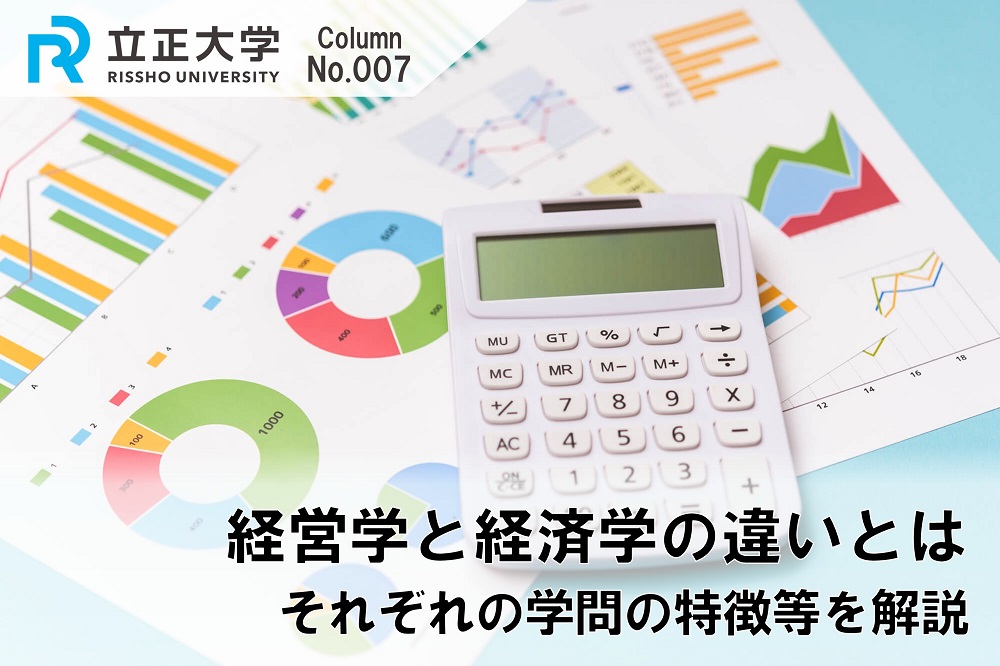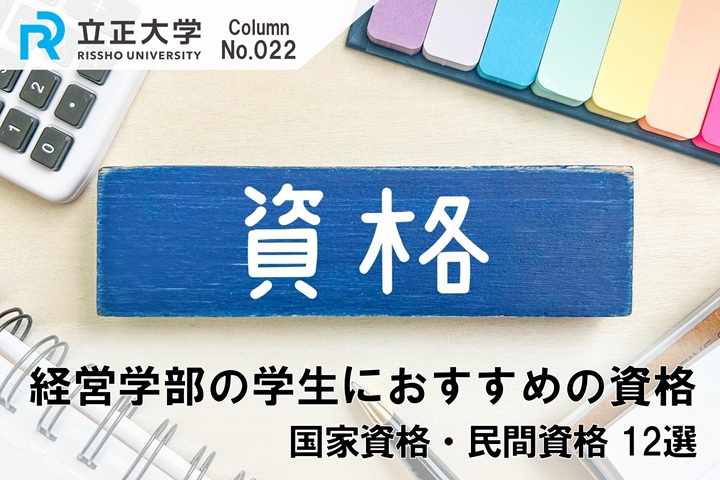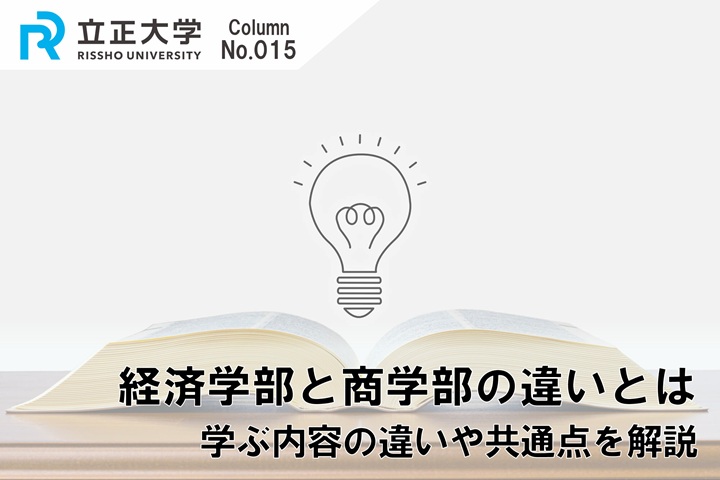経営学と経済学の違いとは それぞれの学問の特徴等を解説
経営学と経済学の違い
経営学と経済学は、いったい何が違うのでしょうか?
ここでは、経営学と経済学それぞれの特徴を解説し、2つの違いを簡単に説明します。
-
経営学とは?
経営とは、会社が事業を運営することをいいます。
経営学とは、会社が事業を運営する中で、どうすれば会社をもっと成長させられるかを研究する学問です。
例えば、会社を経営する上での経営戦略、優秀な人材育成、商品やサービスを売るためのマーケティング、お金のやり取りなどが具体的な研究対象となります。
経営学を学ぶ意義は、よりよい会社づくりや会社の成長に生かせることです。
「会社づくり」というと会社の社長や幹部を目指す人に必要なもの、というイメージかもしれませんが、会社を構成するものの中には社員一人ひとりも含まれています。
よりよい会社づくりを目指す経営学を身に付けておくことで、会社の業績アップや事業拡大にも役立つため、単に会社員を目指す方でも学ぶ意義が非常にあります。
-
経済学とは?
経済とは、人やモノ、お金、サービスなどの流れのことです。
経済学とは、世の中の経済活動を多角的に研究する学問をいいます。
例えば、商品やサービスの価格の決め方、消費者が商品やサービスを購入・利用する要因、景気の動向、為替変動などが具体的な研究対象です。
経済学を学ぶことで、経済活動の仕組みやその変動要因について理解できるようになります。
これにより、会社の経営上の課題が分かったり、今後の社会経済がどのように変化していくか予測できたりするようになることが、経済学を学ぶメリットです。
また、経済活動の仕組みやその変動要因が分かることで、社会経済に存在している課題や今後現れるであろう課題が分かり、解決方法を考えることができるようになるという面から、よりよい社会づくりに生かせる意義もあります。
-
経営学と経済学の違い
経営学と経済学のもっとも大きな違いは、研究の対象といえるでしょう。
経営学が企業の事業運営を対象とするのに対し、経済学は社会の経済活動を対象とします。
具体的にいうと、経営学はいち企業の経済活動について、よりよい経営を目指した研究を行う学問です。
一方で、経済学は経済活動の仕組みについて、国全体の経済活動であったり、生産者や消費者の取引であったり、国家間の貿易だったりと、分野ごとに対象を変えて研究していきます。
とはいえ、経済学でも企業の経済活動に焦点を当て、会社を成長させるにはどうすればいいかを考えることもあるため、経営学は経済学のうちに含まれる、といってもよいかもしれません。
経営学と経済学の共通点と相違点

ここからは、経営学と経済学の共通点や相違点について、比較しながら詳しくご紹介します。
-
学ぶ内容
経営学と経済学は、学ぶ内容が異なります。
経営学では、企業の事業を存続・成長させるための経営戦略や、商品やサービスを売るためのマーケティング、企業のお金に関する会計など、会社経営のための内容を学びます。
経済学で学ぶのは、個人から企業、国、国家間までと、幅広い対象の経済活動の仕組みやその変動要因です。
例えば、生産者や消費者といった個別のグループの経済活動を研究する「ミクロ経済学」や、GDPや物価など国全体の経済活動を研究する「マクロ経済学」、国家間の貿易を研究する「国際経済学」などがあります。
会社経営を学ぶ経営学と、経済活動そのものを学ぶ経済学は、大きく異なる点です。
-
学ぶメリット
経営学と経済学は、学ぶことで得られるメリットに多少の違いがあります。
どちらも、ビジネス感覚が身に付いたり、数字に強くなったりするのは共通のメリットといえるでしょう。しかし、学んだことを最大限活用できる場には違いがあります。
まず、経営学は会社経営のための学問です。事業を存続・成長させるための具体的な方策を学べるため、会社経営に生かしやすいですし、企業の管理部門に登用してもらえる可能性も高くなります。
一方で、経済学は経済活動の仕組みを学ぶ学問です。企業のみならず、国や国家間といった広い視野で経済活動について研究するため、政策や物価など自分と身の回りに大きな影響を与える経済活動の変化があっても、そのメカニズムや今後の見通しを推測できるようになります。
このように、会社経営で大きく活躍できる経営学と、身の回りの経済活動を分析できる経済学とで、メリットには少し違いがあります。
-
就職先
経営学部生と経済学部生の就職先は、ほとんど同じです。
ほとんど、というのは、経済学部生には公務員の選択肢が大きく入ってくるためです。
経済学ではミクロ経済学やマクロ経済学について学ぶのは先述したとおりですが、これは公務員試験で出題される内容でもあります。
実際に、立正大学経済学部の経済学コースは公務員志望の方向けのコースであり、経済学部生の就職先候補には公務員が入ることが多いです。
一方で、経営学は会社経営のための学問ですので、就職先に公務員を選ぶ方は経済学部生よりも少ないでしょう。
公務員以外の一般企業に関しては、経営学部生も経済学部生も変わりありません。商社や金融業界といった就職先が人気の傾向にあります。
-
資格
経営学と経済学の資格は共通しています。代表的な資格は以下のとおりです。
- 簿記…企業のお金の取引を適切に記録できることを認める資格です。
- ファイナンシャル・プランナー…依頼を受けた個人の資金計画をアドバイスする専門家です。
- 宅地建物取引士…国家資格で、不動産の専門家です。
- 税理士…国家資格で、依頼を受けた個人や企業の税に関するサポートを行います。
- 公認会計士…国家資格で、企業の経営状況を監査したり、会計業務を行ったりします。
- 中小企業診断士…国家資格で、中小企業の経営コンサルタントです。
このように、個人や企業の経済活動に携われる資格が数多くあります。
どの資格にも、よりよい経営状況・経済活動を実現するのに貢献できるという共通点があるといえるでしょう。
立正大学の経営学部と経済学部

立正大学には、経営学部と経済学部のどちらもあります。
ここでは、それぞれの特徴についてご紹介します。
-
立正大学 経営学部
『実践力と応用力を身につける、アクティブ・ラーニング』 立正大学経営学部では、理論と実践、理論とスキルとの結合によって、経営学の知識はもちろんのこと、社会で生きる上で必要となる一人ひとりの人間力=共創力を育み、課題を発見・分析・解決する力を身につけます。
まず、理論と実践の結合では実務に密着した学びを深め、理論とスキルの結合では組織でいきる技能として、パソコンの技能や簿記など、経営学の学びに欠かせないスキルの修得や、情報技術・会計技術などの資格の取得に向けた講座の開設で学生のみなさんの学びをサポートします。
また、フィールドワークにも力を入れています。大学の外へ出て、地域活性化のための商品開発やサービスの提案、商店街や企業、官公庁へのリサーチ活動や見学などの調査・研究を行います。
座学で得た知識、フィールドワークで調査・研究した結果をまとめて、ゼミナール発表大会や他大学などでプレゼンテーションを行います。
参考:学びの領域経営学部ホームページ
1年次には経営学の主な分野である「戦略経営」「マーケティング」「会計」「情報システム学」の基礎を学びます。
- 戦略経営…企業が成長し、ほかの企業と競争していくために欠かせない「企業のシナリオ」について学びます。
- マーケティング…マーケティングとは、商品やサービスを売るための活動です。消費者の心理や思考を分析しながら、売れる仕組みづくりについて学びます。
- 会計…会計とは、企業のお金の取り扱いです。経営資金の集め方や、商品やサービスをつくるコスト、お金のやり取りの記録や計算、お金の効率的な使い方などを学びます。
- 情報システム学…企業と情報通信技術(ICT)の現在と未来を考えます。情報分析や業務効率化などの経営とICTの、最適な関係について学びます。
2年次以降は、ゼミを選択して専門分野を学ぶことができます。
パソコンスキルの習得のために、在学生全員に1人1台パソコンを配布してもらえるのが大きな特徴です。
パソコンスキルはもちろん、資格支援プログラムで簿記や情報処理系の資格取得をサポートしてもらえるほか、ビジネス英会話や中国語、ハングルなど、ビジネスシーンで通用する会話力も身に付きます。
会社経営者や有名企業のマネージャーなど、第一線で活躍する経営者による特別講義を受講できるのもポイント。
インターンシップや企業の実態調査などから、実践的な経営学も学べます。
-
立正大学 経済学部
『これからの経済を読み解き、自ら未来を切り拓く経済の専門家を育成』 立正大学経済学部では、複雑な現代社会の構造、変動要因を理解し、自ら課題を発見し解決する力を身につけることを修学の目的としています。
グローバル化、情報化した現代社会で仕事を得て生きていくためには、さまざまな分野の人々と専門的知識を交換することを通じて自己の知的レベルアップをはかりつつコミュニケーション能力を高めることや、英語能力、パソコンの基本操作の習得など、専門領域をこえて求められる「知のインフラ」をしっかり身につけることが、本格的な経済学の専門科目を学ぶことと同様に、重要な側面を持つようになりました。
また、より専門的・段階的に経済学の知識・能力を身につけるには、経済的な動向に対するきちんとした理解が要請されるでしょう。そこで、経済学部のカリキュラムでは、語学や情報処理・基礎演習といった基礎科目を準備し、専門科目においても経済学の入門科目から基幹科目へ、そして応用科目へというように段階的に学習していけるよう体系を整えました。また、立正大学経済学部には学生それぞれの興味や進路によって、「経済学コース」「国際コース」「金融コース」の3コースがあります。
それぞれのコースの特徴や学ぶことを見ていきましょう。
- 経済学コース
経済学コースでは、経済学の幅広い知識を体系的・網羅的に学べます。
特に、ミクロ経済学やマクロ経済学、財政学、経済政策論など、公務員試験で出題される内容についても演習形式で知識を身に付けられるため、公務員志望の方におすすめのコースです。
実際に外に出て、現場の経済に触れられる人気授業「経済フィールドワーク」があるのも経済学の大きな特徴です。
- 国際コース
国際コースは、経済学の知識と実戦的英語力を身に付けた「国際ビジネス人」を目指したコースです。
グローバルな人材として、将来国をまたいで活躍したい方におすすめのコースです。
希望者が短期留学にチャレンジできる「海外語学研修」や、海外の大学生とオンライン英会話ができる授業があります。
- 金融コース
金融コースでは、経済学の知識を身に付けながら、金融・財務の実務に役立つ授業を受けられます。
金融機関や一般企業の財務担当への就職を目指す方におすすめのコースです。
在学中に「日商簿記2級」や「ファイナンシャル・プランナー」、「宅地建物取引士」などの金融・財務関連の資格取得に向けて、サポートを得られるのも特徴です。
- 経済学コース
まとめ
経営学は、会社の事業運営をさまざまな視点から研究し、よりよい会社にしたり、事業をより成長させたりすることを目指す学問です。
経済学は、人やモノ、お金、サービスなどの流れ、すなわち経済活動について多角的に研究することで、その仕組みや変動要因を分析する学問です。
経済学が世の中の経済活動を研究対象とするのに対し、経営学は会社や組織といった個々に焦点を当てて研究するのが大きな違いといえるでしょう。
立正大学には、経営学部と経済学部のどちらもあります。
経営学部では、「戦略経営」「マーケティング」「会計」「情報システム学」の4領域を軸に、1年次に経営学の基礎を学び、2年次からは学生それぞれが選んだゼミで専門分野を研究できます。
経済学部では、学生それぞれの興味や進路に合わせて、「経済学コース」「国際コース」「金融コース」の3コースが用意されています。
経営学部や経済学部への進学を考えている方は、ぜひこちらの立正大学ホームページもご覧ください。