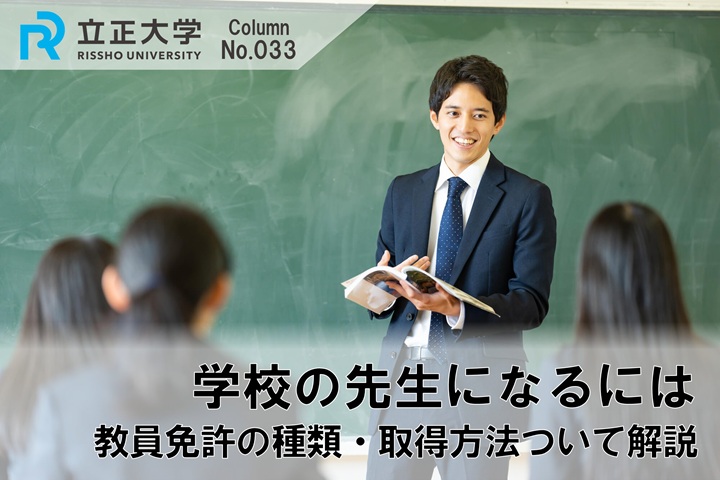気象予報士の資格とは 取得方法・試験概要等を解説(難関資格って本当?)

テレビの天気予報コーナーで見る機会の多い気象予報士。さまざまな気象観測データを解析して気象予報をする気象予報士に、憧れている方は多いでしょう。
気象予報士になるには、国家資格「気象予報士」を取得する必要があります。防災はもちろん、農林水産業、交通機関、流通・販売、イベントなど多様な産業に向けて気象情報を提供する役割が求められ、活躍の場はますます広がっています。
今回は、気象予報士の資格の取り方を一から十まで詳しく解説します。
なぜ気象予報士は難関資格といわれているのか、その理由や気象予報士を目指す道の一つとして、立正大学 地球環境科学部 環境システム学科についてもご紹介します。

「環境・気象関係を学ぶなら」
立正大学 地球環境科学部 環境システム学科へ
5つの分野から環境科学を多角的に学ぶ 【環境生物学/環境地学/環境気象学/環境水文学/環境情報学】 環境システム学科では、地球環境に関わる諸問題について科学的視点で問題の本質を捉えることができ、「持続可能な社会」の形成に貢献できる人材の育成をめざしています。
地球環境科学部 環境システム学科Webサイトへ
気象予報士とは?
気象予報士は、その名のとおり気象予報をする仕事。ここでは、気象予報士の詳しい仕事内容と、気象予報士の資格について解説します。
-
気象予報士の仕事内容
気象予報士は、気象観測データや数値予報資料をもとに、気象予報をする仕事です。
気象予報士といえば、テレビの天気予報コーナーで解説をするウェザーキャスターを思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。実は、テレビに出てくる気象予報士はほんのひと握りで、多くの気象予報士は裏方で活躍しています。
テレビやスマートフォンで天気予報を見て、今日傘を持っていくかを決める。そのような場面で、私たちは天気予報のありがたみを実感しやすいです。
それだけでなく、気象予報は公共交通機関や屋外イベント、農業や水産業といった一次産業などの今後に影響を与えます。また、台風や洪水などが起こった際、気象予報が人命を左右することも。気象予報士の的確で迅速な気象予報は、実は私たちの生活の隅々まで影響を与えているのです。
気象予報士が働いているのは、気象庁だけではありません。民間の気象会社では、地域をピンポイントに絞って細かな天気予報をしたり、気象庁の発表を分かりやすく解説したりと、お客さまのニーズに合わせた気象予報サービスを提供しています。
また、気象予報を商品の需要予測や交通運行管理に活用することで、コンサルティングを行う企業もあります。
民間企業の中でも、気象会社やマスコミ関係の企業などさまざまな就職先があるほか、国や地方自治体に就職することも可能です。さらに、フリーの気象予報士として独立して活動するという道もあります。
このように、気象予報士はさまざまな現場で、市民やお客さまの役に立つ気象予報を行っているのです。
-
気象予報士の資格とは?
気象予報士の仕事をご紹介しましたが、上記の業務はすべて「気象予報士資格」を持っていなければ行うことができません。
「気象予報士資格」は国家資格であり、この資格がなければ気象予報や、それによって起こる現象の予測をしてはいけないと定められているからです。
気象予報士の資格を取得するには、国家試験である「気象予報士試験」に合格する必要があります。このあと、気象予報士資格の取り方や試験について、詳しく解説します。
気象予報士資格の取り方

気象予報士の資格を取るには、「気象予報士試験」に合格したのち、気象庁長官の登録を受ける必要があります。
ここでは、気象予報士試験の受験資格や試験内容、合格基準など、気象予報士資格を取るための試験について詳しく解説します。
出典:気象予報士試験 試験概要一般財団法人 気象業務支援センターホームページ
-
受験資格
気象予報士試験に受験資格はありません。年齢や学歴、国籍、実務経験などに関係なく、誰でも受験できます。
過去には小学6年生の11歳の方が合格したこともあり、いつでもチャレンジできる資格です。
-
試験スケジュール気象予報士試験は、年2回あるのが大きな特徴です。例年、第1回は8月下旬、第2回は1月下旬に開催されています。受験資料配布から合格発表までのスケジュールを以下にまとめました。受験資料は、期間内にダウンロード、郵送もしくは気象業務支援センターに来所することで入手できます。なお、郵送はほかの2つの方法より期限が短く設定されているので、ご注意ください。
スケジュール 第1回 第2回 受験資料配布 5月中旬 10月中旬 申請期間 6月上旬から7月上旬 11月上旬から下旬 受験票到着期間 8月上旬 12月下旬から1月上旬 試験日 8月下旬 1月下旬 合格発表 10月上旬 3月上旬
受験資料には、試験案内や受験申請書などが含まれます。申請期間ぎりぎりに申請しようとしたら、手元に申請書がなかった——とならないよう、早めにダウンロードしておきましょう。 また、受験申請と同時に試験手数料を振り込むことを忘れないでください。
気象予報士試験に無事合格できても、すぐに気象予報士として活動を始められるわけではありません。次に、気象予報士登録の手続きをする必要があります。
登録の申請は、気象予報士合格後随時とされており、いつでもかまいません。
オンライン申請と書面による申請のどちらかを選べますが、申請には気象予報士試験合格証明書(合格通知のハガキに封入されています)が必要なので、言わずもがなですが合格証明書はなくさないようにしましょう。
登録を申請すると、約2週間の審査を経て「気象予報士登録通知書」が届きます。この登録通知書が届けば、晴れて気象予報士として活動できるようになります。
-
試験内容
試験は、学科試験と実技試験で構成されています。学科試験はマークシートによる多肢選択式、実技試験は記述式となっており、いずれも筆記試験です。
それぞれの科目をご紹介します。
- 学科試験の科目
- 予報業務に関する一般知識
- 大気の構造
- 大気の熱力学
- 降水過程
- 大気における放射
- 大気の力学
- 気象現象
- 気候の変動
- 気象業務法その他の気象業務に関する法規
- 予報業務に関する専門知識
- 観測成果の利用
- 数値予報
- 短期予報・中期予報
- 長期予報
- 局地予報
- 短時間予報
- 気象災害
- 予想の精度の評価
- 気象の予想の応用
- 予報業務に関する一般知識
- 実技試験の科目
- 気象概況及びその変動の把握
- 局地的な気象の予想
- 台風等緊急時における対応
-
合格基準
公表されている合格基準は、以下のとおりです。
- 学科試験(予報業務に関する一般知識):15問中正解が11以上
- 学科試験(予報業務に関する専門知識):15問中正解が11以上
- 実技試験:総得点が満点の70%以上
ただし、難易度によって調整されることがあるので、注意してください。
-
合格率・合格者数
合格率は、例年4~6%で推移しています。合格者数は、例年受験者数が4,000人前後に対して200名超です。
例えば、令和6年の第1回は、受験者数4,268人に対して合格者数248人、合格率は5.8%でした。第2回は、受験者数4,034人に対して合格者数244人、合格率は6.0%です。
出典:気象予報⼠試験 実施状況一般財団法人 気象業務支援センターホームページ
-
科目免除
気象予報士試験には、科目免除の制度があります。
学科試験の全部または一部に合格した場合、申請すれば、合格発表日から1年以内に行われる試験において、合格した科目の試験が免除されます。
もし学科試験に合格して実技試験に不合格だった場合、1年以内に再度受験するのであれば、すでに合格した科目については試験を受ける必要がなくなるということです。
合格していないほかの科目や、実技試験に勉強を集中させられるので、気象予報士試験を連続して複数回受けることも視野に入れて、学習を進めてもよいでしょう。
また、気象業務に関する業務経歴または資格を有する場合、こちらも申請することで学科試験の全部または一部が免除となります。
例えば、防衛省・気象庁の養成課程を修了し、3年以上予報業務に従事している方などです。すでに数年間(3年または7年)気象業務に従事している方が対象になります。
-
試験手数料
試験手数料は、以下のとおりです。
- 免除科目なし:11,400円
- 学科1科目が免除:10,400円
- 学科2科目が免除:9,400円
気象予報士はなぜ難関資格なのか?
「気象予報士は難関資格と聞いたことがある」という方も多いのではないでしょうか。
これは、気象予報士試験の難しさが影響しています。ここでは、なぜ気象予報士が難関資格といわれているのかを解説します。
-
合格率が4~6%前後と低い
先に解説したとおり、気象予報士試験の合格率は例年4~6%前後です。100人中4~6人しか合格しないという計算になり、合格率が非常に低いことが分かります。
特に難易度が高いといわれているのが、実技試験です。実技試験では、学科試験と異なり記述や作図、計算などが必要で、その上で総得点が満点の70%以上であることが求められます。
難易度の高い試験が合格率の低さにつながっており、「気象予報士は難関資格」といわれているのです。
-
勉強時間が800~1,000時間必要
気象予報士試験の勉強時間は、一般的に800~1,000時間必要とされています。
仮に1日2時間勉強するとしても、800時間なら400日、1,000時間なら500日かかり、1年から1年半はかかることになります。
気象予報士試験では、当然ながら専門知識が求められます。気象予報士に必要な気象についての基礎知識もあまり身に付いていない状態であれば、基礎を養うためにさらに勉強時間が必要でしょう。
このような長期間・多くの時間を気象予報士試験のための勉強に費やさなくてはいけないことは、「気象予報士は難関資格」といわれる一因となっているようです。
気象予報士試験はどうやって勉強すべき?

気象予報士試験の内容や、「気象予報士は難関資格」といわれる理由を解説してきました。
それでは、イチから気象予報士を目指す場合、どうやって勉強すべきなのでしょうか?
ここでは、気象予報士試験の勉強方法をご紹介します。
-
独学
まずは、学校などに通わず独学で勉強する方法です。
費用があまりかからないこと、自分のペースで勉強できることが何よりのメリットですが、だからこそ効率的に勉強を進めたり、自己管理をしっかりと行ったりすることが大切になります。
スマートフォンで気軽に勉強できる、気象予報士試験に対応したアプリや、市販の気象予報士試験参考書・問題集なども数多くあります。独学の場合、これらを上手に活用して学習を進めていくことになるでしょう。
また、気象予報に関する仕事に就職し、気象予報士試験で科目免除を受けられるよう実務経験を積みながら、実技試験に向けて勉強していくという手もあります。
-
通信講座・予備校
気象予報士試験に向けた通信講座・予備校も数多く開講されています。特に、通信講座は自宅にいながら教員から指導を受けられるので、効率的に勉強を進めやすいです。
一方で、ある程度費用がかかってしまうのは、独学と比較するとデメリットといえるかもしれません。
また、予備校に通う場合は、特に社会人の場合時間を確保するのが難しいことがあります。そして、通信講座は自宅で受けるものなので、どうしても集中できないという方もいるかもしれません。
-
4年制大学や短期大学、専門学校への進学
現在高校生で、将来気象予報士になりたいと志している学生さんには、4年制大学や短期大学、専門学校への進学がおすすめです。
大学や専門学校には、気象予報士資格の取得を見据えて、気象や地学に関する授業を数多く開講しているところも数多くあります。特に、「環境学部」「理学部」といった名称の学部を設置している場合、気象予報士に対応したカリキュラムを整備している可能性が高くなります。
中でも、4年制大学は気象予報士に必要な知識だけでなく、気象に関連した幅広い知識を体系的に学んだり、興味を持ったテーマを自ら研究したりできるのが魅力です。
このあと紹介する、立正大学 地球環境科学部 環境システム学科も、気象予報士になるために必要な知識を幅広く身に付けられる学科です。
立正大学 地球環境科学部について
立正大学 地球環境科学部は、気象予報士を目指せる大学の一つです。特に、地球環境科学部 環境システム学科は気象予報士志望の方におすすめの学科です。
ここでは、地球環境科学部 環境システム学科をご紹介するとともに、学部・学科問わず開講されている特別講座「気象予報士講座」を紹介します。
-
立正大学 地球環境科学部 環境システム学科
そもそも、「環境システム学」とは何なのでしょうか?
環境システム学とは、環境保全を視野に入れた総合的な学問です。私たちを取り巻くさまざまな自然環境を、相互に作用し合う「システム」として捉えると同時に、生物による複雑な影響を考えに入れて体系的に理解します。
環境システム学科の特徴は、自然現象を理解するために、気圏・地圏・水圏・生物圏のメカニズムを広く学習しながら、実験やフィールドワークを通して実戦的な測定法・解析法・分析法を習得できること。
環境科学に不可欠な情報処理の基礎技術に加え、リモートセンシング(遠隔測定技術)や地理情報システム(GIS)といった高度な技術も学べるのが魅力です。
環境システム学科には、「生物・地球コース」と「気象・水文コース」の2つの履修コースがあり、学生それぞれの興味や進路に合わせて選べます。
気象予報士を志望する方におすすめなのは、「気象・水文コース」です。
主に気圏・水圏(気候変動や水循環など)に関する知識を習得することを目的にしており、気象予報士や環境計量士になるのに役立つ授業を受けられます。
一方の「生物・地球コース」は、主に生物圏・地圏(動植物の生態系や地形・岩石など)に関する知識を習得することを目的にしています。こちらでは、生物分類技能検定や自然再生士の資格取得に役立つ授業を受けられるのが魅力の一つです。
- 環境システム学科の特徴
- 地球環境の正確な理解
自然環境の諸要素とそれらの相互関係の理解、 幅広い視野と技術を備えた「環境コーディネーター」をめざし、豊富な実験やフィールドワークをとおして学修します。 - 基礎を固めて発展させる
1年次は基礎科目、2年次は専門科目、3年次はセミナー、4年次は卒業研究と、段階的に専門性を高めるカリキュラムです。4 年間で知識や技術を着実に発展させます。 - 現代自然科学の基本技術ICT
いまや環境問題の対策にも利用されているICT(情報通信技術)。先端技術を活用し、リモートセンシング(遠隔調査)や、地理情報システム(GIS)を学修します。
- 地球環境の正確な理解
- 環境システム学科 学びの領域
- 環境情報学
全ての領域にまたがるのが「環境情報学」です。自然的・社会的要素が複雑に絡み合う環境問題の解決に向けては、広い視野が必要です。SDGs に関連の深い問題は、情報のインフラや情報サービスの普及、環境・情報教育や産業技術の開発をはじめ、天然資源の管理と利用、食品ロス、廃棄物の削減と利用等といった事柄です。その他、環境情報の整理・解析技術を応用して、幅広い問題の解決に貢献します。 - 環境生物学
「環境生物学」は、動植物や海洋・陸上の自然環境を研究対象とし、ヒトが他の生物や生態系に与える影響を明らかにしながらヒトと生物が共存していく方法を考えます。適切な水産資源の確保や海洋と沿岸の生物の保全、陸域や淡水・山地生態系、持続可能な森林開発や砂漠化対策、絶滅危惧種や在来種と外来種の問題等、SDGsにも直結する研究から、問題解決をめざしていきます。 - 環境地学
地球の地形・地質的特徴は、火山噴火や地震等の現象、超長時間の過程等、さまざまな要因で形成されています。「環境 地学」では、固体地球の特徴が作られた歴史を科学的に紐解いていきます。水害や土砂災害の発生メカニズムや対策といった気候変動にも関わる問題、地熱発電や化石燃料、放射性廃棄物といったエネルギー問題、海洋のゴミ問題や沿岸地形の保全等、SDGsの目標達成にも貢献します。 - 環境気象学
異常気象、都市や地球の温暖化、大気汚染といった大気に関わる問題は、人びとの生活にも直接的に大きな影響を与えています。「環境気象学の学びでは、野外での気象観測や実験等に積極的に取り組みながら研究を進めます。SDGs の目標にも関連する、気候変動による地球環境の変化や人体への影響、気候災害とそれに伴う水害への対策や、ヒートアイランド現象と都市、大気汚染や気象災害といった問題にも取り組みます。 - 環境水文学
「環境水文学」では、世界中のあらゆる“水”を扱います。水の循環や水質、さまざまな特徴をもつ水を観測・分析し、科学的に理解していきます。SDGsとの関連では、安全な水と衛生の確保の観点から、地下水や地表水の利用や水質汚染の問題、持続可能な水利用、淡水域における動植物の絶滅危惧種や外来種等の問題、乾燥地の問題等、自然環境から人の暮らしまで、水に関する多様な問題で貢献する分野です。
- 環境情報学
-
「気象予報士講座・問題検討会」
仲間と共に試験問題に取り組み 基礎力・実践力を養い 超難関国家資格取得に挑みます。環境システム学科では気象予報士の資格取得につながる講義を受講できますが、立正大学 地球環境科学部では、気象予報士を目指す方向けに「気象予報士講座」を開講しています。
地球環境科学部が民間気象会社と共催する「気象予報士講座」では、講師である現役の気象予報士から、資格合格のコツを学べます。正規の学部開設科目ではありませんが、例年多くの学生が受講する人気講座です。また「気象予報士問題検討会」は、気象学専門の先生方にサポートを受けながら、学生有志が主体的に学ぶ会です。学生が順に過去の試験問題の解答法を発表し、それについて、その場の全員が先生と学生の垣根を越えて、熱く討論します。2022年度は、なんと参加者の一人が合格! よりよい解き方を試行錯誤する発展的な学びの場は、同じ志を持つ仲間の活気に溢れ、着実な学びに繋がっています。
気象予報士講座は、基礎を固める「基礎講座」と、学科試験・実技試験対策トレーニングを行う「問題演習講座」の2つがあり、W受講で短期合格を目指せるプログラムです。
大学学内講座だからこその特別価格も大きな魅力で、通常15万円以上かかる講座を、- 基礎講座:49,000円
- 問題演習講座:40,000円
- 基礎講座+問題演習講座ダブル受講:59,000円
こちらの価格で受講できます。
W受講で大きな割引を受けられるので、気象予報士講座を受講したい方はW受講がおすすめです。
まとめ
気象予報士は、試験の合格率が例年4〜6%前後、必要な勉強時間は800〜1,000時間とされているなど、難関国家資格として位置づけられています。
しかし、気象予報士は気象観測データから気象を予測し、時には人々に災害の予兆を知らせるなど、なくてはならない存在です。
立正大学 地球環境科学部 環境システム学科では、気象予報士試験で求められる知識を数多く身に付けられます。また、学部・学科を問わず受講できる特別講座「気象予報士講座」も開講しています。
カリキュラムや講義、特別講座を通して、気象予報士を目指す学生さんをサポートしているので、気になった方はぜひ立正大学 地球環境科学部についてホームページをご覧ください。

「環境・気象関係を学ぶなら」
立正大学 地球環境科学部 環境システム学科へ
5つの分野から環境科学を多角的に学ぶ 【環境生物学/環境地学/環境気象学/環境水文学/環境情報学】 環境システム学科では、地球環境に関わる諸問題について科学的視点で問題の本質を捉えることができ、「持続可能な社会」の形成に貢献できる人材の育成をめざしています。
地球環境科学部 環境システム学科Webサイトへ