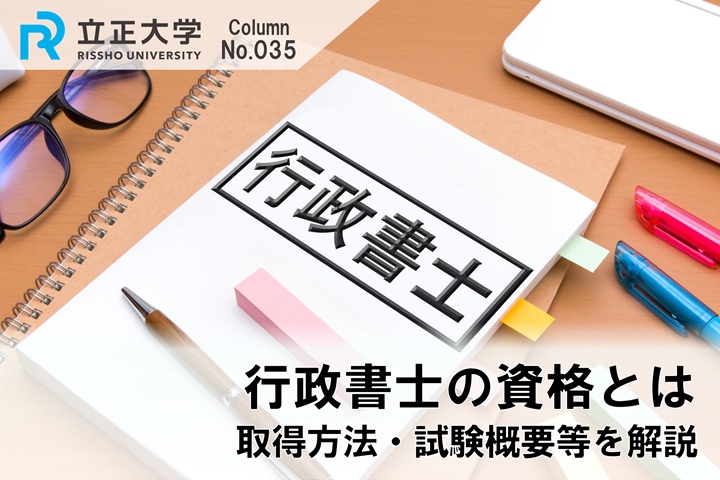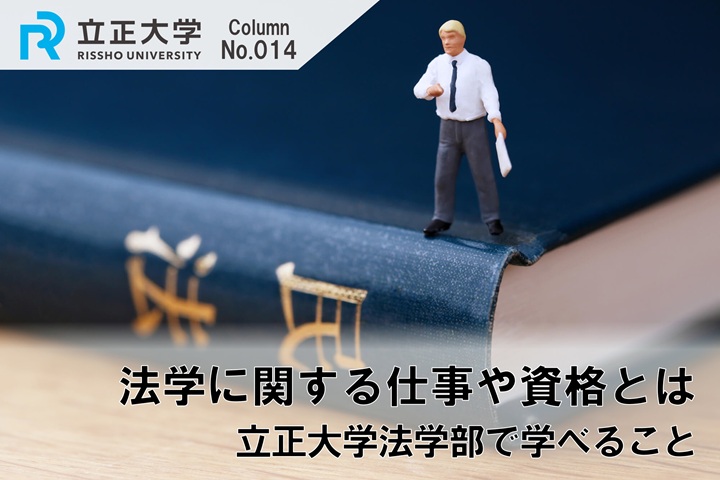法学部の就職先は 就職業界や職種・資格等を解説
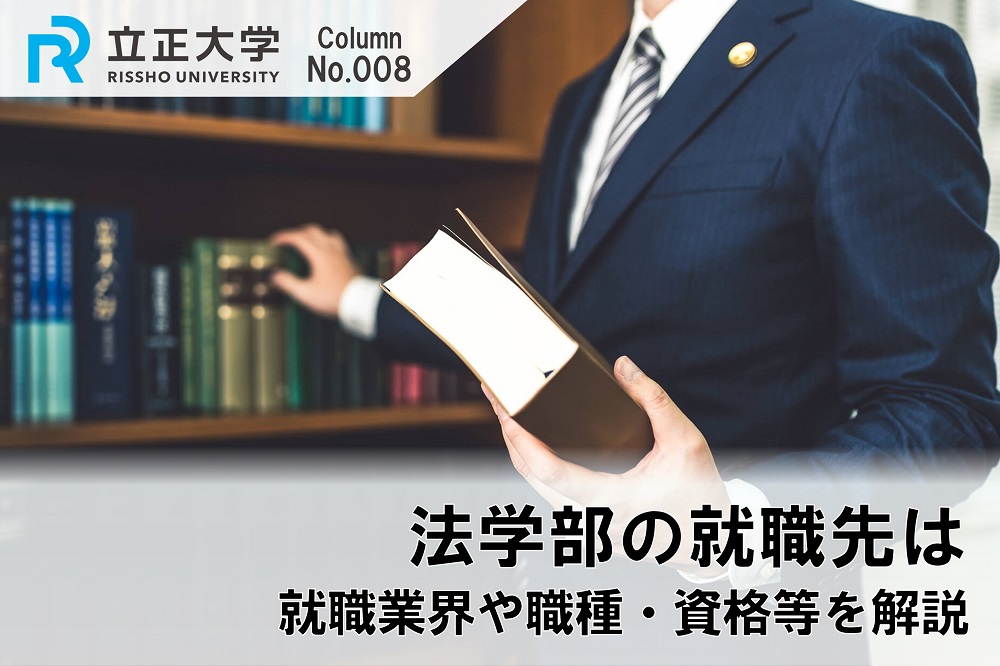
主に法律について学ぶ法学部。
就職先は弁護士や裁判官というイメージが強いですが、実は法学部の就職先は非常にさまざまです。
今回は、法学部の就職先を業界と職種ごとに分けてご紹介します。
また、就活に有利になる資格も紹介しますので、法学部に在籍している方、法学部への進学を考えている方は、ぜひ参考にしてください。
法学部の就職先【業界編】
まずは、法学部の就職先を9つの業界から見ていきましょう。
-
法曹
法学部の憧れの就職先といえば裁判官・検察官・弁護士の法曹三者。法律に関するスペシャリストの中でトップに位置する職業です。
裁判官は、裁判において憲法や法律に基づいた公正な判決を下します。
検察官は、犯罪や事件についての捜査や被疑者の起訴、起訴した事件についての公判での立証などが主な仕事内容です。
弁護士は、裁判において被疑者や被告人の権利を守ったり、依頼者の求めに応じて紛争を解決したりと、幅広く活躍します。
法曹になるには、裁判官・検察官・弁護士のどれを目指すとしても、国家試験である司法試験に合格しなければなりません。
司法試験の受験資格を得るには、以下のいずれかが必要です。
- 法科大学院の修了⋯大学卒業後、法科大学院で2年または3年学びます(法学部を卒業したか方は2年、法学部以外の学部を卒業した方は3年です)。
- 司法試験予備試験の合格⋯ 7月に行われる短答式試験と、9月に行われる論文式試験、1月に行われる口述試験を、順にすべて合格する必要があります。受験資格が特にないのが特徴です。
- 法曹コースの修了⋯2020年度から開始された、特定の法学部と法科大学院で計5年間学ぶ方法です。大学在学年数を従来より1年間短縮できます。
法科大学院や法曹コースの修了では長い年月を必要とする上、司法試験予備試験は合格率が例年3~4%と難易度が非常に高いです。
さらに、司法試験自体の合格率もここ数年は約4割で、司法試験合格へはイバラの道といえます。
ですが、法のスペシャリストのトップとして活躍できる法曹三者。司法試験合格を目指して勉強した内容は、この後紹介するほかの法律の専門家を目指す上でも役に立つため、法曹三者を志すことに損はありません。
-
士業
士業とは、法律に基づいた○○士と付く資格を持つことでなれる、各分野の専門家の総称です。
特に、法律との関連性が強い士業は8士業と呼ばれます。
業務で必要な場合に住民票や戸籍などの書類を請求することが認められている職業で、以下がその一覧です。
- 弁護士…法律全般に関する業務
- 司法書士…登記申請に関する業務
- 行政書士…行政への申請に関する業務
- 弁理士…知的財産に関する業務
- 税理士…税に関する業務
- 社会保険労務士…労働や社会保険に関する業務
- 土地家屋調査士…不動産の登記に関する業務
- 海事代理士…海に関する法律を取り扱う
以上の士業は、どれも法律に関する業務を行う専門家とされていて、なるにはそれぞれ国家試験を受けて合格するのが一般的なルートとなっています。
弁護士のような法曹三者は敷居が高いと感じている方でも、ほかの士業でも法律の専門家として法学部で得た知識や技術を最大限生かして働くことができるので、気になる士業がある方はぜひ目指してみましょう。
-
公務員
国家公務員や地方公務員など、国や地方自治体の運営を担う公務員は法学部生に人気の就職先です。
また、公務員試験には憲法やほかの法律に関する出題も多く、法学部での学びがそのまま合格につながりやすい側面もあります。
警察官や国税専門官など法律との関係が深い職種や、裁判所事務官や家庭裁判所調査官など裁判所で働ける職種もあり、法学部生としてのやりがいを感じやすいでしょう。
公務員については以下のコラムで詳しく解説しておりますので、興味のある方はぜひ読んでみてください。

公務員になるには 公務員試験対策・キャリアについて解説
記事はこちら
-
商社
商社は、商品やサービスの流通の担い手で、国内外の企業と企業の仲介を務めます。
商社には、幅広い商品やサービスを取り扱う「総合商社」と専門の分野に絞って取り扱う「専門業者」がありますが、特に総合商社は年収が高い傾向が強く、人気の業界です。
国内外で取引を行う商社では、日本だけでなく海外の法律についての知識も求められることから、法律に強い法学部生が活躍しやすいです。
商社を志すなら、国をまたいで活躍することを見越して語学力も鍛えておくとよいでしょう。
-
金融業界
金融業界とは、例えば銀行や証券会社、クレジットカード会社、保険会社などです。
主にお金を取り扱う業界で、特に融資や金利などの契約書を作成する場面も多くあり、法律の知識が非常に求められます。
顧客と直接話し、金融商品を勧めたり相談に乗ったりすることも多く、コミュニケーション能力も必要です。
商社と同じく年収が高い傾向があるため、法学部生に人気の業界です。
-
製造業界
いわゆる「メーカー」で、食品メーカーや化粧品メーカー、医薬品メーカー、自動車メーカーなど、製品によって多様なメーカーがあります。
それぞれで、新商品を開発したり販売したりする際に、法律を順守した上での業務が求められるため、法律の知識が役立つでしょう。
メーカーは製作している商品によって、自分の好きなモノを作っている企業に入社できる可能性もありますし、比較的ホワイトな会社が多いとされている業界でもあります。
-
情報・通信業界
情報・通信業界は、情報サービスやWeb系のサービスを取り扱う企業や、テレビや電話、インターネットなどの通信を取り扱う企業を指します。
インターネットが加速度的に成長している現在、成長の一途をたどっている企業は多く、今後も需要が衰えないという観点からも、人気の業界です。
業界の進化に合わせて、今後法律も変化していくことが予想されており、法律の変化に迅速に対応できる能力がある点で法学部生は大きく活躍できるでしょう。
-
サービス業界
サービス業界とは、例えば飲食や宿泊、医療、介護、美容院など、モノよりもサービスを提供する業種を指します。
サービス業界ではそれぞれ順守しなければならない法律があり、お客様と直接コミュニケーションをとる機会も多いので、法律の知識を持つ法学部生は活躍しやすいでしょう。
法学部の就職先【職種編】

次に、法学部の就職先を5つの職種から見ていきましょう。
-
法務
法務は、会社の法律に関する業務を行う部門です。
会社の法的手続きを行ったり、取引先との契約書を確認したりと、会社経営における重要な業務を担います。
新卒で法務に配属されることは少なく、多くの場合入社後に経験を積んでから法務へと異動する形になるでしょう。その際、法学部出身だったり法律に関する資格を持っていたりすることで、法務への配属の可能性が高まります。
-
人事労務
人事労務は、企業の労働者に関する業務を行う部門で、時間外労働や福利厚生などに関する業務が代表的です。
労働基準法や労働安全衛生法などの法律の知識が必須で、法律を順守しなければ労働災害や労働者からの訴訟のリスクも生まれます。そのため、法律に詳しい法学部生は重宝されるでしょう。
また、社会保険労務士と業務が似ているところもあり、社会保険労務士の資格を取得しておくと業務に非常に役立ちます。
-
総務
総務は、組織の運営を円滑にするための幅広い業務を行う部門です。
例えば、電話・来客対応や備品管理、社内行事の企画・運営などがあります。
日々さまざまな部門と連携するため、幅広い法律の知識が役立ちやすく、法学部生が活躍しやすいです。コミュニケーション能力も鍛えられるでしょう。
-
経理
経理は、企業のお金を取り扱う部門です。
売上の管理や給与計算など、会社経営に欠かせない業務を行います。
社会保険や税金など、法律が深く絡んでくる領域も担当するため、法学部生が求められやすいです。
また、税金に関する業務を行うことで、経理から税理士に転職する方も少なくありません。
-
営業
営業は、自社の商品やサービスの魅力を顧客に伝えることで、購入や契約につなげる業務を行う部門です。
営業によって企業の売上が発生するため、なくてはならない部門であると同時に、新卒が最初に配属されることの多い部門でもあります。
営業では消費者契約法や独占禁止法などの法律を守る必要があるため、法学部生は法律にのっとった営業ができる従業員として重宝されるでしょう。
【番外編】法学部の就活を有利にする資格

最後に番外編として、法学部の就活に有利になる資格を8つ紹介します。
-
弁護士(司法試験)
裁判官・検察官・弁護士の法曹三者になるために合格が必須の司法試験ですが、合格すればすぐに法曹三者になれるわけではありません。
司法試験合格後、1年間の司法修習を修了し、司法修習生考試に合格することで、晴れて法曹三者として活躍することが認められます。
そして、司法修習は裁判官・検察官・弁護士それぞれで分かれており、このうち弁護士の道に進んだ方が最終的にゲットできるのが弁護士資格です。
弁護士資格があると、弁護士として働けるようになるのはもちろん、以下の士業に就くこともできます。
- 弁理士
- 税理士
- 社会保険労務士
- 行政書士
- 海事補佐人
この後も紹介するいくつかの資格を兼ねているため、仕事の幅が広がる点でも弁護士資格の取得はおすすめです。
-
司法書士
司法書士は国家資格で、登記業務の代理が代表的な仕事です。
登記とは、不動産や債権などの特定の財産の権利を、公的に記録することです。
これには、必要な書類を法務局に提出する必要があるのですが、手続きが複雑なので本人が適切に行うのが難しい場合があります。
そこで代わりに登記を行うのが司法書士で、登記業務の代理は司法書士にのみ許可されている業務です。
司法書士資格を得るには、司法書士試験に合格するか、法務大臣の認定を受ける必要があります。
司法書士試験は受験資格が特になく、誰でも受けられるのに対し、法務大臣の認定を受けるには特定の仕事に5年または10年従事する必要があるため、司法書士試験の受験が一般的なルートとなっています。
司法書士試験の合格率は、例年4~5%と難易度は高めです。
-
行政書士
行政書士は国家資格で、行政に提出する書類作成の代理が主な仕事です。
例えば、遺言書や遺産分割協議書の作成といった相続関係の手続きや、会社を開業する際に必要な許認可申請業務などを行います。
官公署に提出する書類の作成・権利義務に関する書類の作成・事実証明に関する書類の作成の3つは、行政書士の独占業務です。
行政書士になる道筋は3つあります。
1つ目は行政書士試験の合格、2つ目は公務員の特認制度といって、国家公務員または地方公務員の職に17年以上または20年以上就くこと、3つ目は弁護士・税理士・弁理士・公認会計士のいずれかの資格の有資格者であることです。
行政書士試験の受験資格は特になく、合格率は例年10~13%で推移しています。
行政書士については以下のコラムで詳しく解説しておりますので、興味のある方はぜひ読んでみてください。
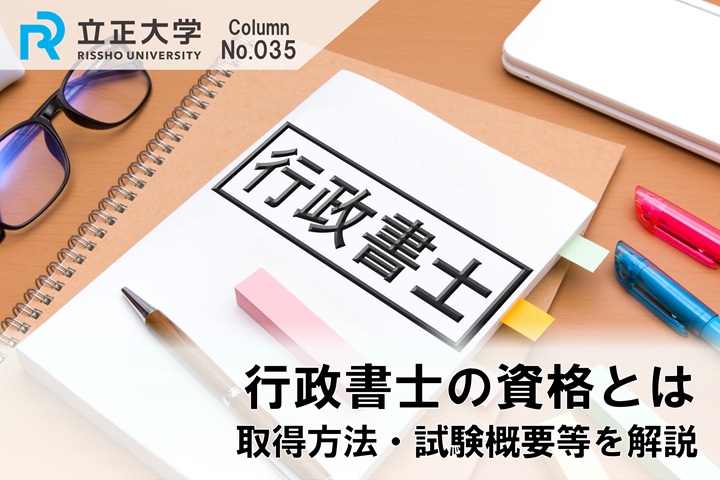
行政書士の資格とは 取得方法・試験概要等を解説
記事はこちら
-
税理士
税理士は国家資格で、税務や会計に関する仕事を代行したり、相談に乗ったりします。
具体的には、依頼者の確定申告の代行や、企業の会計業務の遂行などです。
税務代理・税務書類の作成・税務相談は、税理士にのみ許可されている独占業務です。
税理士になるには、税理士試験への合格後、2年以上の実務試験を積み、日本税理士会連合会の税理士名簿に登録する必要があります。
ただし、税理士試験を受験するには受験資格を満たす必要があり、大学や短期大学での社会科学に属する科目の履修だったり、特定の資格だったり、税務・会計に関する業務への職務経験だったりと、一定の要件を満たさなければなりません。
税理士試験の合格率は、ここ数年は15~20%前後で推移しています。
税理士については以下のコラムで詳しく解説しておりますので、興味のある方はぜひ読んでみてください。
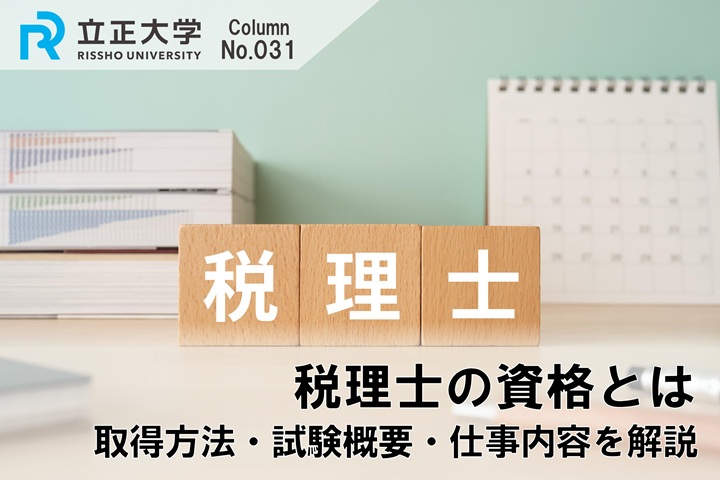
税理士の資格とは 取得方法・試験概要等を解説
記事はこちら
-
社会保険労務士
社会保険労務士は国家資格で、企業の労働や社会保険に関する業務や、年金相談などを担います。
社会保険労務士の独占業務には、1号業務と呼ばれる労働に関する手続き代行と、2号業務と呼ばれる労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成があります。
社会保険労務士になるには、社会保険労務士試験への合格と、2年間の実務経験または事務指定講習の受講、その後に全国社会保険労務士会連合会名簿への登録と、都道府県社会保険労務士会への入会が必要です。
大学や短期大学を卒業していれば受験資格を得られるので、法学部を卒業後すぐに試験を受けられるようになります。
社会保険労務士の合格率は、ここ数年5~7%で推移しています。
社会保険労務士については以下のコラムで詳しく解説しておりますので、興味のある方はぜひ読んでみてください。
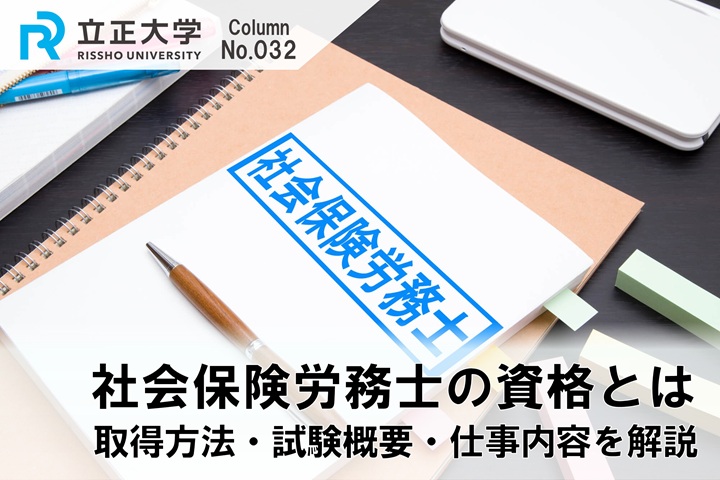
社会保険労務士の資格とは 取得方法・試験概要等を解説
記事はこちら
-
宅地建物取引士
宅地建物取引士は国家資格で、不動産取引が公正に行われるようサポートするのが主な仕事内容です。
不動産業界を目指す方におすすめの資格といえます。
不動産に関する重要事項の説明と、重要事項説明書の記名(35条書面)、契約書の記名(37条書面)は、宅地建物取引士の独占業務です。
宅地建物取引士になるには、宅地建物取引士試験の合格と、2年以上の実務経験または登録実務講習の受講、その後に試験を受けた都道府県知事に資格登録申請および宅建士証交付申請を行い、宅建士証の交付を受ける、と長めのプロセスが必要になります。
宅地建物取引士試験に受験資格は特になく、合格率は例年15~17%前後で推移しています。
-
ビジネス実務法務検定
ビジネス実務法務検定とは、東京商工会議所が認定する民間資格です。
あらゆる業種において、ビジネスパーソンとして必要な法律知識を有していることを証明できる資格とされています。
検定試験は3級・2級・1級の順で難易度が上がっていき、特に1級は企業の法務部門に所属する方向けのクラスですが、合格率は10~20%と難関です。
-
個人情報保護士
個人情報保護士とは、全日本情報学習振興協会が認定する民間資格です。
個人情報保護法への深い理解と、個人情報を適切に取り扱えるスキルを証明できる資格とされています。
合格率は例年35~40%を推移しており、比較的挑戦しやすい資格です。
まとめ
法学部の就職先を、業界別・職種別に解説しました。法学部生は法曹だけでなく、公務員や一般企業でも多くの活躍の場があります。
就職に役立つ資格も紹介したので、法学部への進学を考えている方や現在法学部で学んでいる方は、ぜひ参考にしてくださいね。
立正大学法学部は、キャリア形成支援の充実が特徴の一つ。
1年次にはすべての学生が法律の基礎を学び、2年次からは学生それぞれが興味や進路に合わせて、以下の3つのコースいずれかに進みます。
「社会公共コース」は公務員や士業を目指す学生向け、「ビジネス法コース」は民間企業で活躍したい学生向けのコースです。
「特修コース」は双方向型・少人数講義が特徴で、特定の進路を意識するというより、ディスカッションなどを通して多様な価値観やバランス感覚を培いたい学生向けのコースです。
また、キャリア形成支援として、各種課外講座や資格取得奨励金制度など、公務員試験や資格試験への合格を目指す学生向けの支援が盛りだくさん。
立正大学法学部が気になった方は、ぜひこちらのホームページもご覧ください。

「法学を学ぶなら」 立正大学 法学部へ
立正大学法学部の特長は、徹底した少人数教育、大学内にとどまらないフィールドワーク、経験豊かな実務家による教育とともに、現代社会の諸問題に即応した科目の充実にあります。また、法学部独自に多彩な課外講座が展開されてもいます。立正大学法学部は、正課および課外での教育により、学生の希望進路の実現を後押しするだけでなく、リーガルマインド(法的思考力)を身につけた一人の社会人として社会や地域に貢献できる人材の育成に尽力しています。
法学部Webサイトへ 卒業生の主な進路・就職先