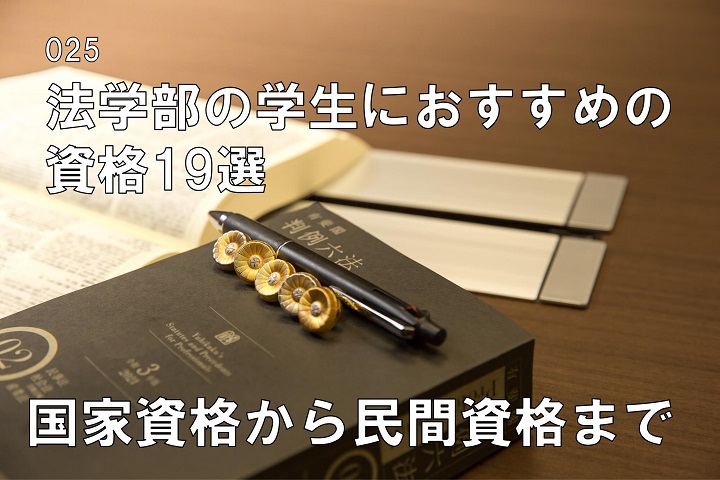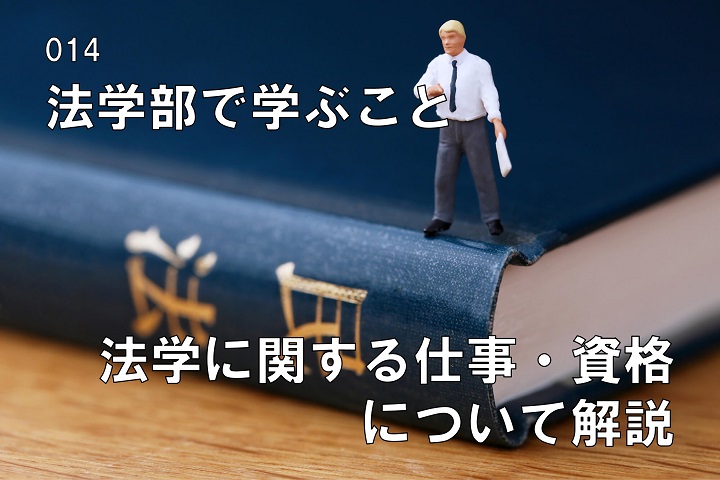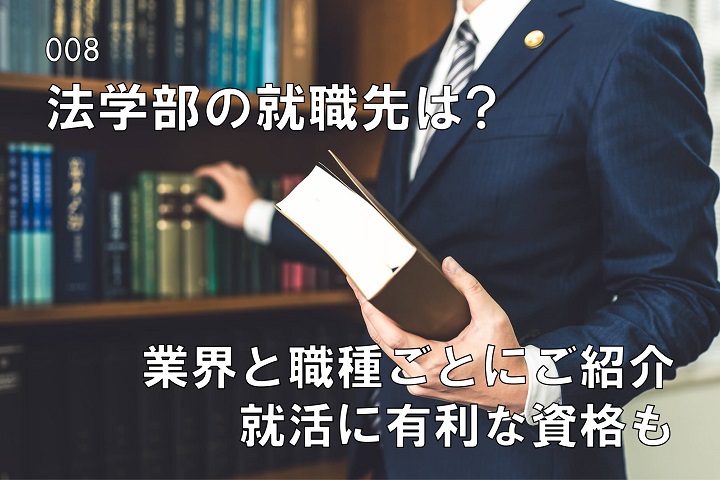社会保険労務士の資格とは 取得方法・試験概要・仕事内容を解説
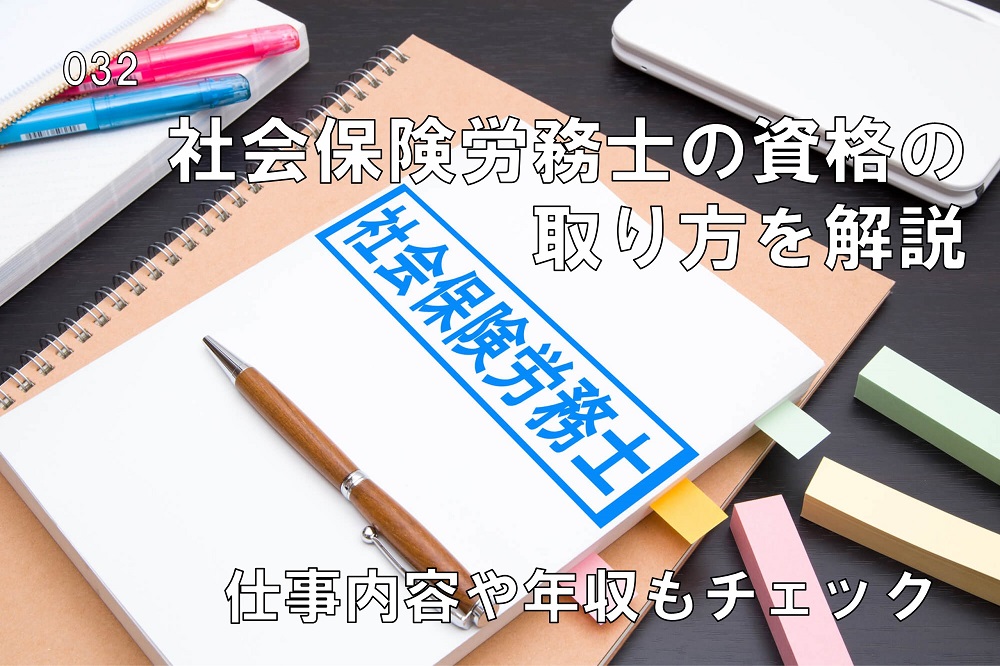
社会保険労務士は、略して社労士とも呼ばれている国家資格です。
企業の「労務」に関する専門家であり、労働や社会保険に関する手続きの代理や相談対応など、幅広い業務を担います。
今回は、社会保険労務士の資格を得る方法を中心に、社会保険労務士の仕事内容や年収などを詳しく解説します。
社会保険労務士が気になる、社会保険労務士になりたいという方は、ぜひ最後までご覧ください。
出典:社労士を目指す全国社会保険労務士会連合会
出典:全国社会保険労務士会連合会試験センター社会保険労務士試験オフィシャルサイト
社会保険労務士の資格を取るには
社会保険労務士の資格を取るには、毎年8月に実施される社会保険労務士試験に合格することが必須となります。
社会保険労務士試験には受験資格が設定されており、誰でも受験できるわけではありません。
また、試験合格後はすぐに社会保険労務士として登録できるわけではなく、全国社会保険労務士会連合会が定める登録要件を満たす必要があります。
ここからは、社会保険労務士試験の受験資格から試験概要、さらに社会保険労務士の登録要件まで、順を追って詳しく見ていきましょう。
社会保険労務士試験について

初めに、社会保険労務士を目指すなら必ず合格しなければならない社会保険労務士試験について、詳しく解説していきます。
-
受験資格
受験資格は、大きく「学歴」「実務経験」「厚生労働大臣の認めた国家試験合格」の3つに分けられ、いずれかを満たしていれば受験が可能になります。
- 学歴
学歴による受験資格は、主に以下のとおりです。- 大学、短期大学、専門職大学、専門職短期大学または高等専門学校(5年制)を卒業した方
- 大学(短期大学を除く)において、62単位以上の卒業要件単位を修得した方
- 一般教養科目と専門教育科目等との区分けをしている大学(短期大学を除く)において、一般教養科目36単位以上を修得しており、なおかつ専門教育科目等の単位を加えて合計48単位以上の卒業要件単位を修得した方
- 専門学校を卒業した方
- 上記以外で、厚生労働大臣が認めた学校等を卒業した方 など
大学への進学予定がある方なら、大学で所定の単位数を修得した時点で受験資格を得られます。
学歴による受験資格を満たすのが、もっとも一般的といえるでしょう。
- 実務経験
実務経験による受験資格は、主に以下のとおりです。- 労働社会保険法令の規定に基づいて設立された法人の役員(非常勤を除く)または従業員として、同法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上ある方
- 国または地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間、行政執行法人や特定地方独立行政法人、特定地方独立行政法人、日本郵政公社などの役員または職員として、行政事務に相当する事務に従事した期間が通算3年以上ある方
- 全国健康保険協会や日本年金機構の役員(非常勤の者を除く)または従業者として、社会保険諸法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上ある方
- 社会保険労務士や社会保険労務士法人、弁護士、弁護士法人などの業務の補助の事務に従事した期間が通算して3年以上ある方
- 労働組合の役員として、労働組合の業務に専従した期間が通算して3年以上になる方
- 法人や社団、財団などの役員として労務を担当した期間が通算して3年以上になる方
- 労働組合の職員や、法人や事業を営む個人の従業者として、労働社会保険諸法令に関する事務に従事した期間が通算して3年以上になる方
おおまかにまとめると、特定の組織にて3年以上労務に関する業務を行った実務経験があれば、実務経験による受験資格を満たせる可能性があります。
- 厚生労働大臣の認めた国家試験合格
厚生労働大臣の認めた国家試験合格による受験資格は、以下のとおりです。- 社労士試験以外の国家試験合格
- 司法試験予備試験等の合格
- 行政書士試験の合格
社労士試験以外の国家試験には非常に多くのものが含まれていますが、例を挙げると公務員試験や公認会計士試験、弁理士試験などです。
詳細は、以下を参照してください。
出典:厚生労働大臣が認めた国家試験全国社会保険労務士会連合会試験センター
- 学歴
-
スケジュール
受験資格を満たしていることが確認できたら、まずは受験の申し込みです。
受験申込期間は、毎年4月中旬に行われる、「社会保険労務士試験の実施について」の厚生労働大臣の官報公示から、5月31日までの間です。
申し込みは、原則としてインターネット申し込みが指定されていますが、当面の間は郵送申し込みも可能とされています。
インターネット申し込みの場合は、24時間申し込みできるのに加えて手続きも比較的簡単に行えます。
一方で郵送申し込みでは、申し込み前に返信用封筒を試験センターに郵送し、受験案内(申込書一式)を請求した上で、受験申込書を郵送にて送らなければなりません。
試験日は、毎年8月となっています。令和7年度試験は8/24(日)に実施されました。
合格発表日は10月上旬で、令和7年度試験では10/1(水)です。
厚生労働省ホームページおよび社会保険労務士試験オフィシャルサイトに合格者の受験番号が掲載され、合格発表日の10日ほど後に、合格者には合格証書が発送されます。
-
試験内容
社会保険労務士試験の試験科目と出題形式、配点は以下のとおりです。
選択式は合計8問(40点)、択一式は合計70問(70点)、満点は110点です。選択式は80分、択一式は210分の時間が用意されており、特に択一式は3時間以上と長丁場になるので覚えておきましょう。試験科目 選択式 計8科目(配点) 択一式 計7科目(配点) 労働基準法及び労働安全衛生法 1問(5点) 10問(10点) 労働者災害補償保険法
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。)1問(5点) 10問(10点) 雇用保険法
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。)1問(5点) 10問(10点) 労務管理その他の労働に関する一般常識 1問(5点) 10問(10点) 社会保険に関する一般常識 1問(5点) 健康保険法 1問(5点) 10問(10点) 厚生年金保険法 1問(5点) 10問(10点) 国民年金法 1問(5点) 10問(10点)
また、解答はマークシート形式で、すべての問題において正しい答えを選びます。
注意点として、合格基準点は明確に定められておらず、合格発表日に公表されます。
例として、令和6年度試験では、- 選択式試験は、総得点25点以上かつ各科目3点以上(ただし、労務管理その他の労働に関する一般常識は2点以上)である者
- 択一式試験は、総得点44点以上かつ各科目2点以上である者
上記1と2の両方を満たした方が合格となりました。
選択式と択一式のそれぞれで60%以上得点していれば、合格できる傾向が見られます。ただし、各科目に最低得点が定められている上に、合格基準点は毎年変わる可能性があるので、入念な準備が欠かせません。
-
合格率
過去5年間の受験者数と合格者数、合格率をまとめました。
例年、合格率は5~7%台で推移しています。10人に1人が合格するかどうかといった割合で、社会保険労務士試験の難易度は高いといえるでしょう。年 受験者数 合格者数 合格率 令和6年度(2024年) 43,174人 2,974人 6.9% 令和5年度(2023年) 42,741人 2,720人 6.4% 令和4年度(2022年) 40,633人 2,134人 5.3% 令和3年度(2021年) 37,306人 2,937人 7.9% 令和2年度(2020年) 34,845人 2,237人 6.4%
社会保険労務士試験の難易度の高さには、度重なる法改正に対応した問題が出題されることや、合格基準点が総得点だけでなく、各科目の得点にも設定されていることが影響していると考えられます。
-
費用
受験手数料は、15,000円です。
インターネット申し込みの場合はクレジットカード決済やコンビニ決済、銀行ATM、Pay-easy、郵送申し込みの場合は郵便局の窓口で支払います。
-
免除資格とは
社会保険労務士試験では、実務経験などに応じて、一部科目の受験が免除される制度が設けられています。
主な免除資格は以下のとおりです。- 国または地方公共団体の公務員として、労働社会保険法令に関する施行事務に従事した期間が通算して10年以上になる方
- 厚生労働大臣が指定する団体の役員もしくは従業者として、労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して15年以上になる方または、社会保険労務士もしくは社会保険労務士法人の補助者として、労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して15年以上で、全国社会保険労務士会連合会が行う免除指定講習を修了した方 など
ほかにも、免除資格は数多く設けられています。詳細は、以下からご確認ください。
出典:試験科目の一部免除資格者一覧全国社会保険労務士会連合会試験センター
社会保険労務士の登録要件

社会保険労務士試験に合格しても、ただちに社会保険労務士として活動できるようになるわけではありません。
社会保険労務士の資格を得るには、全国社会保険労務士会連合会に備わる社労士名簿に登録してもらった上で、都道府県の社会保険労務士会に入会する必要があります。
社労士名簿に登録されるには、社会保険労務士試験の合格と、2年以上の労働社会保険諸法令に関する実務経験(試験の前後は問われません)が必要です。
ですが、実務経験が2年未満の場合は、全国社会保険労務士会連合会が実施する「事務指定講習」を修了すれば、2年以上の実務経験に代えて登録要件を満たすことができます。
事務指定講習は、年に1回実施されており、4カ月間にわたる通信指導課程と、eラーニング講習で構成されています。
2年以上の実務経験や事務指定講習の修了によって、社会保険労務士として登録したら、いよいよ社会保険労務士として活動できるようになります。
社会保険労務士の仕事内容
社会保険労務士は、労務の専門家です。社会保険労務士の独占業務には、「手続代行業務(1号業務)」「帳簿作成業務(2号業務)」があります。
「手続代行業務(1号業務)」は、例えば雇用保険や社会保険に関する手続きや、雇用や人材の能力開発などに関する助成金の手続きです。
「帳簿作成業務(2号業務)」には、労働者名簿や賃金台帳の調整、就業規則・36協定の作成、変更などがあります。
これらの手続きや書類作成は複雑な一方、誤ってしまうと罰則の対象になることも。社会保険労務士は、企業を「労務」の面から支える大切な役割を担っています。
ほかにも、社会保険労務士は企業・労働者双方からの労務や年金に関する相談に応じるだけでなく、「特定社会保険労務士」の資格を取得することで、独占業務として紛争解決手続代理業務(労務に関するトラブルが起こったとき、裁判を行わずに問題解決をサポートする業務)を行えるようになります。
社会保険労務士の年収
厚生労働省の「令和6年賃金構造基本統計調査」によると、社会保険労務士の平均年収は903.2万円です。
国税庁の「令和5年分 民間給与実態統計調査」によれば、給与所得者全体の平均年収は460万円。比較すると、社会保険労務士の年収のほうが2倍近く高いです。
社会保険労務士の平均年収は、なぜ高いのでしょうか?
その理由として代表的なものには、「高い専門性」「社会的需要の高さ」「独立開業しやすい」などが挙げられます。
社会保険労務士は労務の専門家。国家資格で、独占業務もある上に、近年は人手不足や働き方の変化で需要がますます増えています。
さらに、社会保険労務士事務所として独立開業しやすいこともポイント。厚生労働省の職業情報提供サイト job tagによれば、社会保険労務士の7割近くが自営業やフリーランスとして働いている傾向です。
社会保険労務士はもともと平均年収が高いものの、独立開業などで年収1,000万円以上も夢ではありません。
出典:令和6年賃金構造基本統計調査 結果の概況厚生労働省
出典:令和5年分 民間給与実態統計調査国税庁
出典:職業情報提供サイト job tag 社会保険労務士厚生労働省
まとめ
社会保険労務士の資格の取り方や試験内容、社会保険労務士の仕事内容や年収を詳しく解説しました。
企業の健全な成長を「労務」の面からサポートする社会保険労務士。労働に関する法律が目まぐるしく変化し続ける昨今、今後も需要は高まり続けるでしょう。
社会保険労務士を目指す学生さんは、立正大学 法学部への進学も考えてみてはいかがでしょうか。
立正大学 法学部では、4年間のカリキュラムを通して法律の知識や応用技術を身に付けられるとともに、社会保険労務士を目指す方向けの資格取得講座も開講しています。
ぜひ、以下から立正大学 法学部のホームページも見てみてくださいね。