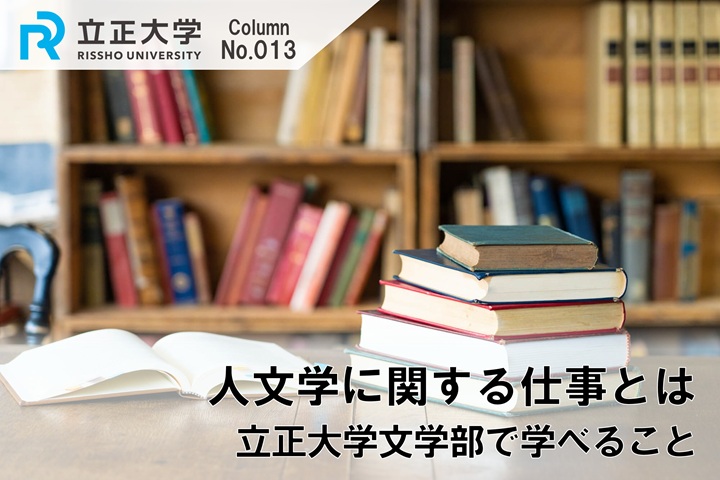歴史学とは? 学ぶ内容や魅力を解説!
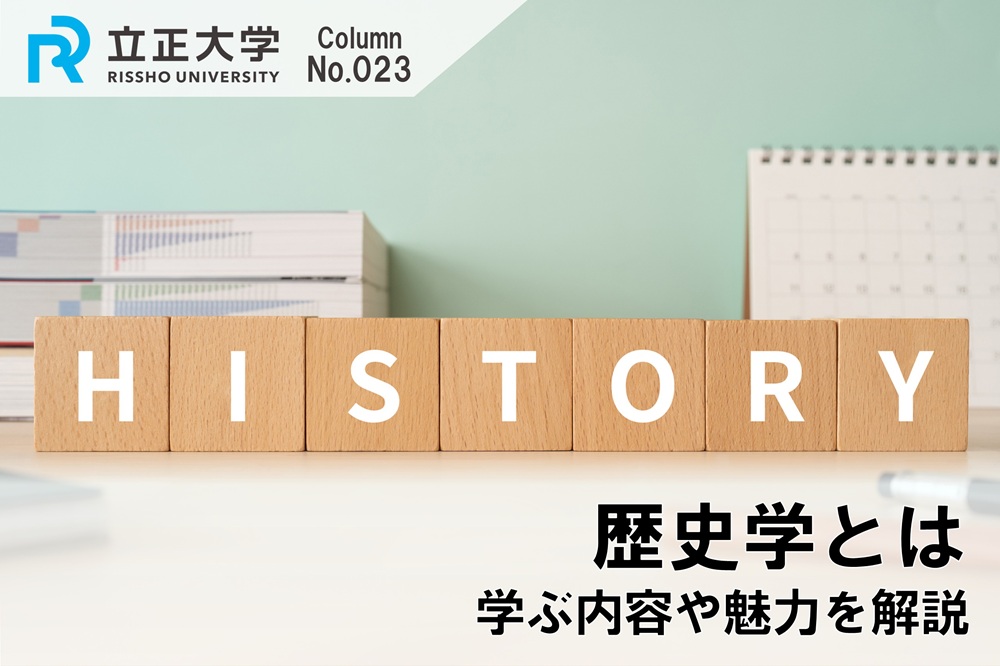
歴史について学ぶ歴史学。単に歴史そのものを知るだけでなく、歴史を学ぶ方法を身に付けたり、歴史について考察したりと、学ぶのが楽しい学問です。
今回は、歴史学では具体的に何を学ぶのか、歴史学を学ぶことにどんな魅力や意義があるのかを解説します。
また、歴史学を専門的に学ぶ場所として、まず挙げられるのが大学の史学科です。そこで、立正大学 文学部 史学科で学べる内容についても紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
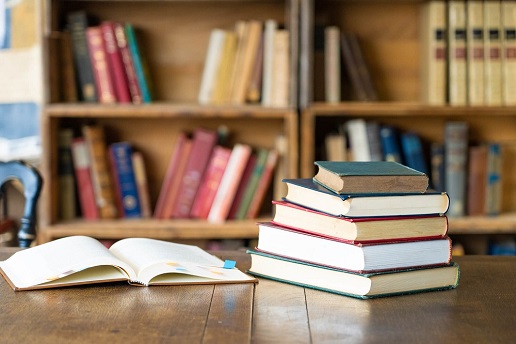
「歴史学を学ぶなら」
立正大学 文学部史学科へ
立正大学文学部史学科では「日本史」「東洋史」「西洋史」「考古学」の4つの分野について幅広く授業を履修することができ、それぞれの礎的な知識を修得することができます。
文学部史学科Webサイトへ歴史学とは
歴史学とは、残された史料や記録を通して、過去に起こった出来事について研究する学問です。何が起こったのか、なぜ起こったのか、その出来事がどのような意味を持ち、どのような影響を与えたのかを知ることで、現代に生かします。
それでは、歴史学では具体的に何を、どうやって学ぶのでしょうか?
-
歴史学では何を学ぶ?
歴史学と一口にいっても、歴史は世界中で積み重ねられてきたものです。歴史学を学ぶ上では、まず「どこの歴史を学ぶか」「どの分野の歴史を学ぶか」といったテーマを決めます。
例えば「どこ」の視点では、地域ごとに「日本史」「東洋史」「西洋史」などです。「どの分野」の視点では、分野ごとに「文化史」「宗教史」「経済史」「政治史」などが挙げられます。
また、遺跡や遺物を土の中から掘り起こし、文字のない時代の社会や文化を知る「考古学」も、代表的な歴史学のテーマの一つです。
ほかにも歴史学では、歴史を時間で見るのか、空間で見るのか、批判的に見るのかといった、「視野や考え方の種類」について学び、身に付けます。
さらに、歴史学を研究するための「方法論」も学ぶことで、決めたテーマをより深く、理論的に研究していく力を育てていきます。
歴史学を学べる代表的な場は、大学の史学科です。史学科には、具体的に以下のような科目で歴史学を学べる講義が開講されています。
- 歴史学入門…「入門」という名前のとおり、歴史学の基礎を学びます。
- 歴史学演習…発展的な科目です。自分で決めたテーマを研究して、結果を発表したりグループディスカッションをしたりすることも。
- 歴史学研究法…歴史学を研究するための方法論を学びます。
「日本史演習」「西洋史研究法」など、地域や分野ごとの名前で開講されていることも多いです。
-
歴史学はどうやって学ぶ?
高校までは、「歴史を知る」ことに焦点を当てた授業が展開されていたでしょう。大学の史学科では、歴史を知ることはもちろん、「歴史を研究する方法」を知り、それを実践して学びを深めていきます。
一つ前の項目で、歴史学を学ぶ上では歴史学を研究するための方法論も学ぶ、と解説しました。では、実際に歴史学を研究するのに、どのような方法が用いられるのでしょうか?
- 史料を読む
歴史学の研究に、史料を読むことは欠かせません。史料とは、歴史が残されたもののことです。紙の文献はもちろん、遺物や遺跡、建築物、絵画、映像、写真、伝承までも史料に含まれます。
歴史学では、史料の正しい読み方を身に付けた上で、史料をもとに学びを深めたり、考察したりしていきます。
- フィールドワーク
フィールドワークとは、現地に赴いて情報を収集する活動です。単に情報収集に役立つほか、学んだことや考察したことが本当かどうかを実証する場にもなります。
特に考古学を学ぶ場合、発掘調査をしたり遺物に触れたりするために、フィールドワークを行う機会が多くなるでしょう。
- テーマを設定して論文を書く
史料の読み込みやフィールドワークを重ねたら、自分の考えをまとめ、論文として言語化します。論文を書く中で、ディスカッションや批評によって客観的な意見を取り入れるのも重要な過程です。
- 史料を読む
歴史学を学ぶ魅力・意義とは
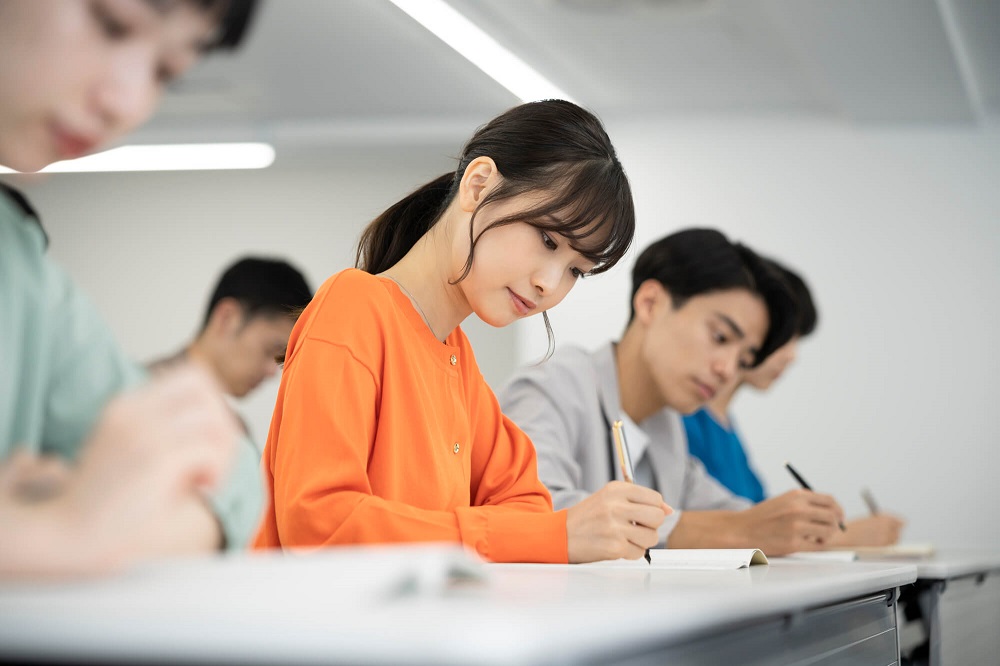
よく、「歴史学って何の役に立つの?」という声が見られます。歴史学の知識は就職に直接結びつきづらい面があることが要因でしょう。
しかし、歴史学には学ぶ魅力や意義がたくさんあるのです。
-
歴史学は現代・未来に生かせる
歴史学は、私たちが現代を生きる上で、さらに未来の世代がより幸せに暮らすために役立ちます。
例えば、戦争の歴史を知ることで、戦争をなくさなくてはいけない理由や、戦争を起こさないために何ができるかを考えることができます。
また、歴史は先人たちの暮らしの積み重ねでもあります。私たち一人ひとりの生活においても、ちょっとした悩みや問題を解決するのに、歴史の知識が役立つこともあるでしょう。
歴史学は、人類が同じ過ちを繰り返さないため、人々の暮らしをより豊かにするための学問でもあるのです。
-
歴史学は思考力を育てる
物事に対して「なぜ?」と疑問を持って、答えを考えたり導き出したりする思考力は、人生のあらゆる場面で必要になります。
歴史学の研究は、考えることの連続です。「なぜこの出来事が起こったのか?」という疑問から研究が始まり、調査と考察を繰り返して、答えに至ります。この過程の中では、自らの考察の整合性を取る必要がありますし、他者の意見も取り入れることで、客観的な思考力が育っていきます。
論理的・客観的に考える力、疑問を打ち立てて解決に向かう思考力は、社会において必要なのはもちろん、生きるのに役立つ力です。
-
歴史学が役に立つ仕事
歴史学を学ぶ魅力や意義を解説してきましたが、歴史が好きな方なら歴史学が直接役に立つ仕事に就きたいですよね。
歴史学を生かせる仕事としてまず挙げられるのが、教職です。学んだ知識を教えられるのはもちろん、上記で解説した歴史学を学ぶ魅力や意義も伝えられれば、教養や思考力に富んだ大人への成長を助けられるかもしれません。
ほかにも、博物館の学芸員や図書館の司書は、歴史学の知識が生きる仕事です。
さらに出版分野では、歴史に関する書籍を執筆・編集したり、海外の歴史書籍を翻訳したりと、「後世に歴史を伝える」仕事ができます。
また、観光協会や文化会館で地域の文化の振興に携わることもできますし、歴史学者として研究を生業とする道もあるでしょう。
このように、歴史学の知識がそのまま役に立つ仕事はたくさんあるのです。
立正大学 文学部 史学科について
立正大学には、文学部があります。中でも歴史学を学べるのが、史学科です。
ここでは、立正大学 文学部 史学科について紹介するとともに、文学部のほかの学科についても紹介していきます。
-
立正大学 文学部 史学科について
史学科では、まず1年次に「日本史」「東洋史」「西洋史」「考古学」の4つの分野について幅広く授業を履修することで、各分野の基礎知識を習得できます。
そして2年次以降は、4つの分野から専攻分野を決めて、それぞれのゼミナールに所属することになります。
歴史学についての幅広い知識を身に付けた上で、興味のある分野を専門的に研究できるようになるのが魅力です。
例えば、もともと日本史に強い興味があった方は日本史のゼミナールに、1年次のカリキュラムで西洋史をもっと研究したいと思った方は西洋史のゼミナールに進むなど、学生それぞれの興味・関心に合わせて進路を選べます。 - 文学部史学科「学びの特徴」
- フィールドワークで体験的・実証的に学ぶ
調査する地域に赴き、史料では得られない現地の雰囲気や細部の情報を収集します。3・4年次の長期休暇には遺構測量や発掘調査なども行います。 - 史料を読み解き論理的に思考する
史学研究に必要な史料を収集し、史実を読み解いて、根拠に基づいた説得力のある議論を展開するための論理的思考力を磨いていきます。 - 自分の考えを的確に伝える学び
演習ではテーマについて史料を収集し、研究書などの文献を読みながら調査を進め、発表でわかりやすく伝えるためのプレゼン技術を学びます。
- フィールドワークで体験的・実証的に学ぶ
- 文学部史学科「学びの領域」
- 幅広い視点から「日本史」を見る
史料の読解法から収集、研究を行う技術まで、ステップアップしながら学修。「近現代の政治史」「中世の生活史」「近世教育社会史」等、複数のテーマを扱い、歴史を幅広い視点から捉えます。 - 原典史料をもとに「東洋史」を学ぶ
特に原典史料に触れることを重視。出土文献・出版文化史・東アジア文化交流史を中心に、「中国」「朝鮮半島」「イスラーム」「中央アジア」等の多様な地域の歴史も研究できます。 - 「西洋史」を多角的に学修
ヨーロッパ・アメリカの歴史について多角的に迫り、新しい観点探究。ジェンダー・出産・身体等の視点からも歴史を考えます。 - フィールドワークを含めた現地調査で「考古学」を深める
先史時代から文字史料の存在する歴史時代まで、多様な遺跡・遺物を研究。実地調査を重視します。
- 幅広い視点から「日本史」を見る
-
ゼミナール
ゼミナールは演習科目で、先生の話を受動的に聞く形式の「講義」とは異なり、グループディスカッションや論文発表など、能動的に研究活動ができるのが特徴です。また、ゼミナールは少人数であることが多いので、自ら発言したり、先生やゼミ仲間と交流したりしやすいのも魅力。
一般的に、3年次からゼミナールを開講する大学が多いですが、立正大学では2年次からと早い時期にゼミナールを開講します。
- 開講科目の例
- 研究法
日本史・東洋史・西洋史・考古学の各分野を研究するために必要な、基礎的な考え方や方法論について説明する講義です。4つの分野それぞれで開講されています。 - 特講
こちらも4つの分野それぞれで開講されています。担当教員が自らの専門分野について、これまでの研究成果を踏まえて講義します。研究方法も習得できるので、自らの研究にも役立つでしょう。 - 古文書学
古文書の様式や形態、機能を学ぶことで、古文書を正確に読み、正しく理解する力を養います。
- 研究法
-
史学科以外の学科について
立正大学 文学部の史学科以外の3つの学科についても簡単にご紹介します。
- 哲学科…「西洋の哲学」「日本や東洋の哲学」「倫理学」「哲学を自分の問題に応用」という4つの領域から、古今東西の哲学を学びます。
- 社会学科…「メディア・ジャーナリズム」「都市・地域・犯罪」「環境・家族」「宗教・社会心理」などの多角的な視点から、社会を分析する技術を学びます。
- 文学科 日本語日本文学専攻コース…日本語学と日本文学を基礎から学びます。日本の「言葉」「詩歌」「物語」「日本列島の文学」に加え、日本と関わりの深い「東アジア文化」という5つの柱でさまざまな講義を受けられます。
- 文学科 英語英米文学専攻コース…英語圏の文学・文化と言語学・コミュニケーションを学びます。英語の意味や歴史を学ぶ「英語学」と、「英米文学・文化研究」の2つの領域で学びを深めます。
史学科以外でも、人間が築き上げてきた文化を学ぶ文学部では、どの学科であっても歴史に触れないことはありません。
進路に迷っている方は、以下から立正大学 文学部についても調べてみてください。
まとめ
歴史学とは、残された史料や記録を通して、過去に起こった出来事について研究する学問です。
歴史を学ぶことで、今ある社会がどうやってできたのかを知り、よりよい未来に生かすことができます。
立正大学 文学部 史学科では「日本史」「東洋史」「西洋史」「考古学」の4つの分野で歴史学を学びます。
立正大学 文学部には史学科のほかにも3つの学科がありますので、気になる方は以下から史学科やほかの学科について、見てみてくださいね。
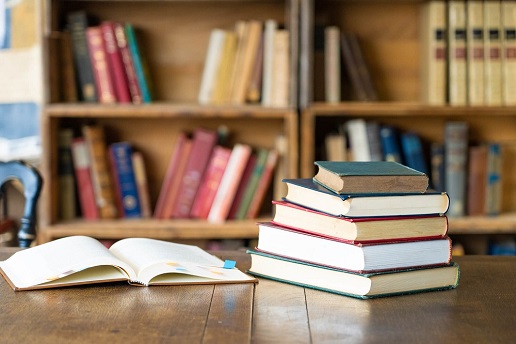
「歴史学を学ぶなら」
立正大学 文学部史学科へ
立正大学文学部史学科では「日本史」「東洋史」「西洋史」「考古学」の4つの分野について幅広く授業を履修することができ、それぞれの礎的な知識を修得することができます。
文学部史学科Webサイトへ 文学部Webサイトへ