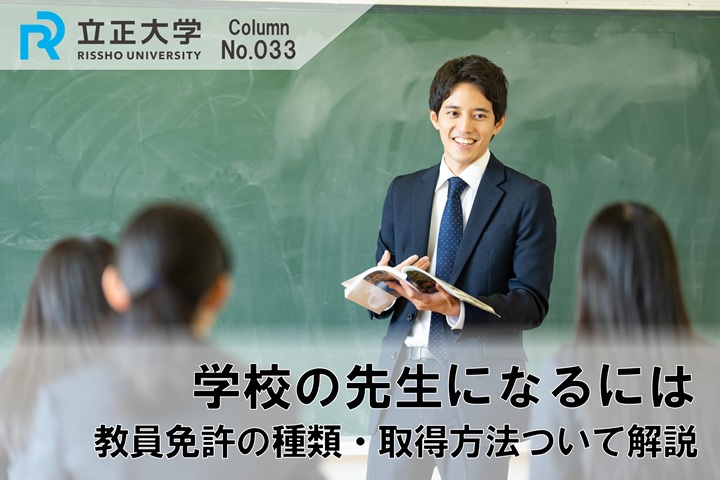地球環境に関する仕事とは (地球環境科学部で学べること)

地球温暖化や森林破壊、海洋汚染など、地球の環境問題は日々深刻化しています。
私たちが住むこの地球を守りたい——そんな思いで、地球環境を守る仕事に就きたいと考えている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、地球環境を守る仕事を詳しくご紹介。さらに、地球環境を守る仕事に就くのに有利になる資格も紹介します。
立正大学 地球環境科学部では、地球の環境問題の改善・解決に貢献できる人材育成を目指したカリキュラムを実施しています。記事の最後では地球環境科学部についての解説もしているので、ぜひ最後までご覧ください。
地球環境を守る仕事11選
早速、地球環境を守る仕事にどんなものがあるのか見ていきましょう。
地球環境を守る代表的な仕事を11個ピックアップしました。
-
自然保護官(レンジャー)
自然保護官(レンジャー)は、国家公務員の職種の一つです。環境省に属し、主に国立公園の管理、自然と触れ合う施設の整備、野生生物の保護管理などを行います。
勤務するのは全国各地にある地方環境事務所であり、国立公園や自然環境保全地域など自然あふれる地域で日々活動することになります。
国家公務員として地球環境を守る仕事ができるのが魅力ですが、採用されるには一年に十数人程度の狭き門をくぐり抜けなければなりません。
-
環境コンサルタント
環境コンサルタントは、企業に対して環境保全のためのコンサルティングを行う仕事です。
地球環境の問題が深刻化していく中、企業それぞれに環境保全への意識が求められるようになっています。「自然にやさしいパッケージ」といった言葉が商品に書かれているのを見たことがある方も多いのではないでしょうか。
環境コンサルタントは、このような「地球環境を守るために企業ができること」をアドバイスする仕事です。年々需要が高まっている仕事でもあります。
-
ビオトープ管理士
ビオトープ管理士は、地域に存在していた多様な自然を復元したり、創出したりする仕事です。「ビオトープ」の「ビオ」は「生きものたち」、「トープ」は「空間」を指すドイツ語です。
ビオトープ管理士は公益財団法人 日本生態系協会が認定する資格で、ビオトープ管理士の資格があることで、就職や仕事上で有利になる場合があります。
例えば、都市・地域計画、土木・造園、農業などにおいて、ビオトープ管理士であることで「環境保全への知識と理解が確かな人材だ」と信頼してもらいやすくなるのです。
-
環境保全エンジニア
環境保全エンジニアは、環境保全のための技術や機器を開発する仕事です。
公害を起こさない機器や廃棄物を安全に処理する装置、大気汚染や水質汚染を調査する機器、省エネ技術などの開発を通して、環境保全に貢献します。
環境に関する知識のほか、工学・理工学系の深い知識が求められます。
-
環境アセスメント調査員
環境アセスメント調査員は、新しく道路や鉄道、ダムなどの開発・建設を行う際に、その地域の環境への影響がどの程度かを調査する仕事です。大きな影響があると分かれば、それを回避するための提案も行います。
環境アセスメント調査員自体に資格が必須というわけではありませんが、一般社団法人 日本環境アセスメント協会が認定する「環境アセスメント士」の資格を持っていると、信頼してもらいやすくなります。
-
環境計量士
環境計量士は、工事現場や事業所などにおいて、有害物質の濃度や騒音、振動を計量する仕事です。
環境計量士は国家資格で、「環境計量士(濃度関係)」「環境計量士(騒音・振動関係)」の2つがあります。
特に、計量を完了したことを証明する「計量証明書」は環境計量士にしか発行が許されておらず、資格取得は必須です。
-
環境分析技術者
環境分析技術者は、大気汚染や水質汚染、地質汚染などを調査し、環境破壊の現状と、それが生態系に与える影響を調べる仕事です。
「技術者」と付いているのは、調査や報告、改善策や予防策の提案の際に、化学的な知識や技術を伴うためです。環境への知識のほかに、測定機器を使いこなすスキルも必要になります。
-
作業環境測定士
作業環境測定士は、工場などの作業現場で発生する有害物質を測定する仕事です。人の体に害を与えるような有害物質が確認されたら、改善するためのアドバイスも行います。
作業環境測定士は国家資格で、試験に合格するだけでなく、指定の講習を受けて登録する必要があります。
-
海洋工学研究・技術者
海洋工学研究・技術者は、海の環境保全に焦点を当てた仕事です。海洋資源の調査や海洋で用いられる新たな技術開発を通して、海洋資源を私たちの生活に役立てたり、地球環境の保全への取り組みを実施したりします。
国の研究機関や民間の海洋開発関連企業に所属して働くのが一般的です。
-
環境教育インストラクター
環境教育インストラクターは、環境についての知識や考え方を教える指導者です。
例えば、小中学校で生徒たちに環境に関する講座を開いたり、自治体の環境イベント開催を支援したりと、環境保全の意識を人々に広める役割を担います。
環境インストラクターになるには、環境省も推進する「環境教育インストラクター認定(特定非営利活動法人 環境カウンセラー全国連合会)」の認定を受けるのを目指すとよいでしょう。
-
気象予報士
気象予報士は、さまざまな気象観測データや数値予報結果をもとに気象予報を行う仕事です。テレビのニュースで気象予報士が活躍しているのは、誰もが見たことのある光景でしょう。
実は、テレビに出演している気象予報士はほんの一部で、多くの気象予報士は裏方で気象予報の業務に当たっています。民間の気象予報会社では、地域を絞って気象予報を行ったり、顧客に気象予報をもとにした解説やアドバイスを提供したりするところもあります。
気象予報士は国家資格です。試験に合格して気象予報士として登録されれば、国や自治体、民間企業、さらにはフリー契約としてでも、気象予報士として活躍できます。
地球環境を守る仕事におすすめの資格7選

地球環境を守る仕事について見てきました。地球環境を守る仕事にはさまざまあり、特定の資格が必須な仕事もあれば、そうでないものもあることが分かったのではないでしょうか。
そこで、ここからは地球環境を守る仕事に就くために取得をおすすめしたい資格を7つ紹介します。
-
環境カウンセラー
環境カウンセラーは、企業や個人、NGOなどが行う環境保全活動について、アドバイス(環境カウンセリング)を行う人材として、環境省が登録するものです。
国家資格などではなく、受験も必要ありません。環境保全の取り組みを豊富に行った経験のある方や、専門知識を持つ方に対し書面審査と面接審査を実施して、一定の水準に達していると認められると登録されます。
出典:環境カウンセラーとは環境省
-
森林インストラクター
森林インストラクターは、一般社団法人 全国森林レクリエーション協会が認定する資格です。
森林を利用する一般の方に対して、森林の動植物について解説したり、キャンプなどの野外活動の実施に協力したりします。
試験は筆記試験と面接試験で構成されています。環境省も推進している資格認定制度です。
-
環境計量士
環境計量士は、先にも解説したとおり有害物質の濃度や騒音、振動を計量する仕事で、「環境計量士(濃度関係)」「環境計量士(騒音・振動関係)」の2つの国家資格があります。
まずは国家試験に合格し、実務経験を1年以上積んだり、特定の講習を修了したりしてから登録することで、資格を取得するのが一般的なルートです。
出典:計量士関係経済産業省
-
公害防止管理者
公害防止管理者は国家資格で、有資格者は公害発生施設を持つ工場内において、公害が発生するのを防ぐ役割を担います。
国家試験の合格で取得でき、受験資格は特に定められていません。
出典:公害防止管理者等経済産業省
-
自然再生士
自然再生士は、一般財団法人 日本緑化センターが認定する民間資格です。「自然再生に必要な知識・技術・経験を有する、自然再生の推進者」と位置づけられています。
資格を取得するには、試験に合格するルートのほかに、森林インストラクターや技術士の有資格者であれば講習会の受講というルートもあります。
なお、試験を受験する場合、満23歳以上であることや一定の実務経験が必要です。
ちなみに、「自然再生に必要な基礎的な知識を有する、自然再生の推進者」と位置づけられている「自然再生士補」という資格もあり、こちらは指定の大学での特定の課程や、講習を修了することで取得できます。
出典:自然再生士資格制度一般財団法人 日本緑化センター
-
技術士(環境部門)
技術士は国家資格で、全部で21の部門に分かれています。そのうちの一つが環境部門です。
技術士(環境部門)の資格があることで、地球環境を守る仕事に就職・転職する際に有利になります。
国家試験は一次試験と二次試験で構成されていますが、一次試験に受験資格が設けられていないのに対し、二次試験を受験するには「技術士補」の資格を持っていることなど、一定の要件が求められます。
出典:試験・登録情報公益社団法人 日本技術士会
-
気象予報士
気象予報士は、先に解説したとおり、気象予報士になるために必要な国家資格です。
受験資格は特に定められていないものの、試験が学科試験と実技試験で構成されており、特に実技試験の難易度が高いことから合格率は4~6%と難関です。
気象予報士の資格については以下のコラムで詳しく解説しておりますので、興味のある方はぜひ読んでみてください。

気象予報士の資格とは 取得方法・試験概要等を解説
記事はこちら出典:気象予報士試験 試験概要一般財団法人 気象業務支援センター
立正大学 地球環境科学部で学べること

立正大学には、地球環境科学部があります。地球環境科学部では、現在人類が直面しているさまざまな地球環境問題について、改善や解決に貢献できる人材の育成を目指したカリキュラムが実施されています。
地球環境科学部は、さらに環境システム学科と地理学科の2つに分かれます。以下で、それぞれの特徴や就職先、取得を目指せる資格を見ていきましょう。
-
環境システム学科
「環境システム学」とは、私たちを取り巻くさまざまな自然環境を相互に作用し合うシステムとして捉えた上で、環境保全を視野に入れながら、生物による複雑な影響を含めて体系的に理解する、総合的な学問です。
環境システム学科は、環境問題を主に自然科学的側面から把握・認識しようとする学科となっています。
環境システム学科は、さらに以下の2つのコースに分かれています。
生物・地球コース…動植物の生態や生物の多様性、地表環境を構成する地形や岩石など、生物圏や地圏、環境情報に関する知識を習得する。
気象・水文コース…身近な大気現象や気候変動、水循環や水質汚染、さまざまな特徴を持つ地下水・湧水など、気圏や水圏、環境情報に関する知識を習得する。
どちらのコースもフィールドワークを多く取り入れており、実践的な知識と調査法を身に付けられるのが魅力です。
また、地球規模の環境データを収集・解析するには欠かせない、リモートセンシングや化学分析などの最新技術と情報処理能力も習得できます。
-
環境システム学科卒業生の就職先
環境システム学科の卒業生の就職先として、業界としては地図・測量・環境・建設といった環境と深い関わりのある仕事のほか、情報通信や機械・化学・技術、鉄道・運輸、さらには公務員や教員など、幅広い就職実績があります。
環境システム学科卒業生の就職先を詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
-
環境システム学科で取得を目指せる資格
環境システム学科では、就職に役立つさまざまな資格取得を目指せます。
以下は、資格試験や検定試験に合格する必要があるものの、資格に関連する講義があるため取得に有利になる資格です。
- 気象予報士
- 環境計量士
- 公害防止管理者
- 自然再生士
- 測量士
測量士については、以下のコラムで詳しく解説しておりますので是非ご覧ください。
測量士(測量士補)になるには 資格取得方法・試験概要等を解説
記事はこちら - 技術士
- 技術士補
- 情報処理技術者
情報処理技術者試験については、以下のコラムで詳しく解説しておりますので是非ご覧ください。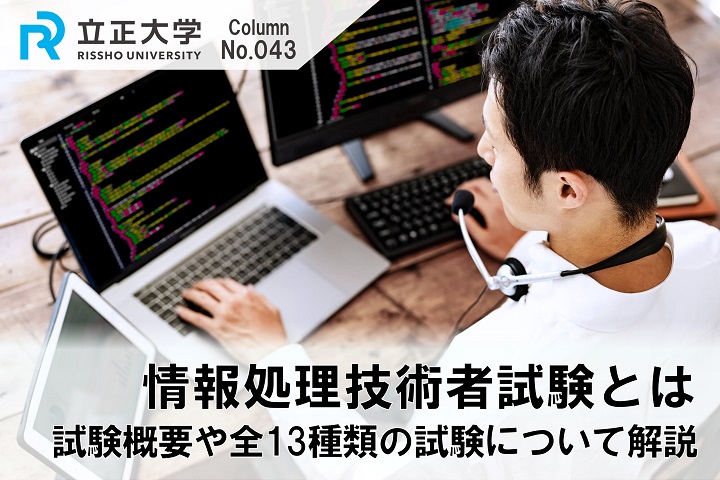
情報処理技術者試験とは 試験概要や全13種類の試験について解説
記事はこちら - システムアドミニストレータ
さらに、特定の課程を修了することで、以下の資格を取得できます。 - 自然再生士補
- 測量士補
- GIS学術士
- 中学校教諭一種免許状(理科)
- 高等学校教諭一種免許状(理科)
- 学校図書館司書教諭
- 社会教育主事(任用資格)
- 社会福祉主事(任用資格)
- 博物館学芸員(任用資格)
- 図書館司書
-
地理学科
「地理学」とは、地球上で見られるさまざまな事象を把握し、それらの相互の関係を地域的・空間的な観点から明らかにする学問です。
地理学科では、人文地理学や自然地理学、地誌学を中心に学びを深めていきます。
人文地理学では地域の人口や経済といった構成要素を、自然地理学では地形や気候、水、自然災害などについて、地誌学では特定地域の地域的性格を、自然環境と人間生活との関係から総合的に研究します。
観光やまちづくり、自然保護、環境問題など、人文社会系と自然系が融合した幅広い分野を扱うのが特徴です。
フィールドワークも豊富で、履修するカリキュラムによっては世界各国を訪れることもできます。
-
地理学科卒業生の就職先
地理学科の卒業生の就職先として、地図製作・測量や都市・不動産・建設コンサルタント、鉄道・運輸・旅行・観光といった地理に関連する業界のほか、金融・保険、製造・流通・サービス、公務員や教員も挙げられます。
先にご紹介した環境システム学科の卒業生と比較しても大きな差はないので、環境システム学科か地理学科か迷ったら、興味のある分野や取りたい資格を重視するとよいでしょう。
地理学科卒業生の就職先をもっと知りたい方は、以下からご覧ください。
-
地理学科で取得を目指せる資格
地理学科で特定の課程を修了することで取得できる資格は以下のとおりです。
- 中学校教諭一種免許状(社会)
- 高等学校一種免許状(地理歴史)
- 学校図書館司書教諭
- 測量士補(測量学実習修了者)
- GIS学術士
- 地域調査士
- 社会教育主事
- 学芸員
また、受験が必要なものの、資格取得を目指す講座を開講しているため資格取得に有利になる資格もあります。 - 国内旅行業務取扱管理者
- 総合旅行業務取扱管理者
まとめ
地球環境を守る仕事には、自然保護官(レンジャー)をはじめ、環境コンサルタントやビオトープ管理士など、さまざまな仕事があることが分かりました。
地球環境を守る仕事を目指すなら、希望の仕事に関連する資格を取得したり、地球環境について専門的に学べる大学に進学したりするのがおすすめです。
立正大学 地球環境科学部では、環境システム学科と地理学科それぞれで、地球の環境問題を改善・解決するための知識や技術を学べるカリキュラムを実施しています。
所定の課程を履修することで取得できる資格も数多くありますので、地球環境を守る仕事を目指している方は、ぜひ以下から立正大学 地球環境科学部についても調べてみてくださいね。

「地理・地球環境・気象関係を学ぶなら」
立正大学 地球環境科学部へ
「地球の問題に挑む。」地球環境科学部の学びの柱は、フィールドワークとアクティブ・ラーニング。自然環境や社会、地域の諸問題を五感で捉えながら発想力と行動力を培い身近なことから大きな問題まで、多様な課題を解決できる専門家を目指します。
地球環境科学部Webサイトへ