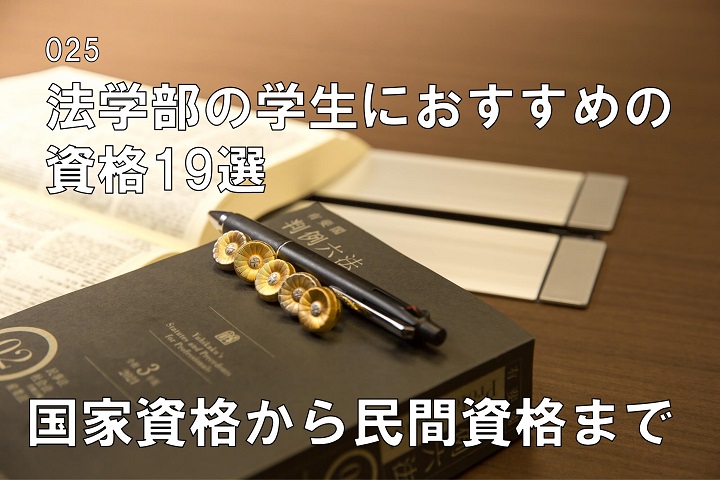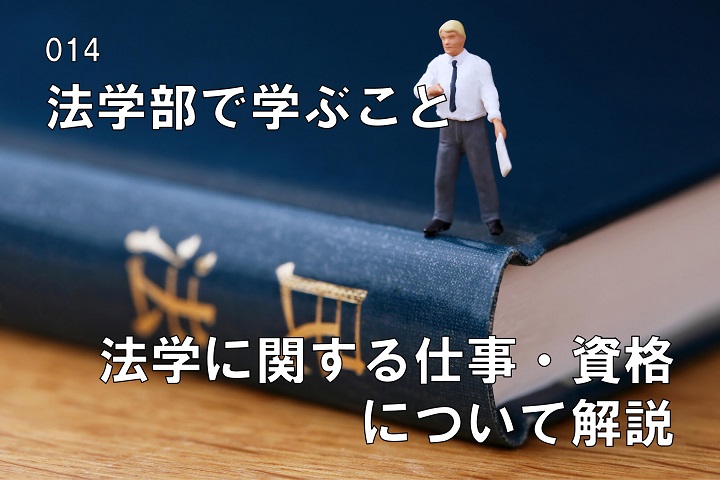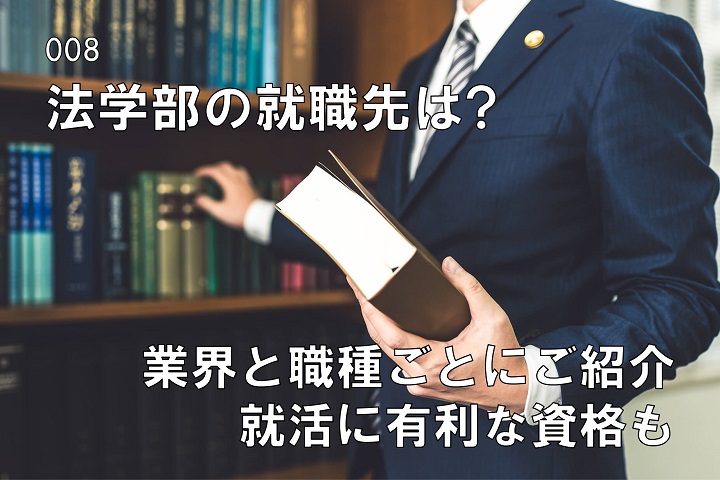行政書士の資格とは 取得方法・試験概要等を解説
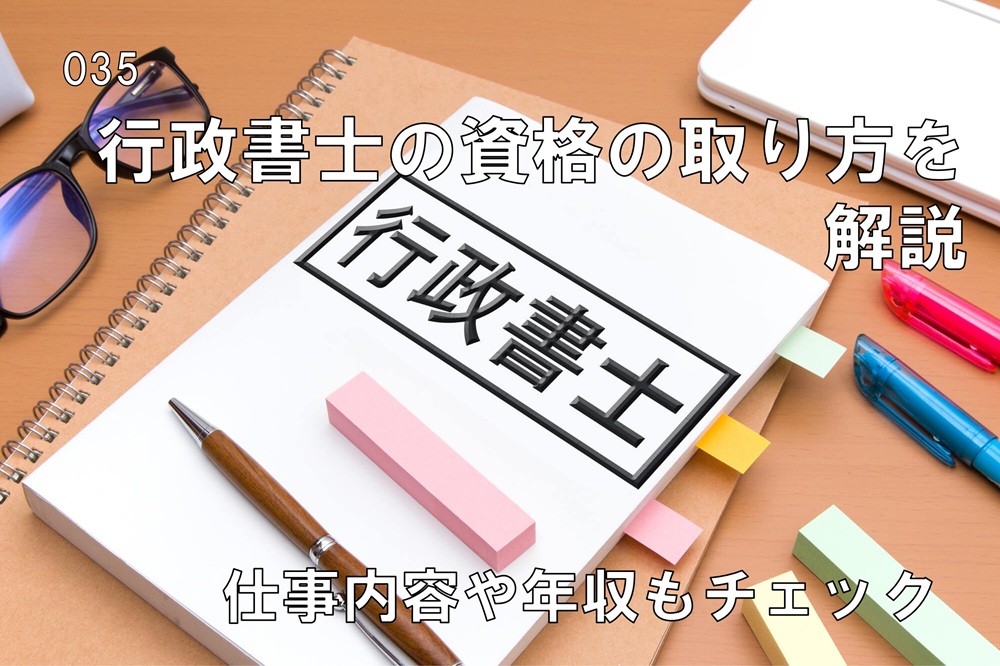
行政手続きの専門家である行政書士。企業から個人まで、幅広いお客さまを「書類作成」を通して支援するお仕事です。
行政書士の資格は国家資格で、取得するには「国家試験の合格」がもっとも一般的ですが、ほかの国家資格や実務経験によっても取得できます。
今回は、行政書士の資格について、資格の取り方から国家試験の概要などを詳しく解説。
初めに行政書士の仕事内容や年収も紹介するので、「行政書士に興味がある!」という方はぜひ最後までご覧ください。
行政書士の仕事内容
行政書士は、行政手続きの専門家です。行政書士の仕事内容として、「独占業務」に焦点を当てて見ていきましょう。
独占業務とは、「特定の資格を持っていなければ仕事として行えない業務」のことで、行政書士の場合は以下の3つが独占業務に当たります。
- 官公署に提出する書類の作成
- 権利義務に関する書類の作成
- 事実証明に関する書類の作成
「官公署に提出する書類」とは、省庁や都道府県庁、役所、役場、警察署などに提出する書類をいいます。
その多くは許認可に関する書類とされており、例えば建設業許可申請や飲食店営業許可申請がこれに当たります。特定の業種を営む際には、こういった許可申請を官公署に提出しなければなりません。
「権利義務に関する書類」とは、権利の発生や存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする書類です。
例えば、遺産分割協議書や契約書、念書、示談書、協議書、内容証明、告訴状、告発状、嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書、定款が挙げられます。
個人で作成する必要があるケースも多く、行政書士に作成を依頼することで、法的に適切な書類を確実に作成できます。
「事実証明に関する書類」とは、「社会生活に交渉を有する事項を証明するに足りる文書」とされていて、その名のとおり事実を証明する書類です。
例えば、位置図や案内図、現況測量図など実地調査に基づく各種図面類や、議事録、会計帳簿、貸借対照表、損益計算書等の財務諸表、申述書などが該当します。
法人から個人まで、幅広い層が行政書士の手を必要とする可能性があることが分かったのではないでしょうか。
出典:行政書士の業務日本行政書士会連合会
行政書士の年収
行政書士の平均年収は、厚生労働省の「令和6年賃金構造基本統計調査の結果」によると591万円です。
国税庁の「令和5年分 民間給与実態統計調査」によると、給与所得者全体の平均年収は460万円とのことなので、行政書士の年収は平均より100万円以上高いことになります。
行政書士として年収を上げるためにもっとも有効なのは、独立開業です。初めは行政書士事務所に勤めるなど、従業員として働き、経験を積んだら独立することで、平均年収以上の年収も狙えるでしょう。
また、ほかの士業系国家資格を取得して、行政書士だけでなくほかの士業と兼業するのもおすすめ。業務の幅が広がるので、より多くの方に依頼してもらいやすくなります。
詳しくは後述しますが、行政書士はほかの士業系国家資格よりも比較的取得しやすい国家資格です。
平均年収も高めなので、取得を目指してみてはいかがでしょうか。
出典:令和6年賃金構造基本統計調査の結果厚生労働省
出典:令和5年分 民間給与実態統計調査国税庁
行政書士の資格の取り方

行政書士の資格の取り方は3つあります。
-
国家試験の合格
行政書士国家試験に合格して行政書士になるのは、もっとも一般的なルートです。
国家試験を受けるのに必要な要件は特になく、年齢や国籍を問わず、誰でも受験できます。
-
ほかの士業系国家資格を取得する
弁護士・弁理士・公認会計士・税理士いずれかの国家資格を持っている場合、国家試験を受けずとも行政書士の資格を得られます。
この4つの資格は、すべて行政書士よりも取得難易度が高い国家資格ではあるので、行政書士になるためにこのルートを利用する方は少ないでしょう。
ですが、「行政書士と、ほかの士業系資格も取得したい」という方はぜひ検討してみてください。
-
特認制度を利用する
こちらは行政書士やほかの士業系の国家試験を受けなくても、行政書士の資格を取得できるルートです。
国家公務員または地方公務員として、行政事務に従事した期間が20年以上(高校を卒業している場合は17年以上)あれば、行政書士の資格を得られます。
これを「特認制度」といい、長い年月を要するものの、試験を受けなくてよい点はメリットといえるでしょう。
行政書士国家試験について
ここからは、行政書士になる上でほとんどの方が受けることになる国家試験について、詳しく解説していきます。
-
受験資格
行政書士の国家試験には、受験資格が特にありません。
年齢や学歴、国籍などに関係なく、誰でも受験できます。
-
スケジュール
行政書士試験のおおまかなスケジュールは以下のとおりです。
行政書士試験の案内は、その年の7月上旬に公示されます。一般財団法人 行政書士試験研究センターのホームページから確認しましょう。試験の公示 7月上旬 受験願書配布期間 7月中旬~8月中旬 受験申し込み受付期間 7月中旬~8月中旬
(受験願書配布期間と同じ。インターネット申し込みでは期日が約1週間延長される)受験票の送付 10月 試験日 11月上旬 合格発表日 1月下旬 合格者へ合格証の発送 2月中旬
一般財団法人 行政書士試験研究センター
受験の申し込みをするには、受験願書を請求することが必要です。受験願書は、窓口で受け取る方法と、センターに郵便で請求して郵送してもらう方法の2つがあります。
受験願書を入手したら、インターネットまたは郵送で申し込みの手続きを行います。
申し込み受付期間は、受験願書配布期間と同じです。願書の入手が遅れないよう注意しましょう。ただし、インターネットで申し込みをする場合には、申し込み受付期間が約1週間延びます。
申し込みが正しく完了していると、10月に圧着した郵便はがきで受験票が届きます。受験票に試験場などが記載されているので、詳しく確認しましょう。
試験日は11月上旬で、基本的に第2日曜日です。
合格発表は翌年1月下旬で、合格者の受験番号が行政書士試験研究センター事務所の掲示板と、ホームページに公表されます。同時に、圧着した郵便はがきで、合否通知書が発送されます。
その後、2月中旬に合格者を対象に合格証が発送されます。
以上が、行政書士試験の一連のスケジュールです。
-
試験内容
行政書士試験は、筆記試験によって行われます。
試験科目は以下のとおりです。
なお、法令に関する問題については、基本的に現在施行されている最新の法令が適用されます。試験科目 内容 行政書士の業務に関し必要な法令等
(出題数46題)・憲法
・行政法
(行政法の一般的な法理論、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法及び地方自治法を中心とする。)
・民法
・商法
・基礎法学行政書士の業務に関し必要な基礎知識
(出題数14題)・一般知識
・行政書士法等行政書士業務と密接に関連する諸法令
・情報通信・個人情報保護
・文章理解
出題の形式は、「行政書士の業務に関し必要な法令等」は択一式および記述式、「行政書士の業務に関し必要な基礎知識」は択一式です。
記述式は、40字程度で記述するものが出題されます。 -
費用
行政書士試験を受けるのにかかる費用は、受験手数料10,400円です。
インターネット申し込みの場合、このほかにシステム手数料370円がかかります。払い込みは、受験者本人名義のクレジットカードか、コンビニエンスストアで行います。
郵送で申し込む場合は、専用の振替払込用紙で郵便局(ゆうちょ銀行)の窓口で払い込み、振替払込受付証明書を受験願書に貼付します。
一度払い込んだ受験手数料は、受験しなかったとしても返還されないので注意してください。
ちなみに、行政書士試験に合格後、行政書士として登録する際には、受験手数料よりも大きな金額がかかります。
金額は活動する都道府県によって異なるものの、例えば東京都の場合は以下のとおりです。
登録や入会にかかる一時的な費用だけでなく、会費などの定期的に発生する費用もあることが分かります。登録手数料 25,000円 入会金 200,000円 東京都行政書士会会費3カ月分 18,000円 東京行政書士政治連盟会費3カ月分 3,000円 登録免許税(収入印紙) 30,000円
行政書士の登録に、期限はありません。一度試験に合格してしまえば、その後はいつでも行政書士として登録できます。
そのため、特に学生の方や、まだ行政書士として働く予定がない方などは、試験に合格しても登録しないという手もあります。出典:登録・入会のご案内東京都行政書士会
-
合格率・難易度
行政書士国家試験の、過去5年間の受験者数と合格者数、合格率は以下のとおりです。
例年、10〜13%前後で推移しています。試験年度 受験者数 合格者数 合格率 令和6年度(2024年) 47,785人 6,165人 12.90% 令和5年度(2023年) 46,991人 6,571人 13.98% 令和4年度(2022年) 47,850人 5,802人 12.13% 令和3年度(2021年) 47,870人 5,353人 11.18% 令和2年度(2020年) 41,681人 4,470人 10.72%
合格できるのは、ざっくり10人に1人。そのため行政書士国家試験の難易度は高いですが、実はほかの士業系国家資格と比較すると難易度は易しめといえます。
士業系国家資格として代表的な資格の、国家試験合格率は以下のとおりです。
- 弁護士:約40%
- 司法書士:3〜4%
- 弁理士:6〜10%
- 税理士:12〜15%
- 社会保険労務士:4〜6%
一見、「弁護士と税理士のほうが難易度は低いのでは?」と思える数値です。
しかし、弁護士は国家試験を受けるまでに法科大学院を修了するか、難易度が非常に高い予備試験に合格することが必要。そもそも受験するハードルが高い試験なのです。
一方の税理士は、「全11科目から5科目を選び受験する」という特殊な方式を採っており、この合格率も1科目の合格率です。それを踏まえると、税理士の国家試験取得のハードルも高いといえます。
受験資格がなく、国家試験に1回合格すれば国家資格を取得できる行政書士は、ほかの士業系国家資格と比べて取りやすい資格といえるのです。
出典:最近10年間における行政書士試験結果の推移一般財団法人 行政書士試験研究センター
行政書士試験対策はどうやる?

ここまで、行政書士の国家資格の取り方や、試験について解説してきました。
受験資格が特に定められていない行政書士試験。いつでも挑戦しやすい分、どうやって勉強して対策すればいいのか分からない方もいるのではないでしょうか。
ここでは、行政書士試験対策の主な方法をご紹介します。
-
独学で勉強する
市販のテキストや問題集、過去問を活用して、独学で勉強する方法です。
独学のメリットは、何よりも費用を抑えられること。自分のペースで勉強できるため、特に社会人など、あまりまとまった時間が取れない方にもおすすめです。
一方で、独学では問題や解答への理解が不十分になりやすいこと、自己管理が求められることは注意点といえます。
-
予備校や通信講座を活用する
予備校に通う、通信講座で自宅から授業を受ける方法もあります。
カリキュラムに沿って、行政書士試験対策を効率的に進められるのが魅力です。分からないことがあっても教えてくれる先生がいるので、安心して取り組めます。
一方で、予備校にも通信講座にも一定の費用がかかるのと、まとまった時間が必要になるのはデメリットといえるでしょう。
-
大学の講座を活用する
一部の大学の学部では、行政書士試験対策ができる授業や課外講座を設置している場合があります。立正大学 法学部もその一つです。
大学の講座を活用するメリットは、通い慣れた大学で、普段の授業や研究と並行しながら勉強できること。講座の先生はもちろん行政書士試験に精通しているので、分からないことを質問すれば、分かるまで丁寧に教えてもらえます。
特に、これから大学への進学を考えている学生さんは、行政書士試験の対策ができるかどうかも考慮して大学を選んでみてはいかがでしょうか。
まとめ
行政書士の仕事内容から年収、資格の取り方、国家試験の概要まで詳しく解説しました。
国家試験は難関ではあるものの、ほかの士業系国家資格と比べると合格率は高めで、士業の中でも比較的目指しやすいお仕事といえるでしょう。
立正大学では、法学部主催の資格取得講座として、行政書士の国家試験合格をバックアップする講座を用意しています。
キャリア形成支援が充実しており、法学部生の中には在学中に行政書士国家試験に合格する方もいらっしゃいます。
行政書士に興味がある方は、ぜひ、立正大学 法学部についてホームページをご覧ください。

「行政書士を目指すなら」 立正大学 法学部へ
立正大学法学部の特長は、徹底した少人数教育、大学内にとどまらないフィールドワーク、経験豊かな実務家による教育とともに、現代社会の諸問題に即応した科目の充実にあります。また、法学部独自に多彩な課外講座が展開されてもいます。立正大学法学部は、正課および課外での教育により、学生の希望進路の実現を後押しするだけでなく、リーガルマインド(法的思考力)を身につけた一人の社会人として社会や地域に貢献できる人材の育成に尽力しています。
法学部Webサイトへ 資格受験対策講座ページ