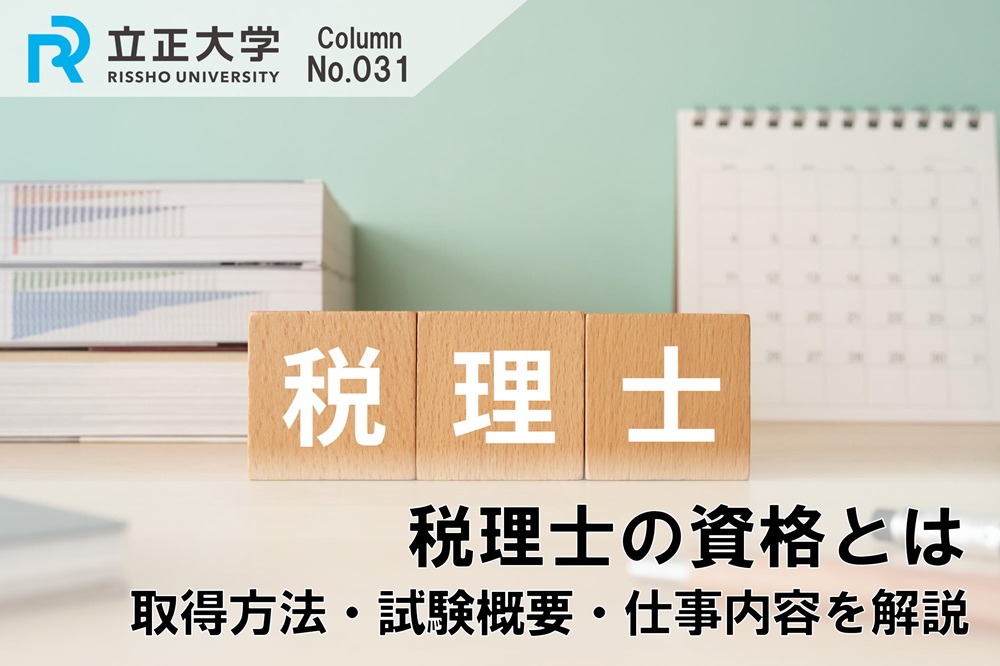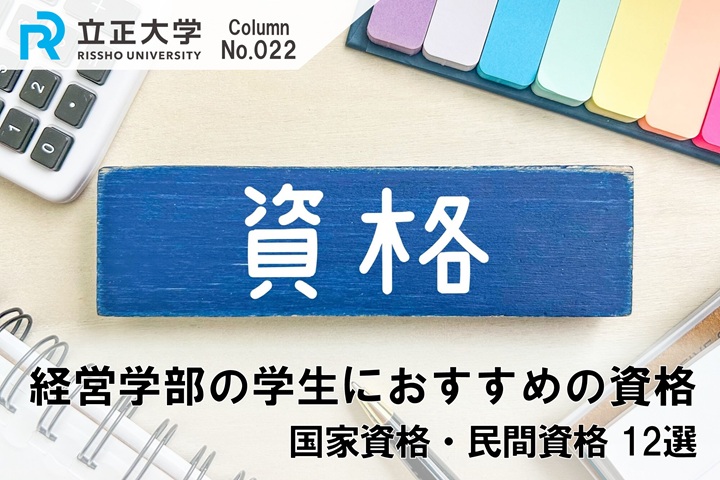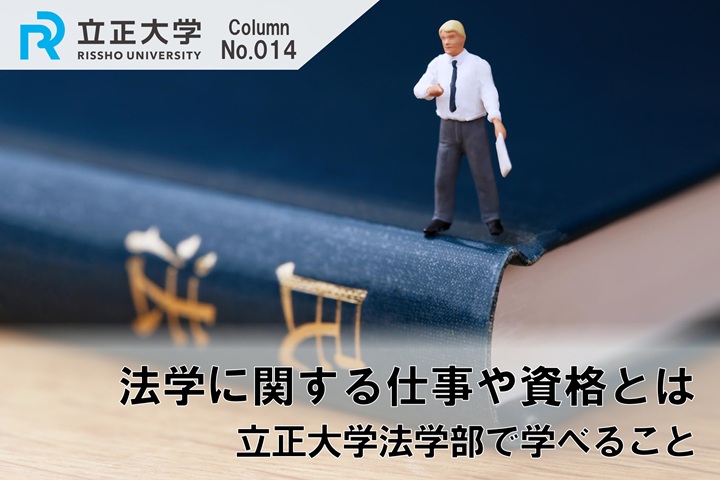税理士の資格とは 取得方法・試験概要・仕事内容を解説
税理士の資格を取るには?
初めに、税理士の資格を取る主な方法を2つ紹介します。
-
税理士試験合格+実務経験
税理士試験合格+実務経験は、税理士の資格を取得するもっとも一般的な方法です。税理士試験に合格し、2年以上の実務経験を積むことで、税理士の資格を得られます。
なお実務経験については、税理士事務所や一般企業などで「租税または会計に関する事務」に従事した経験が求められます。
この実務経験の要件は、試験合格前・後を問いません。試験合格時にすでに実務経験が2年以上あれば、試験合格後すぐに税理士として登録できます。
ちなみに、税理士試験には試験免除の制度が設けられており、場合によっては税理士試験の一部科目が免除される方もいます。こちらについては、後ほど詳しく解説します。
-
弁護士資格または公認会計士資格の所持
弁護士または公認会計士の資格を所持していれば、試験合格や実務経験なしで税理士資格を取得できます。
ただし、平成29年4月1日以降の公認会計士試験合格者については、財務省令で定められている税法に関する研修を修了しなければ、税理士登録ができないため注意しましょう。
また弁護士も公認会計士も、税理士として活動する場合には、まず日本税理士会連合会に申請し、税理士登録をする必要がある点には注意してください。
税理士試験の仕組み
税理士の資格保持者の多くは、税理士試験に合格して資格を取得しています。
税理士試験は、単一の試験ではありません。複数の科目から構成されており、「何を受けるか」を自分で選択する必要があります。
そこで、ここでは税理士試験の特徴をいくつかピックアップし、その仕組みを分かりやすく解説します。
-
全部で11の科目がある
税理士試験は、以下の科目で構成されています。全部で11の科目の中から、5つに合格すれば税理士試験合格となります。
会計科目 簿記論 財務諸表論 税法科目 所得税法 法人税法 相続税法 消費税法 酒税法 国税徴収法 住民税 事業税 固定資産税
このうち、会計科目に属する「簿記論」と「財務諸表論」は、必ず受験しなくてはいけません。
一方で税法科目については、まず「所得税法」または「法人税法」のいずれかを受験することが必須です。なお、どちらも受験しても問題ありません。
加えて、税法科目のほか7科目から、2科目または1科目を選択します。「所得税法」と「法人税法」の両方を受験する場合は1科目になります。
注意点として、「消費税法」と「酒税法」、「住民税」と「事業税」については、それぞれいずれか1科目しか選択できません。
例えば「消費税法」と「住民税」の組み合わせなら受験できますが、「消費税法」と「酒税法」をどちらも受験するということはできないので、覚えておきましょう。
-
受験する科目は自分で決める
前の項目でも説明しましたが、受験する科目は一部自分で決める必要があります。
「所得税法」と「法人税法」のどちらを選択するか、またはどちらも受験するのか、ほかの7科目からどの科目を受験するか、受験者次第で決められます。
受験科目を自分で選択する方式は、数ある試験の中でも比較的珍しいといえるでしょう。
自分が特に興味のある分野や、得意な分野に絞って学習を進められる点は、受験者にとってうれしいポイントかもしれません。
-
科目合格制で、一度合格した科目は生涯有効
全11科目から5科目を受験する税理士試験ですが、5科目すべてを一度に受験・合格する必要はありません。
税理士試験は科目合格制をとっており、例えば1回の試験で1科目のみ受験するということも認められています。
そして、一度合格した科目は生涯有効です。合格が取り消されることはないので、安心してまだ合格していない科目の試験対策に注力できます。
このことから、税理士試験はほとんどの方が数年をかけて受験・合格しています。
【令和5年度試験から緩和】税理士試験の受験資格
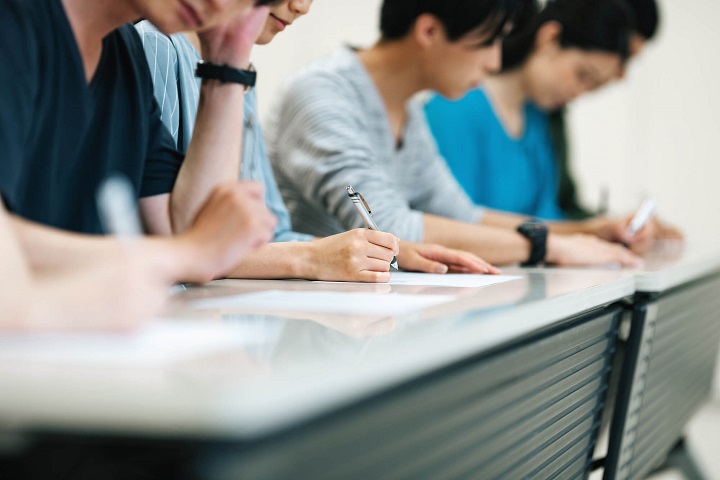
税理士試験は、前述した「会計科目」と「税法科目」で受験資格が異なります。
ここでは、それぞれの受験資格を解説します。なお、令和4年の税理士法改正により、令和5年度試験から受験資格が一部緩和されたので、そちらも併せて見ていきましょう。
-
会計科目の受験資格
会計科目の「簿記論」と「財務諸表論」には、受験資格がありません。学歴や資格を問わず、誰でも受験できます。
令和4年度試験までは、学歴や資格などで一定の受験資格が求められていました。
しかし、受験ファーストタッチの早期化が図られ、令和4年に税理士法が改正。令和5年度試験以降、受験資格が撤廃されたのです。
-
税法科目の受験資格
9つの科目が属する税法科目は、大きく分けて4つの受験資格の分類があります。
数多くの要件がありますが、どれか一つを満たせば問題ありません。ここからは、各要件の解説に加えて、クリアするのが比較的容易な要件についても触れていきます。
-
学識
学識に該当する受験資格は、以下のとおりです。
- 大学、短大または高等専門学校を卒業していて、社会科学に属する科目を1科目以上履修した者
- 大学3年次以上の学生で、社会科学に属する科目を含め62単位以上を取得した者
- 専修学校の専門課程(修業年限が2年以上かつ、課程の修了に必要な総授業時数が1,700時間以上)を修了していて、社会科学に属する科目を1科目以上履修した者
- 司法試験に合格した者
- 旧司法試験法の規定による司法試験の第二次試験または、旧司法試験の第二次試験に合格した者
- 公認会計士試験短答式試験合格者(平成18年度以降の合格者のみ)
- 公認会計士試験短答式試験全科目免除者
大学や短大への進学を予定している方や、在学中の方は、上から1つ目または2つ目をクリアするのが容易な受験資格でしょう。
「社会科学に属する科目」とは、法学や政治学、商学、経済学などに関する科目のことです。
1科目でも履修していれば大学卒業後に、大学3年生の方でも、社会科学に属する科目を含め62単位以上を取得していれば、受験資格を得られます。
かつては、「社会科学に属する科目」ではなく「法律学または経済学に属する科目」が要件でした。
しかし、「税理士には広く社会に関する基礎的素養が必要」との考えから、令和4年の税理士法改正で対象範囲が拡充され、令和5年度試験から反映されています。
-
資格
資格に該当する受験資格は、以下のとおりです。
- 日本商工会議所主催「簿記検定試験1級」合格者
- 公益社団法人 全国経理教育協会主催「簿記能力検定試験上級」合格者(昭和58年度以降の合格者のみ)
- 会計士補
- 会計士補となる資格を有する者
簿記検定試験1級は「日商簿記1級」、簿記能力検定試験上級は「全経簿記上級」という名称も一般的に使われています。
いずれかの試験に合格していれば、大学2年生以下で学識や職歴の要件を満たせない方も、税法科目の受験資格を得られます。
会計士補とは、平成18年に廃止された会計士補制度に基づく資格で、新しく取得することはできません。しかし、会計士補の資格自体は制度廃止後も有効であり、会計士補の資格を有する方は受験資格を得られます。
-
職歴
職歴に該当する受験資格は、以下の事務または業務に通算2年以上従事した方が得られます。
- 弁理士・司法書士・行政書士・社会保険労務士・不動産鑑定士の業務
- 法人または事業を営む個人の会計に関する事務
- 税理士・弁護士・公認会計士などの業務の補助の事務
- 税務官公署における事務または、そのほかの官公署における国税、もしくは地方税に関する事務
- 行政機関における会計検査などに関する事務
- 銀行などにおける貸し付けなどに関する事務
すでに会計や税務に関する業務に従事している場合、以上の条件を満たしている方も多いでしょう。
-
認定
国税審議会より、受験資格に関して個別認定を受けた方が、こちらのケースに該当します。
これまで個別認定を受けた方の例としては、- 外国の大学を卒業しており、社会科学に属する科目を1科目以上履修した方
- 商工会や青色申告会における複式簿記による記帳(経理)および、決算指導の事務に、通算2年以上従事していた方
などが挙げられます。
個別認定を受けたい場合、受験申込期間前に国税審議会宛てに申請を行い、あらかじめ認定を受けておく必要があります。
出典:受験資格について 問17 国税審議会が受験資格に関して個別認定したものとは、具体的にどのようなものがありますか。国税庁
税理士試験について
ここで、税理士試験について、スケジュールや出題形式、費用を確認しておきましょう。
-
スケジュール
税理士試験は、年1回、8月上旬に日本各地の試験場で実施されます。
受験するには所定の期間内に申込手続きを行うことが必要です。申込用紙は各国税局や国税事務所にて交付してもらえるほか、郵送での請求やe-Taxでの受験申込も可能なので、申請しやすい方法を選びましょう。
なお、申込受付期間は4月下旬から5月上旬ごろまでです。期間を過ぎると申込を受け付けてもらえなくなってしまうので、早めに準備に取りかかりましょう。
申請後は、6月下旬から7月上旬までに、受験票が届きます。
合格発表は11月下旬から12月中旬です。合格科目が5科目に達した方には合格証書が郵送されると同時に、合格発表予定日に受験地・受験番号が官報および国税庁ホームページに掲載されます。
一部の科目に合格した方、また合格科目のなかった方については、税理士試験結果通知書が郵送されます。
合格科目のある方は、合格発表予定日に受験地・受験番号が国税庁ホームページに掲載されるので、結果通知書が届く前に確認することが可能です。
受験票は、税理士試験が終わっても大切に保管しておきましょう。
-
出題形式
出題形式は、一部が択一式で出題されることもあるものの、基本的には記述式です。
計算問題と理論問題で構成されており、計算問題では例えば簿記の計算や財務諸表の作成、税金の計算などが求められます。一方で理論問題では、会計や税法の理論に関する問いへの解答が求められます。
合格基準点は各科目60点です。ただし、詳しくは後述しますが、税理士試験には相対評価が用いられていると考えているため、合格基準点以上の得点を目指したいところです。
-
費用
税理士試験の受験には、受験申込手数料がかかります。
1科目のみ受ける場合は4,000円、それ以降は科目数が1つ増えるごとに1,500円がプラスされていく仕組みです。
なお、支払いには郵便局や法務局、コンビニなどで入手できる収入印紙を使用するので、覚えておきましょう。受験申込科目数 1科目 2科目 3科目 4科目 5科目 受験手数料 4,000 円 5,500 円 7,000 円 8,500 円 10,000 円
税理士試験の科目免除について
税理士試験には免除制度が設けられており、学位や職歴によって科目の一部が免除される可能性があります。
なお、科目免除を受けた上で残りの科目の試験を受けること、ほかの科目に合格した上で最後の1科目の科目免除を受けることはどちらも可能であり、科目免除と試験の前後は問われません。
科目免除をしたことで合格科目数が5科目に達する場合は、随時、国税審議会会長宛てに必要書類を提出することで、税理士資格を取得できるようになります。
-
学位
学位とは大学や大学院を卒業した方に与えられる称号のようなものです。
修士または博士の学位を持っている方で、「法律学」または「財政学」に属する科目に関する研究で学位を得た方は税法科目が、「商学」に属する科目に関する研究で学位を得た方は会計科目が免除されます。
ただし、平成13年に成立した改正税理士法により、学位の種類や進学した年によって科目免除の内容が大きく異なるようになりました。
-
平成14年3月31日以前に大学院の修士課程に進学した方、または博士の学位取得者
平成14年3月31日以前に大学院の修士課程に進学した方、博士の学位取得者については、
- 「法律学」または「財政学」に属する科目に関する研究で学位を得た場合 → 税法科目免除
- 「商学」に属する科目に関する研究で学位を得た場合 → 会計科目免除
となります。
博士の学位取得者については、進学時期などは関係なく、科目免除を受けられます。
-
平成14年4月1日以降に大学院の修士課程に進学した方
平成14年4月1日以降に大学院の修士課程に進学した方については、税理士法改正以前と比べて大きく不利になったと言わざるを得ません。
簡潔にまとめると、科目免除を受けたい科目のいずれかの1科目を合格していなければ、学位(修士)による科目免除を受けられなくなりました。
- 「法律学」または「財政学」に属する科目に関する研究で学位を得た場合 → 税法科目のいずれか1科目に合格した上で申請すると、残りの税法科目免除
- 「商学」に属する科目に関する研究で学位を得た場合 → 会計科目の「簿記論」または「財務諸表論」いずれかに合格した上で申請すると、残りの会計科目免除
となります。
- 学識
- 公認会計士試験合格者
- 公認会計士試験論文式試験(会計学)合格者
ただし、公認会計士は試験に合格してからすぐに資格を取得することができず、実務補習や修了考査、業務補助などを経なければなりません。
公認会計士試験、または論文式試験(会計学)に合格していれば、科目の一部免除を受けられます。
- 資格
- 会計士補
- 会計士補となる資格を有する者
上記の資格がある方は、科目の一部免除を受けられます。
-
職歴
大学の教授や税務経験がある方は、科目の一部免除を受けられる可能性があります。
特に国税従事者については、- 10年または15年以上税務署に勤務した → 税法科目免除
- 23年または28年以上税務署に勤務し、指定研修を修了した国税従事者 → 会計科目免除
以上の科目免除規定があります。
税理士試験は難しい?

税理士試験は、受験する科目を一部自ら選択できる上に科目合格制をとっており、一見取得しやすい資格にも思えます。
実際に、税理士試験は難しいのでしょうか?
ここでは、税理士試験の合格率や難易度、必要な勉強時間、5科目を一発合格できるかどうかを解説します。
-
税理士試験の合格率
過去5年間の税理士試験の合格率を、受験者数と合格者数とともにご紹介します。
なお、合格者数と合格率は、合格科目が5科目に達した方と、一部科目に合格した方を含みます。
年 受験者数 合格者数 合格率 令和2年度(2020年) 26,673人 5,402人 20.3% 令和3年度(2021年) 27,299人 5,139人 18.8% 令和4年度(2022年) 28,853人 5,626人 19.5% 令和5年度(2023年) 32,893人 7,125人 21.7% 令和6年度(2024年) 34,757人 5,762人 16.6%
合格率は、10%後半から20%前半を前後していることが分かります。5人に1人が受かるかどうかといったところなので、「税理士試験の難易度は高い」といえるでしょう。
この難易度の高さは、試験全体の専門性の高さや記述式の出題形式はもちろん、大きな要因として「相対評価の試験であること」も影響していると考えられています。
「相対評価」とは、受験者全体の成績によって合格ラインが変わることです。明確な合格点が定められている「絶対評価」と、対照的な評価方法になります。
上記で、合格ラインは各科目で60点以上とお伝えしました。しかし、例年の合格率の推移から、一般的に「税理士試験には相対評価が用いられている」と考えられているのです。
したがって、税理士試験対策においては「60点取ればいい」と考えるのではなく、満点合格を狙うつもりで、入念に勉強を進める必要があります。
-
5科目合格に必要な勉強時間
税理士試験合格に必要な勉強時間は、科目によって異なります。
各科目の勉強時間を紹介しますが、実際には受験者それぞれの状況に応じて上下するでしょう。あくまで目安として、参考にしてください。
簿記論 400~500時間 財務諸表論 400~500時間 所得税法 600~700時間 法人税法 600~700時間 相続税法 400~500時間 消費税法 300~400時間 酒税法 100~150時間 国税徴収法 100~150時間 住民税 200~250時間 事業税 200~250時間 固定資産税 250~300時間
5科目合計で、2,000時間以上の勉強時間がかかることが一般的です。毎日2時間ずつ勉強すると考えても、3年程度かかる計算になります。
年に1回の試験で受験する科目に必ず合格できるよう、年単位のスケジュールを立てて勉強を進めていきましょう。
-
税理士試験を一発合格するのは難しい?
税理士試験は数年かけて合格を目指す方がほとんどだと説明しました。では、一発合格、すなわち1回の試験で5科目すべてを合格することは難しいのでしょうか。
税理士試験を一発で合格することは、ほぼ不可能といわれています。実際に、現行の税理士試験が始まってからこれまで、5科目を同時に合格した方は数えるほどしかいないとされているのです。
税理士試験は、一部科目合格の方を含めても、合格率が10%後半~20%前半と難易度の高い資格。一度にすべて合格しようとして、それぞれの科目の勉強が中途半端になっては元も子もありません。
科目合格制をうまく活用して、少しずつ合格科目数を増やしていきましょう。
税理士の年収
厚生労働省の「令和6年賃金構造基本統計調査」によると、税理士の平均年収は856.3万円です。一方で、給与所得者全体の平均年収は、国税庁の「令和5年分 民間給与実態統計調査」によると460万円とのことでした。
税理士の平均年収は、給与所得者全体の平均年収を大きく上回っていることが分かります。
税理士は、自分の実力によって給与を上げやすい職業です。大手税理士法人への就職や独立開業をすれば、年収1,000万円以上も狙えるでしょう。
税理士の資格取得までだけではなく、資格取得後も税務の知識を深め、実務経験を着実に積んでいくことが大切です。
出典:令和6年賃金構造基本統計調査 結果の概況厚生労働省
出典:令和5年分 民間給与実態統計調査国税庁
税理士の仕事内容
税理士は、一言でいうと税の専門家です。活躍の場は非常に広く、個人の確定申告の代理から企業の会計業務まで、税務や会計のスペシャリストとして大きな役割を担っています。
税理士の仕事内容として、まず理解しておきたいのが独占業務です。
税理士には「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」という3つの独占業務があり、この業務は税理士の資格を所持していないと業務に携わることはできません。
「税務代理」とは、確定申告や青色申告の承認申請、税務調査の立ち会いのこと。「税務書類の作成」とは確定申告書や相続税申告書などの書類作成のことです。そして「税務相談」は、税に関する相談にアドバイスすることを指します。
税金は非常に複雑で、自分一人で手続きをすべて済ませようとすると、間違ってしまうことも少なくありません。税理士は、確実な納税や税に関する手続きを支える、なくてはならない存在なのです。
また、税金だけでなく、財務書類の作成や会計帳簿の記帳代行といった会計に携わることも多く、「お金」の面から個人から企業までさまざまなお客さまを支えています。
まとめ
税理士の資格を取得するまでの過程や、税理士の年収や仕事内容を解説してきました。
資格取得までの道のりは長いものとなりますが、この記事を参考に、税理士への第一歩を踏み出していただけたら幸いです。
税理士を目指す学生さんは、立正大学への進学もぜひご検討ください。
立正大学の法学部と経営学部では、それぞれ税理士の資格取得講座を開講しており、税理士を目指す皆さんの背中を後押ししています。
法学部・経営学部は、それぞれカリキュラムの内容や進路に違いがあるので、詳しくはぜひ以下からホームページをご覧ください。