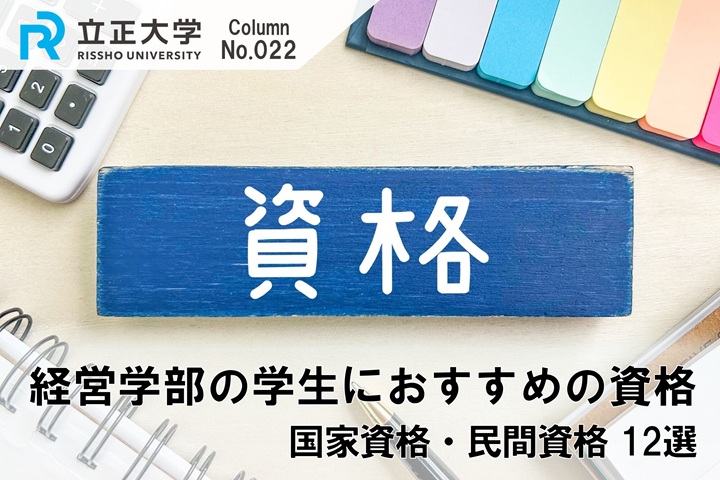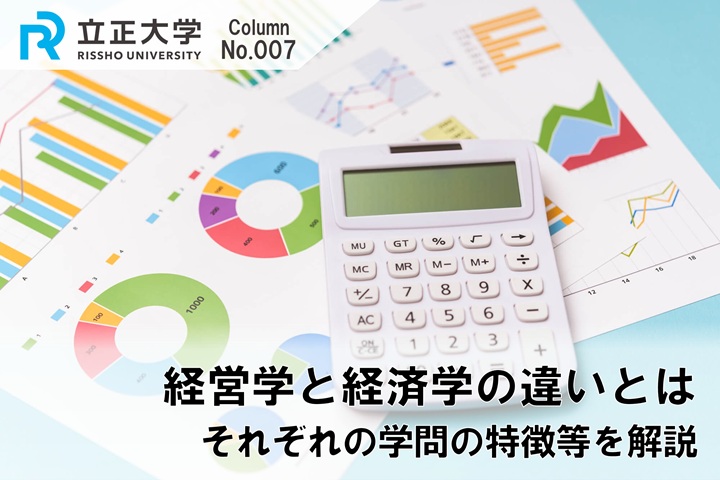経営コンサルタントとは 仕事内容や取得推奨資格について解説

企業の経営課題を解決するために、アドバイスや支援を行う経営コンサルタント。企業のDX推進や少子高齢化によるM&A増加などの背景から、需要が高まり続けている職業です。
「経営コンサルタントに憧れるけど、必要な資格はあるのかな?」「経営コンサルタントの仕事内容を詳しく知りたい!」という方も多いかもしれません。
そこで、今回は経営コンサルタントについて、仕事内容からおすすめ資格10選、さらに経営コンサルタントを目指す方におすすめの大学の学部まで、詳しく解説します。
経営コンサルタントとは
経営コンサルタントは、企業が直面するさまざまな経営課題について、その解決をサポートし、企業の持続的な成長を支援する専門家です。
主な仕事内容を順序に沿ってまとめると、以下のようになります。
- 企業から依頼を受注
- クライアント企業の経営状況や市場を分析し、課題を特定
- 経営戦略の策定や新規事業の立案、組織・人事制度の改革、業務プロセスの改善など、最適な解決策を提案
- 単なる助言だけでなく、提案した戦略や施策が現場で確実に機能するかどうか、成果が出るまで伴走支援
このように、依頼を受けると、経営課題の特定から成果が出るまで、包括的に支援を行うのが経営コンサルタントの役割です。
経営コンサルタントが提案した解決策は、企業の業績や将来、ひいてはその企業で働く従業員の生活にも直接影響を与えます。企業をよりよい方向に導くことで、産業全体の競争力強化や経済の発展にも貢献する、社会的意義が非常に大きい仕事です。
経営コンサルタントとして働くには、コンサルティング会社への就職が第一に挙げられます。ある程度実績を積んだ後は、独立開業するという道もキャリアアップの一つです。
ちなみに、コンサルティング会社とひとくくりにいっても、その種類はさまざまです。
- 戦略系コンサルティング会社…経営戦略や新規事業戦略、M&A戦略などを主に扱う。グローバルに展開する外資系企業が多い。
- 総合系コンサルティング会社…経営戦略や業務改善、システム導入、アウトソーシングなどのサービスを幅広く扱う。
- IT系コンサルティング会社…ITを活用した経営戦略や業務改革を扱う。
- 業界特化系コンサルティング会社…特定の業界や業務に特化し、専門性を生かしたコンサルティングを行う。
以上は一例です。会社によって業務内容や必要なスキルが異なるため、経営コンサルタントを目指すなら「どの分野で、どのように活躍したいか」を考えてみましょう。
経営コンサルタントの年収
経営コンサルタントの年収は、厚生労働省の「令和6年賃金構造基本統計調査」によると、903.2万円です。一方で、給与所得者全体の平均年収は、国税庁の「令和5年分 民間給与実態統計調査」によると460万円。
経営コンサルタントの年収は、給与所得者全体の平均年収の2倍近い数値であることが分かります。
この年収の高さは、専門性が強く求められる仕事内容であることや、業務が企業全体に与える影響が大きいことが要因です。「経営コンサルタントとは」で説明したように、クライアント企業の将来に関わる業務であるため、大きな責任が伴う一方、報酬もそれに見合う多さになっているのです。
経営コンサルタントとして年収アップを目指すなら、外資系や大手コンサルティング会社の正社員として勤めるか、ある程度実績を積んだ後に独立開業する道が挙げられます。この場合、年収は平均の数値を上回り、年収1,000万円以上を狙うことも十分可能でしょう。
出典:令和6年賃金構造基本統計調査 結果の概況厚生労働省
出典:令和5年分 民間給与実態統計調査国税庁
経営コンサルタントに資格は必要か?
結論からいうと、経営コンサルタントに絶対に必要な資格はありません。そのため、無資格でも「経営コンサルタント」を名乗ってコンサルティングを行うことは可能です。
ただし、実際には経営コンサルタントに関する資格を持っていると、就職活動や営業活動の際に有利になるのは間違いありません。
特に、経営コンサルタントとして独立開業するのであれば、資格の有無が依頼や契約に直結するでしょう。また、コンサルティング会社に就職した場合も、資格があったほうが取引先やクライアントから信頼されやすいです。
そのため、経営コンサルタントに資格は必須ではありませんが、「資格は持っておいたほうがいい」といえるのです。
経営コンサルタントにおすすめの資格10選

ここからは、経営コンサルタントにおすすめの資格を10個紹介します。
おすすめ度、取得難易度も記載するので、ぜひ参考にしてください。
-
中小企業診断士
おすすめ度:★★★(非常におすすめ)
取得難易度:★★☆(難しい)
中小企業診断士は、「日本唯一の経営コンサルタントの国家資格」といわれる資格です。企業の経営課題を分析し、成長戦略を策定・実行支援するための幅広い知識を有することを証明できます。
中小企業診断士の資格取得においては、コンサルティングに必要な知識を体系的に習得できます。特に中小企業支援の分野で信頼が厚く、就職やキャリアアップに有利になるのはもちろん、公的機関の仕事にも携わりやすくなるでしょう。
資格取得には、1次試験(筆記)と2次試験(筆記・口述)に合格し、さらに実務補習または実務従事を行う必要があります。難易度は高いですが、取得すればキャリアの強力な武器となります。
受験資格は特に定められておらず、年齢や学歴などに関係なく誰もが受けられることもあり、ぜひ取得を目指してほしい資格です。
中小企業診断士については以下のコラムで詳しく解説しておりますので、興味のある方はぜひ読んでみてください。

中小企業診断士の資格とは 取得方法・試験概要等を解説
記事はこちら出典:中小企業診断士制度一般社団法人 日本中小企業診断士協会連合会
-
公認会計士
おすすめ度:★★☆(おすすめ)
取得難易度:★★★(最難関クラス)
公認会計士は、企業会計や監査の最高峰の国家資格です。企業の財務情報の信頼性を担保する「監査業務」は、公認会計士の独占業務となっています。
公認会計士の高度な会計知識と財務分析能力は、企業の経営状況を数値面から深く理解し、財務改善や企業再生、さらにはM&Aといったハイレベルな会計・財務コンサルティングを行う上で、非常に役立ちます。
資格取得には、短答式と論文式で構成される国家試験に合格した後、3年以上の業務補助と実務補修を経て、最終的に修了考査に合格することが必要です。
出典:公認会計士とは日本公認会計士協会
-
税理士
おすすめ度:★★☆(おすすめ)
取得難易度:★★★(最難関クラス)
税理士は、税務に関する国家資格です。税務申告の代理・税務書類の作成・税務相談の3つは、税理士の独占業務となっています。
企業経営において、税務はコストやキャッシュフローに直結します。そのため、税理士の専門知識は、コンサルティングにおいて大きな強みとなるでしょう。さらに、節税対策や事業承継などの分野でも、法律を順守した経営判断をサポートできます。
資格取得には、税理士試験において全11科目から5科目に合格することに加え、租税または会計に関する2年以上の実務経験が必要です。一度合格した科目は生涯有効なので、数年をかけて合格を目指すケースがほとんどです。
税理士については以下のコラムで詳しく解説しておりますので、興味のある方はぜひ読んでみてください。
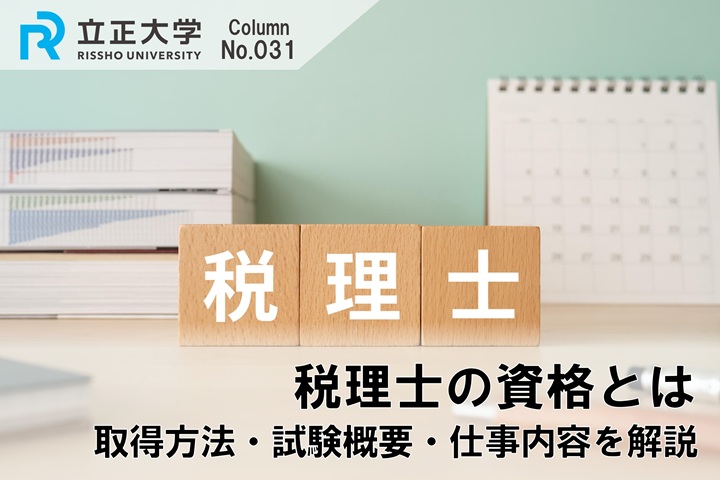
税理士の資格とは 取得方法・試験概要等を解説
記事はこちら出典:税理士を目指す日本税理士会連合会
-
社会保険労務士
おすすめ度:★★☆(おすすめ)
取得難易度:★★☆(非常に難しい)
社会保険労務士(社労士)は、労働保険・社会保険諸法令、人事労務管理についての専門家で、国家資格です。労働社会保険諸法令に基づく手続代行業務や帳簿作成業務は独占業務となります。
現代の経営課題の多くは、「人材」と「組織」に関わるものです。そして、社会保険労務士の知識は、人事や組織に関するコンサルティングの専門性を高めます。採用や人材育成、賃金制度、働き方改革といった分野で、法律を順守した上で戦略的なアドバイスが可能になります。
資格取得には、社会保険労務士試験の合格に加え、2年以上の実務経験もしくは事務指定講習の修了が必要です。
社会保険労務士については以下のコラムで詳しく解説しておりますので、興味のある方はぜひ読んでみてください。
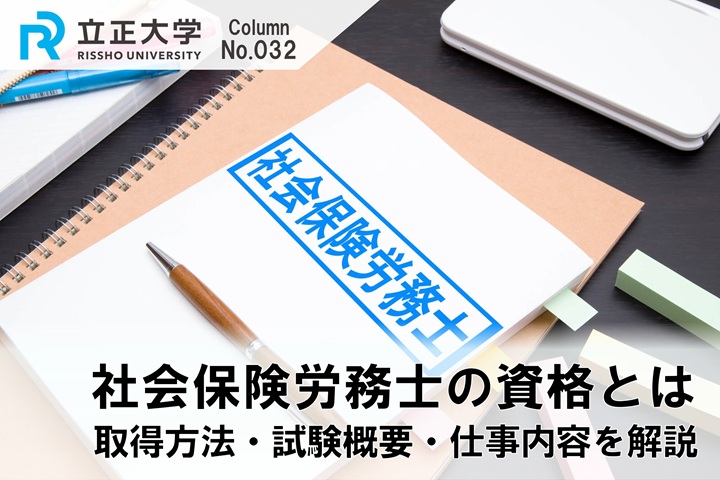
社会保険労務士の資格とは 取得方法・試験概要等を解説
記事はこちら出典:社労士を目指す全国社会保険労務士連合会
-
経営士
おすすめ度:★★☆(おすすめ)
取得難易度:★☆☆(取得までに段階的なステップを踏める)
経営士は、特定非営利活動法人 日本経営士協会が認定する、日本でもっとも歴史のある民間の経営コンサルタント資格です。
「経営士」はA・B・Cの3つのクラスに分かれ、さらに「経営士補」という資格もあります。「経営士」は、コンサルタントとして開業できる実力を有することを証明でき、「経営士補」は経営士の補助的な業務を行えることを証明できます。
資格を取得するには、- 「一般会員」として日本経営士協会に入会
- 協会が実施する研修会・講習会を受講
- 「経営士」「経営士補」を持つ「資格会員」昇格のために必要な単位を取得
- 昇格審査を受け、合格
という流れが一般的です。
出典:日本経営士協会の資格制度特定非営利活動法人 日本経営士協会
-
行政書士
おすすめ度:★☆☆(取得を検討したい)
取得難易度:★★☆(難しい)
行政書士は、「街の法律家」とも呼ばれる、幅広い行政手続きを行う専門家で、国家資格です。「官公署に提出する書類」「権利義務に関する書類」「事実証明に関する書類」の作成は独占業務となります。
企業が新規事業を立ち上げたり、事業規模を拡大したりする際には、必ず官公署への許認可申請や届出が必要となります。そのため、行政書士の知識と資格は、特に事業立ち上げや事業拡大に関するコンサルティングをスムーズに行うのに役立つでしょう。
行政書士単体よりも、ほかの資格と組み合わせるのがおすすめです。年1回行われる国家試験に合格すれば、資格を取得できます。
行政書士については以下のコラムで詳しく解説しておりますので、興味のある方はぜひ読んでみてください。
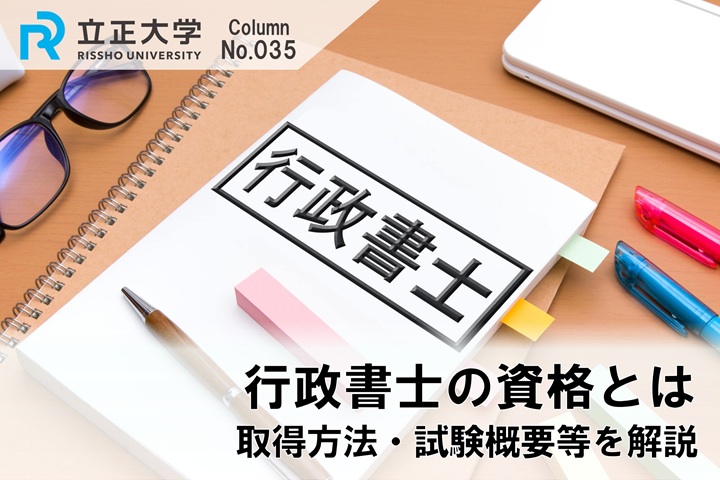
行政書士の資格とは 取得方法・試験概要等を解説
記事はこちら出典:行政書士とは日本行政書士会連合会
-
司法書士
おすすめ度:★☆☆(取得を検討したい)
取得難易度:★★☆(難しい)
司法書士は登記の専門家で、国家資格です。登記や供託に関する手続きの代理や、法務局に提出する書類の作成などが独占業務となっています。
企業経営において、会社設立や事業承継の際には、必ず登記業務が発生します。そのため、司法書士の知識や資格は、事業立ち上げや承継に関するコンサルティングでは大きな強みになるでしょう。
行政書士同様、ほかの資格と組み合わせるのがおすすめの資格です。資格取得には、年1回行われる国家試験に合格後、所定の研修を受ける必要があります。
出典:司法書士を目指す人へ日本司法書士会連合会
-
キャリアコンサルタント
おすすめ度:★☆☆(取得を検討したい)
取得難易度:★☆☆(比較的難易度が低い)
キャリアコンサルタントは、個人の職業選択や能力開発に関する相談に応じ、助言や指導を行う国家資格です。企業の人材開発、ひいては組織開発を支援する専門家でもあります。
企業の課題解決には、人事や組織の問題が深く関わっていることが多いです。そのため、この資格を持つことで、人材戦略・組織コンサルティングの専門性を強化できます。例えば、従業員の定着率向上やモチベーション管理、キャリアパスの設計などに対し、専門的な視点からアプローチが可能になります。
資格取得には、厚生労働大臣が認定する講習の修了もしくは3年以上の実務経験を経て、キャリアコンサルタント試験に合格する必要があります。
出典:キャリアコンサルタントになりたい方へ厚生労働省
-
ファイナンシャル・プランナー
おすすめ度:★☆☆(取得を検討したい)
取得難易度:★☆☆(比較的難易度が低い)
ファイナンシャル・プランナー(FP)は、個人や企業の資産運用や資金計画に関する幅広い知識を持つ専門家で、国家資格です。「家計のホームドクター」ともいわれます。
中小企業の資産管理や退職金制度などのコンサルティングを行う際、FPの知識は非常に役立ちます。また、経営者の個人資産と法人資産の両面から、最適な財務アドバイスを提供できることも強みといえるでしょう。
FP資格には1級・2級・3級があり、1級がもっともハイレベルです。経営コンサルタントとしてFP資格を活用したいのであれば、2級以上を取得するのが望ましいでしょう。
出典:FP資格取得を目指す特定非営利活動法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会
-
MBA
おすすめ度:★★★(非常におすすめ)
取得難易度:★☆☆(取得までに段階的なステップを踏める)
MBA(Master of Business Administration)は、経営学の大学院修士課程を修了することで授与される学位です。資格ではないものの、企業経営に必要なあらゆる専門知識を体系的かつ実践的に学んだことを証明できます。
MBAの取得過程で習得する経営のフレームワークや論理的思考力、問題解決能力は、経営コンサルタントとしての土台を強固にします。特に、戦略系や総合系のコンサルティング会社に就職したい場合、MBAは非常に高く評価されるでしょう。
経営コンサルタントにおすすめの学部

経営コンサルタントの仕事内容や、経営コンサルタントになるためにおすすめの資格を解説してきました。
経営コンサルタントを目指すなら、大学で経営に関する勉強をするのもおすすめです。特に「経営学部」または「経済学部」では、経営コンサルタントになるために非常に役立つ知識や技術を身につけられるでしょう。
ここからは、それぞれの学部で何を学べるのかを紹介します。
-
経営学部
経営学部は、その名のとおり経営コンサルタントを目指すのにぴったりの学部です。
経営コンサルタントには、企業の経営に関する幅広い知識が求められます。経営学部では、「企業をもっと成長させる」ことを念頭に置いて、例えば経営戦略やマーケティング、会計、情報システム学などを中心に学ぶことが多いです。
「企業の経営課題をどう解決するか」といった具体的な方策も学べるので、勉強したこと・研究したことが、経営コンサルタントとしての仕事に直接役立つことも少なくないでしょう。
また、一部の経営学部では、上記でご紹介した「経営コンサルタントにおすすめの資格」の取得を支援していることがあります。履修することで資格取得に役立つ知識を得られる場合もあれば、特定の資格取得に向けた課外講座を設置している場合も。
このような理由から、経営コンサルタントを目指すなら、第一に「経営学部」への進学を考えてみることをおすすめします。
-
経済学部
経済学部では、世の中の経済活動を多角的に研究できます。
「経営学部と経済学部の違いがよく分からない」と疑問に思う方もいるでしょう。両者のもっとも大きな違いは、「研究の対象」にあります。
経営学部が一つの企業の経営活動に焦点を当てる一方で、経済学部は個人・企業・国・世界と、さまざまな対象に焦点を当てるのが特徴です。そして、対象の経済活動の仕組みや変動要因、今後の展望などを分析していきます。
ただし、経済学部では経営について学べないというわけでは決してありません。経営学は経済学の一つと考えられており、経済学部でも経営についての知識を得たり、企業経営をテーマにして研究したりすることは可能です。
「より広い視野で経営を学びたい」「世の中の経済活動を理解した上で経営コンサルタントになりたい」という方は、経済学部への進学も選択肢に入れるとよいでしょう。
まとめ
経営コンサルタントを目指すなら、中小企業診断士や公認会計士などの国家資格のほか、経営士といった民間資格やMBAの学位を持っていることで、就職やキャリアアップに非常に役立ちます。
立正大学には、経営学部と経済学部のどちらも設置されています。
以下から、ぜひ経営学部・経済学部のホームページをご覧いただき、「自分に合っているのはどっちかな?」と考えてみてくださいね。

「経営学を学ぶなら」 立正大学 経営学部へ
経営学は実践的な学問であり、理論と実践の結びつきが大切です。ヒト、モノ、カネ、情報に合わせて4つの領域を学び、1年次はすべての領域を、そして2年次からはゼミナールで学びの「柱」を決めていきます。また企業や地域とのコラボレーションやアクティブ・ラーニング、グループワーク等を通じて、学んだことをリアルに実践する機会を豊富に用意しています。
立正大学経営学部Webサイトへ
「経済学を学ぶなら」 立正大学 経済学部へ
経済学は、社会をよりよくするために希少な資源をどう活用するかを考える学問です。基本的なコースワークに加え、近年重要なデータ分析科目、多彩な専門科目をとおして多様な視点から経済・社会を分析する力を修得します。
立正大学経済学部Webサイトへ