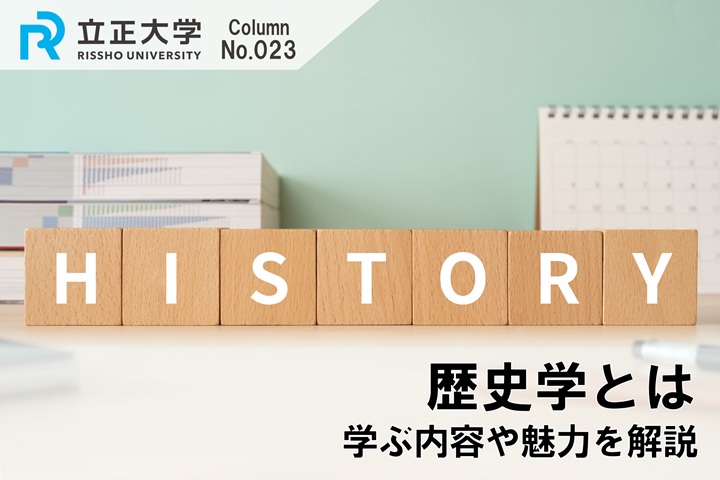博物館学芸員になるには 認定資格や仕事内容等を解説

学芸員は、博物館で働き、資料の収集や保管、展示、調査研究などを行う専門職員です。
学芸員になるには「c」の資格が必須で、大学で特定の科目を履修したり、学芸員資格認定の試験および審査に合格したりする必要があります。
今回は、学芸員の役割から博物館学芸員の資格取得の方法、学芸員資格認定まで、学芸員になるために必要な情報を詳しく解説します。
併せて、博物館学芸員課程のある立正大学についてもご紹介するので、学芸員を目指す方、学芸員に興味がある方は、ぜひ最後までご覧ください。
学芸員とは
学芸員とは、国家資格「博物館学芸員」を持っていて、博物館に勤務する方を指します。
初めに、学芸員の役割や仕事内容について解説します。
- 学芸員の役割
- 学芸員は、博物館で働きます。博物館といえば、歴史的な資料を管理・展示する施設を思い浮かべる方が多いと思いますが、それだけでなく、美術館や水族館、動物園、植物園も博物館の一つです。
博物館の名を持つ施設も、歴史博物館や郷土博物館、自然博物館など、施設によって扱う資料はさまざまです。一般的に、学芸員は自らが持つ専門知識を生かした分野の博物館で働いています。
学芸員は、就業先の博物館で、主に資料の収集や保管、展示、調査研究などを行います。これは、今まで積み重ねられてきた歴史を守り、伝えていくことにほかなりません。
博物館には、老若男女問わず多くの方が訪れます。博物館を訪れて、価値観が大きく変わる方も少なくありません。
学芸員の大きな役割は、資料を集め、適切に保管し、来館者に伝えることで、歴史を次世代につないでいくことにあるといえるでしょう。
- 学芸員は、博物館で働きます。博物館といえば、歴史的な資料を管理・展示する施設を思い浮かべる方が多いと思いますが、それだけでなく、美術館や水族館、動物園、植物園も博物館の一つです。
-
学芸員の仕事内容
学芸員の仕事内容は、非常に多岐にわたります。
まずは、資料の収集や保管です。「収集」には、文化財の発掘や動植物の収集など、野外での活動も含まれる場合があります。また、館内にない資料を購入したり、借り入れたりすることも少なくありません。
資料の保管も大切で、資料が劣化したりしてしまわないよう、適切な方法で保管する必要があります。この際、もし資料に破損などが見られた場合、修理を担うことも。
収集・保管した資料は、来館者が見られるように展示します。展示にあたっては、会場の設営はもちろん、展示のテーマや並べ方を考えたり、解説書やポスターを作成したりと、企画から広報活動まで行います。
開館時間中は、来館者を案内したり、展示について直接解説したりすることも多いです。
さらに、研究者的な役割も大きく、資料に関する調査や研究を行って、その結果を学術雑誌で発表することもあります。
出張講座やイベントなどで外部に出向する機会もありますし、予算の申請や管理、博物館スタッフの採用や教育など、直接資料とは関わらない仕事も多くあります。
学芸員になるには

学芸員になる方法は、大きく分けて3つあります。
-
大学で博物館に関する科目を履修する
大学で、博物館に関する科目を履修した上で卒業すると、博物館学芸員資格を取得できます。
博物館に関する科目は9科目19単位あり、以下のとおりです。
これらは、すべての大学で履修できるわけではありません。上表の科目がある「学芸員養成課程」が開講されている大学でのみ履修することができます。科目名 単位数 生涯学習概論 2 博物館概論 2 博物館経営論 2 博物館資料論 2 博物館資料保存論 2 博物館展示論 2 博物館教育論 2 博物館情報・メディア論 2 博物館実習 3
大学に通って博物館学芸員資格を取得したい方は、令和7年4月1日現在で、以下の大学のいずれかに通うことが必要です。
文化庁:学芸員養成課程開校大学・短期大学(部)一覧(令和7年4月1日現在)291大学
一緒に掲載されている短期大学については、このあとの項目で詳しく解説します。
なお、学芸員養成課程をすべて修めても、大学を卒業せず「学士」の学位を取得できなかった場合は、博物館学芸員資格を得ることはできないので注意してください。
立正大学は、学芸員養成課程がある大学の一つです。立正大学では「博物館学芸員課程」という名前で開講しています。
全学部・全学科の学生さんが対象なので、学芸員を目指す方は、ぜひ立正大学での学びも考えてみてくださいね。
立正大学 ホームページ -
短期大学で博物館に関する科目を履修し、実務経験を積む
短期大学にも、学芸員養成課程が開講されているところがあります。
ただし、短期大学で学芸員養成課程を履修した場合、「学芸員補」として、3年以上の実務経験を積まなければなりません。
学芸員補とは、学芸員補資格を所持している方のことで、博物館にて学芸員の補佐を行う方を指します。
この学芸員補は、従来「大学に入学できる方」すなわち高等学校などを卒業している方であれば、誰でもなることができました。
しかし、進学率の上昇や学芸員に求められる業務の多様化・高度化を受け、2022年4月に博物館法が改正されます。そして、2023年4月1日以降は、短期大学で学芸員養成課程を履修し、卒業した方しか「学芸員補」として働けないようになったのです。
学芸員として働けるのは博物館です。しかし学芸員補の場合、社会福祉主事や司書として、官公署や学校、社会教育施設で勤務した場合も、学芸員補としての実務経験に含まれることになります。
なお短期大学の場合も、卒業して「短期大学士」の学位を取得しなければ、学芸員補資格を得られないので注意してください。
-
文化庁の資格認定を受ける
文化庁の資格認定を受けて博物館学芸員資格を取得する場合、「試験認定」か「審査認定」を受けることになります。
試験認定は、「学芸員養成課程の修得に代わる学力を試験するもの」として位置づけられており、出題される8科目すべてで合格する必要があります。
一方で、審査認定は、「博物館における学識および業績を審査するもの」として位置づけられており、実施されるのは書類審査です。
詳しくは、次の項目で見ていきましょう。
学芸員資格認定について
学芸員資格認定、すなわち「試験認定」または「審査認定」は、大学や短期大学で学芸員養成課程を履修することなく、博物館学芸員資格を取得するチャンスがある点が魅力です。
ただし、それぞれに出願できる条件が定められており、大学をすでに卒業している方や、一定の実務経験がある方などが対象となります。
したがって、「まだ進学先の大学について考えている」という段階の高校生の学生さんなどには、基本的には大学で学芸員養成課程を履修することがおすすめです。
これを踏まえて、ここからは2種類の学芸員資格認定について、詳しく解説していきます。
なお、2024年度以降、試験認定と審査認定は2年に1回の実施となりますので、スケジュールについては十分注意してください。
-
試験認定
試験科目8科目の筆記試験に合格し、合格後1年間博物館での実務経験を積むことで、博物館学芸員資格を取得できます。
受験資格は、以下のとおりです。いずれかの要件を満たすことで、試験を受けられます。
- 大学院に入学できる(大学を卒業している方など)
- 大学に2年以上在学し、62単位以上を修得・博物館での実務経験が2年以上
- 大学に入学できる(高等学校を卒業した方など)・博物館での実務経験が4年以上
- 教育職員の普通免許状を有する・教育職員としての経験が2年以上
出題される8科目の内訳は、以下のとおりです。- 生涯学習概論
- 博物館概論
- 博物館経営論
- 博物館資料論
- 博物館資料保存論
- 博物館教育論
- 博物館情報・メディア論
- 博物館展示論
出願期間は、例年7月中旬以降から9月上旬まで。試験日は12月中で、翌年2月下旬に受験結果が送付されます。
2年に1回の実施に変更されているので、受験を考えている方は文化庁のホームページで最新情報をチェックしましょう。
出典:学芸員の資格認定について文化庁ホームページ
8科目すべてに合格することで、「筆記試験合格証書」が交付されます。そして、博物館で1年以上の実務経験を積むと、「合格証書」が交付され、晴れて博物館学芸員資格を取得できます。
-
審査認定
審査認定では、受験者が博物館学芸員資格を取得するのにふさわしい学力や実績があるかが問われます。
学力や実績として審査されるのは、博物館に関する著書や論文、報告、展示、講演、実務経験などです。
受験資格は、以下のとおりです。いずれかの要件を満たすことで、審査を受けられます。
- 「修士」「専門職」「博士」のいずれかの学位がある(大学院を卒業した方など)・博物館での実務経験が2年以上
- 大学で博物館に関する授業を2年以上教える・博物館での実務経験が2年以上
- 以下のいずれかに該当して、都道府県の教育機関に推薦される
- 大学を卒業して「学士」の学位を取る・博物館での実務経験が4年以上
- 大学に2年以上在学し、62単位以上を修得する・博物館での実務経験が6年以上
- 高校を卒業して大学に入れる学力がある・博物館での実務経験が8年以上
出願期間は、試験認定と同様に、例年7月中旬以降から9月上旬までです。12月上旬に書類審査が行われ、翌年の1月下旬に審査結果が送付されます。
審査認定も2年に1回の実施で、試験認定と交互に実施されています。受験を考えている方は、文化庁のホームページで最新情報を確認してください。
出典:学芸員の資格認定について文化庁ホームページ
審査認定では、試験認定と異なり合格後に実務経験を積む必要はありません。
合格すると、「合格証書」が交付され、博物館学芸員資格を取得できます。
博物館学芸員についてのよくある質問

ここでは、博物館学芸員について、よく寄せられる質問と回答を紹介します。
-
博物館学芸員資格を取得したらどうすればいい?
博物館学芸員資格を取得して、ただちに学芸員として博物館で働けるわけではありません。学芸員になるには、各地の博物館で採用選考を受ける必要があります。
なお、博物館には「登録博物館」「博物館相当施設」「博物館類似施設」と異なる種類の博物館があることに注意が必要です。
設置主体や職員の規定にそれぞれ違いがあり、大きな違いとして「登録博物館で学芸員として働くには、博物館学芸員資格が必須」ということがあります。
逆にいえば、博物館相当施設と博物館類似施設では、学芸員として働くにあたって必ずしも資格は必要ではありません。とはいえ、学芸員として専門的な知識が求められることに変わりはなく、博物館学芸員資格があることで就職に有利になるのは確実です。
博物館に学芸員として就職したい場合、インターネットなどから公募情報を確認しましょう。学芸員養成課程のある大学には、博物館側から公募情報が提供されることもあり、キャリアセンターに確認してみるのもおすすめです。
-
博物館以外にどんな就職先がある?
博物館学芸員資格は、任用資格です。すなわち、「博物館の学芸員になるために必要な資格」であり、一般企業への就職において有利にはなりづらいといえるでしょう。
博物館学芸員資格を生かして、学芸員として就職する場合、例えば以下の就職先があります。
- 歴史博物館
- 郷土博物館
- 自然博物館
- 科学博物館
- 美術館
- 郷土資料館
- 水族館
- 動物園
- 植物園
前項で紹介した「登録博物館」については、文化庁の博物館総合サイトから調べられるので、ぜひチェックしてみてください。
立正大学の博物館学芸員課程について
立正大学には、博物館学芸員課程があります。こちらは文化庁に「学芸員養成課程開講大学」として正式に認められたもので、立正大学の学生さんは所定の科目を履修することで、博物館学芸員の資格を取得できます。
なお、この講座は全学部・全学科を対象として開設されているので、履修にあたって学部や学科を気にする必要はありません。
博物館学芸員課程の中でも、「博物館実習」は、考古・古文書・美術・自然・情報の5分野で実施されています。現地で行う野外実習や博物館施設見学に加え、実際の博物館で5日間以上にわたって業務を実習する「実習博物館館務実習」もあり、充実した内容です。
まとめ
博物館学芸員の資格について、取得の方法や、学芸員の役割や仕事内容も含めて解説しました。
まだ進学前で、学芸員の道に進みたいと考えている学生さんには、学芸員養成課程がある大学に進学する方法がおすすめです。
立正大学には、博物館学芸員課程があります。学部・学科を問わず履修できる課程で、こちらを履修した上で本校を卒業することで、博物館学芸員資格を取得できます。
進学先を迷っている学生さんは、ぜひ以下から立正大学での学びをのぞいてみてくださいね。