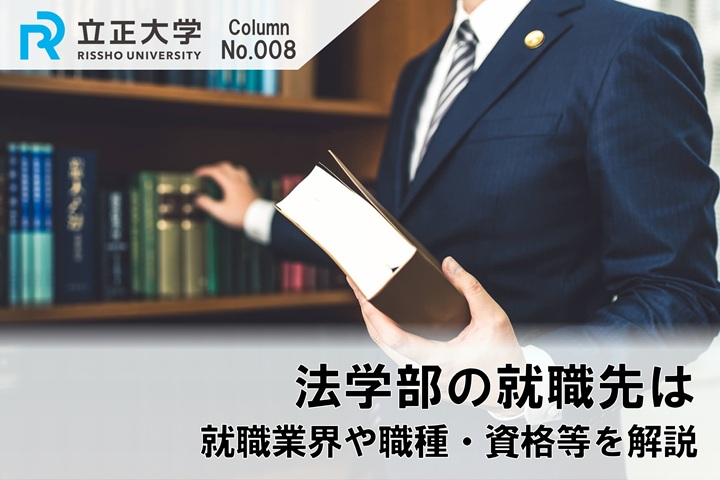証券アナリストとは 仕事内容やCMA資格について解説

証券アナリストは、株などの金融商品への投資を考えている方に対し、リターンやリスクを分析してアドバイスする仕事です。
NISAの拡充・恒久化などで、近年注目されている仕事でもあります。
今回は、そんな証券アナリストについて、仕事内容から年収、なる方法まで徹底解説。
証券アナリストの民間資格である「日本証券アナリスト協会認定アナリスト(CMA)」の取り方も詳しく解説します。
証券アナリストを目指す方、証券アナリストという仕事が気になる方は、ぜひ最後までご覧ください。
証券アナリストとは?
初めに、証券アナリストとはどんな仕事なのかを解説します。
-
証券アナリストとは
証券アナリストは、証券会社や運用会社などの金融機関において、企業を「投資」の面から分析・評価し、投資家がよりよい投資を行えるようサポートする仕事です。
「投資」というと、サポートの対象は株などを運用する投資家に限られるように一見思われますが、近年は「NISA」の登場で活躍の幅が一気に広がりました。
NISAは、正式には「少額投資非課税制度」といいます。NISAも投資の一つなので、証券アナリストの仕事の対象です。
また、2024年からは「新NISA」が始まり、NISAが拡大・恒久化されたことで、新しくNISAを始める方も増加傾向にあります。
NISAの拡大・恒久化と、それに伴うNISA利用者の増加により、証券アナリストは近年注目を浴びている仕事です。
-
仕事内容
証券アナリストは、主に証券会社や保険会社、銀行などの金融機関で働いています。
ほかにも、加入者から預かったお金を運用する年金基金などの機関や、一般企業の財務・IR部門で働く方も多いです。
仕事内容は、企業や市場の分析とお客さまのサポートが中心です。
担当する企業の業績や、専門とする業界の動向の調査・分析は継続的に行うと同時に、マクロ経済やミクロ経済など、経済全体の動きについても常に把握しておく必要があります。
調査・分析は、企業が出している決算情報などをもとにするだけでなく、実際にその企業を訪問して情報収集することも。
得られたデータから投資情報や今後の予測をレポートにし、お客さまに提供します。
さらに、お客さま一人ひとりの状況に応じた対応も多いです。
具体的には、資産運用のアドバイスや運用状況のモニタリング・報告、投資判断についてのアドバイスやリスク分析など、「投資家の頼れる相棒」としての役割も大きいといえるでしょう。
証券アナリストの年収

厚生労働省の「令和6年賃金構造基本統計調査」によると、証券アナリストの平均年収は903.2万円です。 一方で給与所得者全体の平均年収は、国税庁の「令和5年分 民間給与実態統計調査」によると460万円で、実に2倍近くの差があります。 この年収の高さは、主に仕事内容の専門性の高さや、成果報酬型の給与体系が影響しています。 証券アナリストは、業績に応じて給与にインセンティブが付けられるケースが多く、実力があればあるほど年収も高くなりやすいのです。加えて就業先が外資系企業だと、さらに給与がアップしやすく、年収1,000万円を大きく超す証券アナリストも少なくありません。
出典:令和6年賃金構造基本統計調査 結果の概況厚生労働省
出典:令和5年分 民間給与実態統計調査国税庁
証券アナリストになるには?
証券アナリストは、証券会社や保険会社、銀行などの金融機関や、資産運用会社に就職し、さまざまな経験を経た後になるのが一般的です。
学歴は、必須ではないものの大卒以上の方がほとんど。また、金融機関や資産運用会社への就職には、経営学部や経済学部、商学部、法学部だと有利になりやすいといわれています。
そのため、証券アナリストを目指すなら、まずは金融機関や資産運用会社への就職を目指すとよいでしょう。
また、こちらも証券アナリストになるために必須というわけではありませんが、金融業界で信頼性が高い民間資格に「日本証券アナリスト協会認定アナリスト(CMA)」があります。
名前のとおり、証券アナリストとしての知識を証明できる資格で、就職活動においても評価されやすい資格です。
CMAの詳細は次の項目で詳しく解説しますが、証券アナリストになりたい方は、CMAの資格を取得しておくのがおすすめです。
民間資格「日本証券アナリスト協会認定アナリスト(CMA)」について

ここからは、証券アナリストを目指す方はぜひ取得しておきたい、「日本証券アナリスト協会認定アナリスト(CMA)」について解説します。 CMAは、公益社団法人 日本証券アナリスト協会が認定する民間資格です。資格取得までには、指定の講座の受講や試験合格、一定の実務経験など、いくつかの要件があります。 ここからは、CMAの資格取得までの道のりや試験概要などを詳しく解説します。
出典:CMA資格公益社団法人 日本証券アナリスト協会
-
資格取得までの道のり
CMAの資格取得には、大きく分けて3つの壁があります。それが、「第1レベル講座の受講+受験」、「第2レベル講座の受講+受験」、そして「3年以上の実務経験」です。
第1レベル講座の受講+受験で合格後、第2レベル講座の受講+受験が可能になります。
第2レベル講座の合格後は、実務経験がその時点で3年以上あれば、ただちにCMA資格を取得できます。3年未満の場合は、その後実務経験が3年に達したタイミングで取得が可能になるという流れです。
ここからは、各段階の詳細を解説します。
-
第1レベル講座の受講+受験
CMAの講座は、第1レベルと第2レベルともに通信講座です。講座テキストによる自習形式で、学習を進めていくことになります。
第1レベル講座の受講が終わると、受講年度の翌年から試験を受けられるようになります。
受験が可能な期間は、受講年度の翌年から原則として3年間です。ただし、もし試験に合格できなくても、期限内に第1レベル講座を再受講すれば、受験可能期間を延長できます。
講座の開講期間は6月から翌年1月末までです。開講前の5月下旬から、申込受付が始まります。いつでも受講を開始できますが、学習時間確保のため、早めの申込・受講が勧められています。
-
第2レベル講座の受講+受験
第2レベル講座は、第1レベル講座の試験に合格した年度から受講可能です。
そして第2レベル講座の試験は、第1レベル講座同様、受講年度の翌年から受講できるようになります。
第2レベル講座も、受講年度の翌年から原則として3年間受験が可能です。合格できなかった場合も、期限内に第2レベル講座を再受講することで受験可能期間を延長できます。
講座の開講期間は8月から翌年3月末までです。開講の2カ月前である6月から、申込受付が始まります。いつでも受講を開始できますが、学習時間確保のため、早めの受講が勧められています。
-
3年以上の実務経験
3年以上の実務経験は、受講前でも後でもかまいません。第2レベル講座の試験合格前に3年以上の実務経験があれば、合格後すぐにCMA資格の取得が可能です。
第2レベル講座合格時点で実務経験が3年未満であれば、実務経験を経たのちに取得することになります。
なお実務経験とは、例えば以下が該当するとされています。
- 金融機関等における資産運用相談・証券投資・企業融資・リサーチレポートの作成・金融関連商品のITシステム開発等
- 事業会社における財務管理・分析・企画業務、IR業務、経済、産業、金融に関する調査・分析業務
- 監査法人における監査業務
-
試験概要
試験は、第1レベル講座に対応する第1次試験と、第2レベル講座に対応する第2次試験とで、スケジュールや試験内容が大きく異なるためご注意ください。
-
第1次試験
第1次試験は、第1レベル講座を受講した方が受験できます。
春と秋の年2回実施されており、春は4月下旬、秋は9月下旬または10月上旬です。
受験の申込受付期間は、試験日の約1カ月半前を期限として、1カ月程度取られています。
これまでは、各地の試験会場に赴いての受験が必須でしたが、2026年秋試験からはCBT方式が導入される予定です。
試験は3科目の科目別試験で、各科目に以下の学習分野が含まれます。
- 科目Ⅰ…証券分析とポートフォリオ・マネジメント
- 科目Ⅱ…財務分析 / コーポレート・ファイナンス
- 科目Ⅲ…市場と経済の分析 / 数量分析と確率・統計 / 職業倫理・行為基準
試験時間は、科目Ⅰが170分、科目Ⅱが100分、科目Ⅲが90分で、合計360分です。配点も試験時間と同様、科目Ⅰが170点、科目Ⅱが100点、科目Ⅲが90点で、合計360点となっています。試験は選択肢方式で、計算問題と穴埋め問題が含まれます。
合否結果は、春試験は6月上旬、秋試験は11月上旬に、日本証券アナリスト協会のマイページで確認できます。なお、最新の試験スケジュールは、必ず日本証券アナリスト協会の公式サイトで確認してください。
-
第2次試験
第2次試験は、第1次試験を合格し、第2レベル講座を受講した方が受験できます。
第1次試験と異なり、年に1回、6月上旬に試験が実施されます。
受験の申込受付期間は、3月中旬から4月中旬までの約1カ月です。
第1次試験はCBT方式が導入されますが、第2次試験は変わらず各地の試験会場での受験となります。
360点満点の総合試験で、試験形式は計算問題を含む記述式応用問題です。採点に際しては、解答に至る過程も考慮されます。
合否結果は、8月中旬~下旬ごろに日本証券アナリスト協会のマイページから確認できます。
なお、最新の試験スケジュールは、必ず日本証券アナリスト協会の公式サイトで確認してください。
CMA第1次レベル講座 試験に備える・申込む公益社団法人 日本証券アナリスト協会 -
合格率・難易度
合格率は、第1次試験と第2次試験ともに、例年50%前後で推移しています。
直近5年間の合格率は、それぞれ以下のとおりです。
≪第1次試験≫年 合格率(春) 合格率(秋) 2025年 48.4% - 2024年 46.5% 49.9% 2023年 46.4% 50.5% 2022年 48.6% 47.0% 2021年 51.8% 53.8%
≪第2次試験≫年 合格率 2024年 44.6% 2023年 46.7% 2022年 54.8% 2021年 52.1% 2020年 53.4%
約半数の方が合格しているので、難易度はそこまで高くはないと思う方もいるかもしれません。ただし、CMAの試験は日本証券アナリスト協会指定の講座を受講した上で受験するものです。 受験者が基本的に同じ内容を学習していると考えると、決して難易度が高くないとはいえないでしょう。
また、一般的に、CMAの試験に合格するには計200時間の勉強時間が必要といわれています。もちろん、初級者の方や実務経験がある方など、人によって必要な勉強時間は前後するでしょう。
CMAの講座は、講座テキストを用いた自己学習が基本です。取り組み方次第で試験の合否も左右されるので、満点合格を目指すつもりで学習を進めてください。
-
資格取得までにかかる費用
CMAの資格取得までには、各ステップで比較的大きな費用がかかります。資格取得までにかかる費用と、資格取得以降にかかる費用をまとめました。(2025年8月時点)
≪資格取得までにかかる費用(税込)≫第1レベル講座 一般受講者:66,000円 会員受講者:60,000円(法人会員等の役職員の方) 第1次試験 科目Ⅰ:7,000円+手数料200円 科目Ⅱ:3,500円+手数料200円 科目Ⅲ:3,500円+手数料200円 第2レベル講座 63,000円 第2次試験 16,500円+手数料200円
≪資格取得以降にかかる費用≫第2次試験に合格し、なおかつ実務経験が3年以上ある方は、日本証券アナリスト協会の検定会員に入会することで晴れて「日本証券アナリスト協会認定アナリスト」の資格を取得できます。入会金 10,000円 年会費 18,000円(満65歳以上の方は12,000円)
ただし、入会には上記の費用がかかり、入会後も資格を維持するために年会費がかかり続けます。CMAの資格取得を目指すのであれば、上記の費用がかかることも考慮しておきましょう。
まとめ
まとめテキスト証券アナリストは、投資を考えているお客さまがよりよい投資を行えるようサポートする仕事です。
証券アナリストになるには、まず金融機関や資産運用会社で実務経験を積むことが一般的。民間資格の「日本証券アナリスト協会認定アナリスト(CMA)」の取得を目指すのもおすすめです。
証券アナリストを目指すなら、大学、特に経営学部や経済学部、商学部、法学部に進学すると、証券アナリストに必要な知識を得られるだけでなく、就職にも有利になりやすいです。
立正大学の経営学部と経済学部、さらに法学部では、それぞれで将来を見据えた実践的な学修を実施しています。気になる方は、ぜひ以下から立正大学の各学部についてもご覧ください。