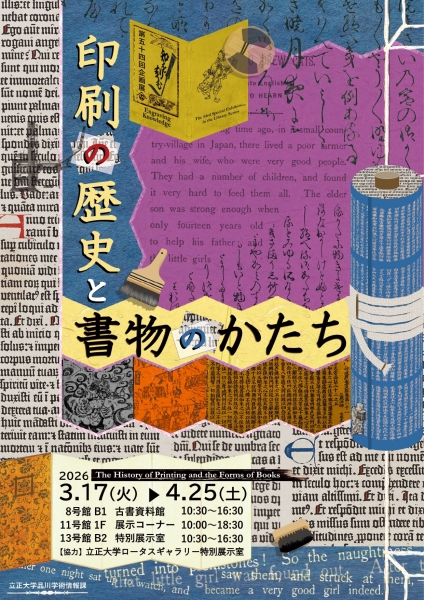令和7年度 館務実習生ミニ展 立正大学博物館所蔵の古代瓦~文字瓦を中心に~
企画概要
今年度、当館において博物館実習を行いました館務実習生が、自分たちが決めたテーマに基づき、館内収蔵品より展示品を選び、展示パネルやキャプションの作成・設置など、展示にかかる一連の作業をすべて行っています。
今年度は館内収蔵品より、博物館のある埼玉県内を中心とした窯跡から発掘された古代瓦のうち、文字瓦と呼ばれるものを中心に展示しています。
文字瓦について
瓦の一部に、郡などの頭文字などが記されているものを「文字瓦」と言います。
度重なる飢饉や疫病と内政の混乱から脱するため、仏教による鎮護国家を目指そうと考えた聖武天皇は、天平13(741)年に「国分寺建立の詔」を発布しました。
武蔵国(東京都・埼玉県・神奈川県の一部)でも国分寺の建立が行われましたが、寺院の建立には荘厳にするための瓦が大量に必要となります。このため、武蔵国には末野(寄居町)、南比企(鳩山町)、東金子(入間市)、南多摩(稲城市・多摩市・八王子市など)の各地に窯が築かれ、多くの瓦が生産されました。
本学では昭和30年代以降、これらの窯跡の発掘調査に取り組んでおり、当館には多くの出土品が収蔵されています。今回の展示は、調査資料の利活用展示となります。
学芸員養成教育について
博物館実習は、博物館法施行規則第1条に基づき、大学において修得すべき博物館に関する科目の一つであり、登録博物館又は博物館指定施設(大学においてこれに準ずると認めた施設を含む)における実習により修得するものです。
博物館概論、博物館経営論、博物館資料論、博物館資料保存論、博物館展示論、博物館情報・メディア論、博物館教育論などの講義を通じ、広範にわたる専門的な事項について理論的・体系的に学んできた技術や知識を、現場で博物館資料を取り扱ったり、利用者に対応したりするなどの実践的な経験や訓練を積むことによって、博物館の専門的職員である学芸員としての基本的な素養を身につけるための実習となります。
当館は県内の大学としては数少ない、大学が設置する博物館指定施設であり、例年実習希望者の受け入れを行っています。
実施概要
会期 令和7年8月16日(土)~9月27日(土) 全26日間
会場 立正大学博物館 1階第1展示室
(埼玉県熊谷市万吉1700 立正大学熊谷キャンパス内)
開館時間 午前10時より午後4時まで
休館日 火・土・日曜日
※8月16日(土)・17日(日)と9月27日(土)は特別開館を実施します
展示概要
展示については当館収蔵品のうち、新久窯跡(埼玉県入間市)および新沼窯跡(埼玉県鳩山町)から出土した文字瓦より、次の資料のケース展示およびパネル解説を行います。
・「久」久(く)良(ら)郡(現・神奈川県横浜市付近)
・「大」大里郡(現・埼玉県熊谷市付近)
・「播」播(は)羅(ら)郡(現・埼玉県熊谷・深谷市付近)
・「高」高麗郡(現・埼玉県日高市・鶴ヶ島市付近)
・「父」秩父郡(現・埼玉県秩父市付近)
・「男」男(お)衾(ぶすま)郡(現・埼玉県熊谷市・寄居町などの一部)
・「豊」豊島郡(現・東京都荒川、板橋、豊島、文京、新宿区の全域、および港、渋谷、千代田区の一部)
・「入」入間郡(現・飯能市・日高市・鶴ケ島市)

博物館へのアクセス
熊谷駅(JR高崎線、新幹線、秩父鉄道)利用の場合
熊谷駅南口より国際十王バス立正大学行または森林公園駅行に乗車(約10分)
立正大学下車
森林公園駅(東武東上線)利用の場合
森林公園駅北口より国際十王バス立正大学行または熊谷駅行に乗車(約12分)
立正大学下車
交通アクセスのご案内はこちらをクリックしてください。
問い合わせ先
立正大学博物館 博物館事務課(担当:草川)
電話:048-536-6150
e-mail:kusakawa【※】ris.ac.jp
※掲載メールアドレスの注意点
迷惑メール対策のため各アドレスの”@”の部分は”【※】”に変えて掲載しております。
メールを送る際は”【※】”の部分を @ に変えてください。