川村ゼミの学生が「社長弟子入りウィーク」に参加し、企業経営者と交流しました。

2025年8月25~29日の5日間、川村ゼミの3年生9名が「社長弟子入りウィーク」に参加しました。川村ゼミとしては2年連続の参加となります。
東京中小企業家同友会様が主催する社長弟子入りウィークは、以下の2点を目的として開催されました。
①第一線で活躍している経営者に密着して経営者の行動や発言に触れ、ビジネスの最前線を肌で体験するとともに今後の就職を考える糧とする。
②特別ワークショップや業界研究会に参加し、より多くの業種について企業研究を行う。また様々な経営者と語り合い、今後取り組む就職活動の「考え方や心構え」を学ぶ。
企業で働く先輩社員との交流や経営者の考えに触れ、普段接することのないビジネスの現場を体験することができ、大学で行われる授業では得られない学びを得ることができました。
さらに代表して3名が、この社長弟子入りウィークを通じて得た学びについて取り上げます。
3年 木永梨咲
今回の弟子入りウィークで、1~2日目に道路設計など建設コンサルタントを行っている会社、3日目に社会インフラに関するシステムの開発など行うIT業界の会社、4日目には建築設備の企画や設計、施工管理に従事している建設業の会社に行きました。

1社目 株式会社計画設計様
1社目では、1日目に設計コンサルタントの業務について学び、2日目には実際に道路設計に取り組む本格的な業務体験をさせていただきました。先輩社員とのお話や、会社での業務体験によって現場の方の姿勢に触れることができ、働くイメージがより具体的なものになりました。また、普段目にする道路や社会インフラを利用者の視点だけでなく、作る・管理する側からも考えるようになり、社会を支える仕組みへの理解が深まりました。
さらに社長から、「社会貢献とは?」という問いかけをいただき、改めて考える機会となりました。社会貢献にはさまざまな形があり、必ずしも感謝されることや、すぐに成果が目に見えるものではないというお話が印象に残っています。社会貢献には多様な形があると知り、今後何を大切にしたいかという自分の軸を見つめなおす機会になりました。
2社目 株式会社RayArc様
コンピューターシステムにおけるソフトウェア開発を中心に行っている会社で業務を体験しました。午前中にIT業界について学び、午後には社長、先輩社員、社会保険労務士の方々からお話を伺いました。IT業界では文系未経験の学生が就職する事例も多いと知り、自分の進路を考えるうえで視野を広げるきっかけになりました。これまでIT業界には漠然としたイメージしか持っていませんでしたが、社会に広く影響を与え、基盤から支える重要な役割を担っていることを学びました。
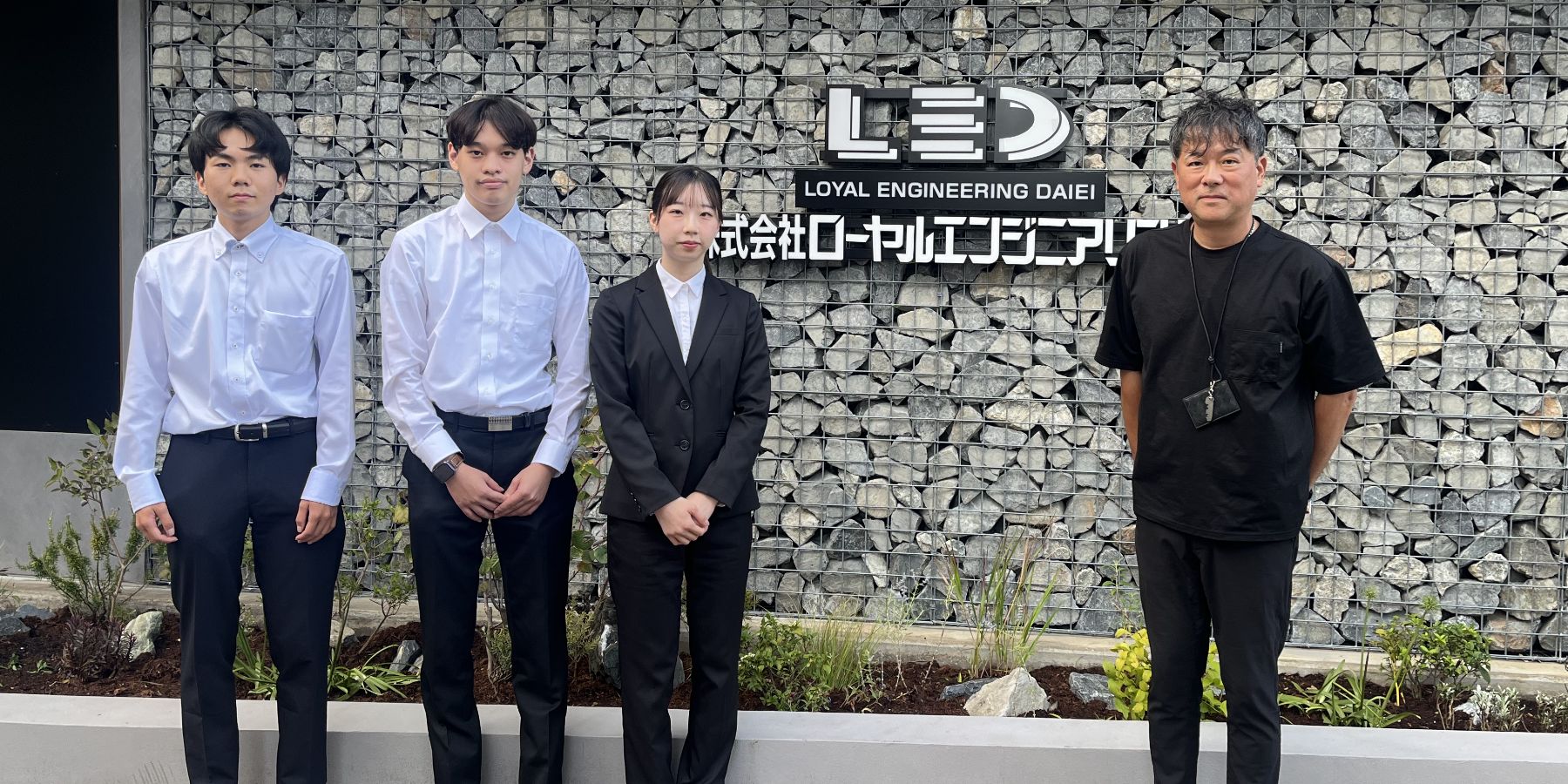
3社目 株式会社ローヤルエンジニアリング様
3社目では午前中に建設業について学び、午後には社長講話に加えて信用金庫の支店長や課長、税理士の方々からお話を伺いました。建設業には建築設備や土木工事など多様な種類があり、知らないことばかりで新鮮な学びとなりました。また、午後の社長講話では過去の失敗から得られた経験や目標と目的の違いについてなど貴重なお話を伺うことができました。さらに、普段関わることのない信用金庫の支店長、税理士の方々のお話を伺い、銀行の役割や税務の重要性について学ぶことができ、とても有意義な時間となりました。
4日間、経営者の行動や発言に触れ、表層的な部分をみるのではなくその背景にある考え方や学びを大切にされていると感じ、模範にしたいと感じました。社長の過去の経験や、社会貢献について考える時間、また普段関わることのない方とのお話を通じて、就職活動の軸を広げるきっかけにもなりました。
3年 渡部風花
私は、卸売・小売業を展開する 株式会社五十嵐商会様と、IT企業の アドバンスト・ソフト様の2社で研修を行いました。それぞれの現場で、貴重な体験と学びを得ることができました。
1社目 株式会社五十嵐商会様
五十嵐商会様は、卸売・小売業を通じて「ネットワーク」「フットワーク」を大切にし、人と人、人とモノをつなぐことを理念に掲げています。子ども食堂の支援、大学バスケットボール大会の共催、日本語学校との交流など、地域貢献活動にも積極的に取り組んでいます。

1日目:営業・配達に同行
一日で7社を訪問し、名刺交換やお客様との会話を体験しました。企業訪問では五十嵐商会様の取引先が立正大学の教科書を取り扱っていることを知り、大学とのつながりを実感しました。また、「安全運転」、「新規顧客の開拓」、「顔を合わせて話すこと」を大切にしている姿勢から、地域密着型営業の重要性を学びました。
2日目:店舗業務を体験
在庫補充や棚卸、SNS(Instagram)での情報発信を行い、裏方の作業と発信の両面を経験しました。お客様との接点を支える日常業務の大切さを学ぶとともに、地域との関係づくりを支える仕組みを理解することができました。

2社目 株式会社アドバンスト・ソフト様
創立40周年を迎えたアドバンスト・ソフト様は、システム開発から運用までを担うIT企業です。経営者交代の際には社員全員で経営理念について考えたそうです。企業全体で理念を共有する姿勢が印象的でした。また、CSR活動として日本国内だけでなくインドネシア・タイ・フィリピンで子ども向けプログラミング教室を開催し、海外人材の雇用にも積極的に取り組むなど、グローバルな視点で社会に貢献しています。
1日目:Scratchプログラミングに挑戦
朝のミーティングでは、一人ひとりが経営理念をどう捉え、今後どう活動していくかを1分間で共有し、さらに3人による1分間スピーチでコミュニケーションを深めていました。午後には社長と株式会社ベルチャイルド様とのZoom意見交換に参加し、IT企業間のつながりや課題解決の重要性を学びました。その後、Scratchを使ったプログラミングに初挑戦し、難しさを感じつつもプログラムが動く面白さを体験しました。
2日目:自己紹介文のプログラム作成
首都圏物流事業組合様とのZoom意見交換に参加しました。業界全体の課題や取り組みについて伺い、社会とのつながりを実感しました。その後は、自分自身を紹介する文章をプログラミングで表現する課題に挑戦。コードを通して自己表現を行うという新しい学びを得ました。

五十嵐商会様では「地域との直接的なつながり」、アドバンスト・ソフト様では「ITによる社会との広がり」を体感しました。異なる業種を経験することで、どちらの企業も経営理念を大切にし、「人と人とのつながり」を重視している点が共通していると気づきました。また、社員と社長との距離が近く、雰囲気がとても良かったことも印象的でした。今回の研修で得た学びを、今後の学生生活や将来のキャリアに活かしていきたいと思います。
3年 齋藤あかり
私は、今回の弟子入りウィークで1社目に医療ITの導入・運用・保守を行っている会社、2社目にETCカードやガソリンを共同購入・共同利用をすることで企業を支える組合に行きました。

1社目 株式会社デジタルソリューション様
1日目は、朝礼と会議に参加し、事業説明をしていただきました。ITは意外と身近な部分で活躍していること、そしてなくてはならないものだということを実感しました。2日目には、実際に同社による「医療費後払いシステム」が導入されている病院の見学に行き、待ち時間短縮や従業員の負担軽減などの効果を感じることができました。また、社長とお話しをした際には、「社員さんには長く働いてもらいたい」という経営者として社員を大切にする思いを知ることができました。IT企業はパソコンに向かって黙々と作業するイメージを持っていましたが、自分の好きな環境で働くことができ、かつ現場を訪問して多くの人と関わるという事を知り、企業イメージが大きく変わったインターンシップでした。
2社目 首都圏物流事業共同組合様
1日目は、朝礼に参加して代表理事から経歴や組合理念についてお話しいただきました。代表理事は、人とのつながりを大事にされており、社員の居場所になるような会社づくりに努めていることを知りました。組合としても「人と企業をつなぐ」という理念を掲げており、良質な情報発信を行い、企業同士をつなぐ多くの社会貢献に繋がっているのだと感じました。
2日目は、事業内容を説明していただいた後、社員の皆さんとチームビルディングを目的としたゲームを行いました。この2日間を通じて、色々な取り組みを柔軟に取り入れているなど1つのチームとして働かれている様子を見て中小企業ならではの魅力を実感しました。また、経営理念の重要性や自分がどういった場所で働きたいのかを考える貴重な機会になりました。

最終日
特別ワークショップ「先輩社員・経営者と語る」・業界研究会
5日目には社長弟子入りウィークの学生参加者全員が集まり、社員の方や経営者の方も交えて8グループに分かれて参加し、期間中に感じたことを話し合いました。感想は人それぞれでしたが、多くの学生が今後の就職活動に役に立ったと感じていました。また、働くこと、就職活動で大切にしたいことについてもグループで話し合いました。働くことについてはこれまで漠然としたイメージしかありませんでしたが、自分の指針となるものという先輩社員の方の言葉が印象に残っています。自分が何を大切にしたいかを考えるきっかけになりました。このグループワークを通じて多様な意見を聞くことができ、自分にはなかった考えや視点に触れることができ、大きな学びとなりました。
午後には業界研究会に参加しました。これまで視野に入れていなかった業界の話を聞くことができ、新しい発見や考え方に触れる良いきっかけとなりました。

編集後記
4日間、経営者に密着した経験を通じて社長の考え方や会社を経営するうえでの大切な視点に触れ、日々の意思決定の重さや責任の大きさを実感しました。実際に体験する中で、当初抱いていたイメージと異なることが多く、職業に対する固定概念を払拭しようと思えるきっかけになりました。そのうえで、自分のやりたいことや興味のあることに挑戦していきたいという前向きな考えを持つことができました。
今回得た気づきを活かし、今後の進路選択や自己成長につなげていきたいと考えています。このような貴重な機会をいただき、企業の皆様には心から感謝申し上げます。
執筆・編集
木永梨咲、渡部風花、齋藤あかり