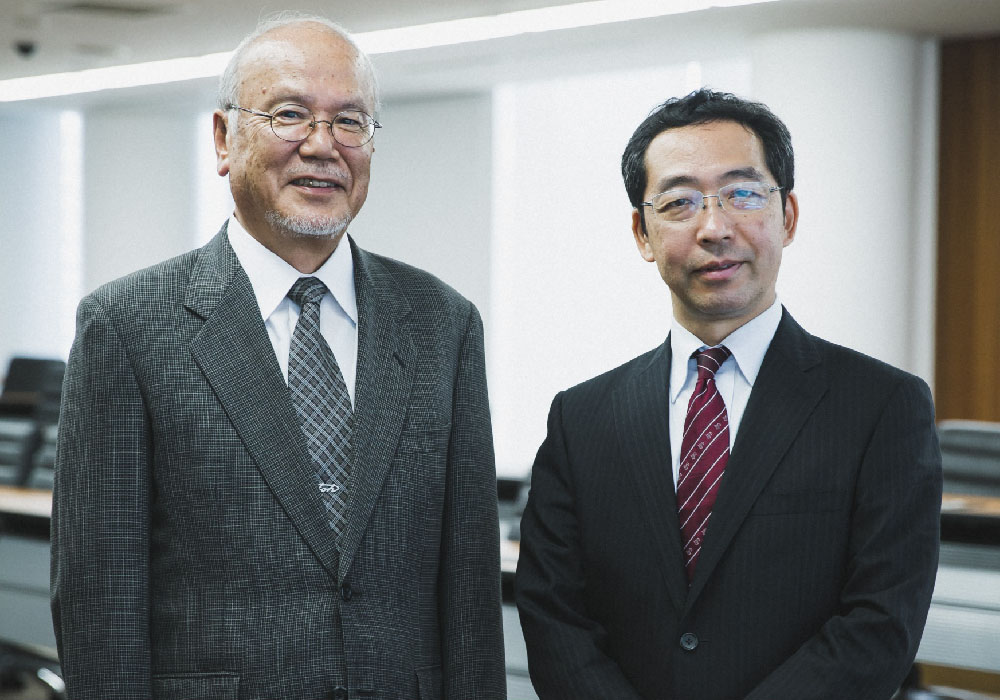学部長経験者に聞く 経営学部の歴史と未来
経営学部が日本の大学を背負って立つという夢を持っています。

突然のFAXで英国から単身帰国し、学部長に就任

宮川 本日は、経営学部長を3回もお務めになった加藤吉則先生においでいただきました。
私が1993年に本学の専任講師に就任したときの学部長が加藤先生でした。加藤先生の時代は、ある意味で経営学部が最も変革した時代であり、その遺産が現在まであるように思います。当時を振り返ってみて、さまざまな困難を乗り越えてあれほど大きな改革を成し遂げることができた要因は何だったのかと、改めて思いました。
加藤 私が最初に経営学部長になったときは、ドラマチックないきさつがありましたね。1992年に、私は客員教授として英国のスターリング大学におりました。そこに立正大学からFAXが入り、経営学科に昼夜開講制の夜間主コースをつくるから手伝うようにと。私は家族を残して急遽、単身帰国したのです。原案を作成して文部省と交渉を重ねたのが、学部長に就任したばかりの私の主な仕事でした。
建学の精神と「モラリスト×エキスパート」
宮川 加藤先生が常任理事を経て再び学部長に就任なさったときは、経営学部創立40周年を記念する企画がかなり進んでいたと思います。
加藤 そうでしたね。経営学部の教育を紹介し、PRにもなるような『人がいきる組織―共創が働き方を変える』という本を出しました。この本は、現在、本学のブランドビジョンとして展開されている「モラリスト×エキスパート」を単なる掛け声に終わらさず、教育のミッションとして学部教育に落とし込むためのものとして出版されました。
 そもそも、このブランドが創られたのは2005年頃ですが、当時の立正大学は教育改革や財政改革の成果も上がって、雑誌『週刊東洋経済』の「大学格付ランキング」で全国1位に位置付けられるまでになっていました。そこで次のイノベーションの手がかりを得るために、社会的な視点から学校法人の総合能力を評価してもらう格付けをとりました。格付会社R&Iの評価はA+でした。雑誌ではランキング1位の本学は、早稲田大学、慶應義塾大学のAA+より低かったのです。少しがっかりしましたが、その原因は「競争力とブランド力」の不足にありました。教育方針や教育内容が社会に知られておらず、したがって本学についての具体的なイメージが定着していないとのことでした。「大学冬の時代」にあって、認知度を上げて競争力を高めるには、大学のブランド力が重要だったのです。
そもそも、このブランドが創られたのは2005年頃ですが、当時の立正大学は教育改革や財政改革の成果も上がって、雑誌『週刊東洋経済』の「大学格付ランキング」で全国1位に位置付けられるまでになっていました。そこで次のイノベーションの手がかりを得るために、社会的な視点から学校法人の総合能力を評価してもらう格付けをとりました。格付会社R&Iの評価はA+でした。雑誌ではランキング1位の本学は、早稲田大学、慶應義塾大学のAA+より低かったのです。少しがっかりしましたが、その原因は「競争力とブランド力」の不足にありました。教育方針や教育内容が社会に知られておらず、したがって本学についての具体的なイメージが定着していないとのことでした。「大学冬の時代」にあって、認知度を上げて競争力を高めるには、大学のブランド力が重要だったのです。
そこで、建学の精神の根底にあるミッションを現代化することで、『「モラリスト×エキスパート」を育む』というブランドを創造することとなりました。このフレーズは商標権を取得しました。
本学の建学の精神の淵源である仏教の「共生の精神」を経営教育のミッションに据えて立正ブランドを考えた本が、『人がいきる組織―共創が働き方を変える』だったのです。経営学の対象であるビジネスは、一人の独創的な天才だけで成功するわけではありません。僕たちのような普通の人間が共鳴し合い、共創することで特別なことを成し遂げることもできます。共創とは同じ価値観の者が寄り集まるのではなく、ミッションを共有した異質な者同士がぶつかりあいながら、混沌としたカオスの中から新しい何かを創造していく営みなのですから。
教育の原点は当事者として学び、考えること
宮川 経営学部50周年のコンセプトとして「信頼し、信頼される教育」といったことを考えているのですが、これも共創の概念から来たものです。
 加藤 教育というのは、学生に対してどれだけ当事者意識を持たせることができるかがポイントだと思います。ある問題について、他人事として考えていると、本当の意見は出てきません。「あなたは、それを本当に実行できるのか」と問われて、初めて悩む。信頼し合う前に、その信頼される人間が当事者としての意識や自覚をどれだけ持てるかということが、教育による人づくりの根幹だと思っています。
加藤 教育というのは、学生に対してどれだけ当事者意識を持たせることができるかがポイントだと思います。ある問題について、他人事として考えていると、本当の意見は出てきません。「あなたは、それを本当に実行できるのか」と問われて、初めて悩む。信頼し合う前に、その信頼される人間が当事者としての意識や自覚をどれだけ持てるかということが、教育による人づくりの根幹だと思っています。
例えばいじめの問題でも、いじめられる子どもの気持ちは分かるかもしれませんが、いじめる子どもの気持ちはどうなのかと考えていかないと、一方的な見方になってしまって問題解決につながりにくい。自分が加害者になった場合を考え、加害者がどうしてそこに至ったかを考えないとだめではないかと思います。
ですから、キーワードは「当事者」ではないでしょうか。自分が参加しなければ、何一つ身に付きません。いまはスマートフォンで文字情報をやりとりする時代ですが、教室という一つの空間に学生が集まり、教員と面と向かって、つまり当事者として学び、考えるところに教育の原点があると思っています。